要旨
令和7年10月1日より施行される改正育児・介護休業法は、労働者が仕事と育児・介護を両立できる環境の整備を目的としています。本改正の核心は、事業主に対する新たな義務の導入と、それを支援する助成金制度の拡充にあります。
主要なポイントは以下の通りです。
- 柔軟な働き方の措置義務化
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のため、事業主は「フレックスタイム制」や「テレワーク」など5つの選択肢から2つ以上の措置を講じることが義務付けられます。 - 個別の周知・意向確認の義務化
子が3歳になる前の労働者に対し、導入した制度の個別周知と利用意向の確認が必須となります。また、妊娠・出産を申し出た労働者等から仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、配慮する義務も課されます。 - 両立支援等助成金の拡充
法改正に伴い、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が刷新されます。柔軟な制度を3つ以上導入し、利用実績があった場合に助成金が支給されるなど、企業の取り組みを経済的に後押しする内容となっています。
本記事では、これらの法改正の具体的な内容と、事業主が活用できる助成金制度の詳細を網羅的に解説します。
関連資料
解説動画
1. 育児・介護休業法の改正内容(令和7年10月1日施行)
1.1 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(義務化)
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の5つの措置の中から2つ以上を選択し、講じる義務があります。
| 措置の分類 | 措置の名称 | 具体的な内容 |
| 始業時刻等の変更 | ①フレックスタイム制 ②時差出勤制度 | 一日の所定労働時間を変更しないこと。 |
| 場所の柔軟化 | テレワーク等 | 一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上時間単位で利用できるもの。 |
| 保育サービスの提供 | 保育施設の設置運営等 | 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜を供与するもの。 |
| 新たな休暇の付与 | 養育両立支援休暇 | 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇。一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上、原則として時間単位で取得できるもの。 |
| 労働時間の短縮 | 短時間勤務制度 | 一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの。 |
1.2 個別の周知・意向確認の義務化
A. 柔軟な働き方に関する措置の周知・意向確認
- 対象者:
3歳未満の子を養育する労働者 - 時期:
子が3歳になるまでの適切な時期(具体的には、子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間) - 周知事項:
・事業主が選択した上記2つ以上の措置の内容
・措置の申出先(例:人事部)
・所定外労働(残業)の免除、時間外労働の制限、深夜業の制限に関する制度 - 方法:
以下のいずれか。ただし、FAX・電子メール等は労働者が希望した場合に限る。
・面談(オンラインも可)
・書面交付
・FAX
・電子メール等
B. 仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮
- 時期:
1. 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時
2. 労働者の子が3歳になるまでの適切な時期(上記A. と同様の期間) - 聴取内容:
子や家庭の事情に応じた、仕事と育児の両立に関する労働者の意向
◦ 勤務時間帯(始業・終業時刻)
◦ 勤務地(就業の場所)
◦ 両立支援制度等の利用期間
◦ その他、仕事と育児の両立に資する就業条件(業務量、労働条件の見直し等) - 方法:
上記A. と同様 - 事業主の責務:
聴取した労働者の意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
2. 両立支援等助成金の改正内容(令和7年10月~)
法改正に伴い、中小企業事業主等を対象とした両立支援等助成金が拡充されます。
2.1 柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児を行う労働者のための柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、利用実績があった場合に助成されます。
- 基本助成:
◦ 対象制度を3つ導入し、対象労働者が利用した場合: 20万円
◦ 対象制度を4つ以上導入し、対象労働者が利用した場合: 25万円
◦ 対象制度(※):
▪ フレックスタイム制度または時差出勤制度
▪ 育児のためのテレワーク
▪ 柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度
▪ 保育サービスの手配及び費用補助
▪ 養育両立支援休暇制度 (※) 3歳以降小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる制度であること。
◦ 支給上限:
1事業主あたり5人まで。 - その他の助成対象:
◦ 子の看護等休暇制度の整備: 30万円
▪ 法で求める内容を上回る有給の休暇制度で、以下の要件を全て満たすもの。
• 有給休暇であること(年次有給休暇を除く)。
• 年度内に10日以上付与されること。
• 時間単位で取得でき、始業・終業時刻と連続しない「中抜け」が可能であること。
• 一日の所定労働時間を変更せずに利用できること。
◦ 対象者の拡大: 20万円加算
▪ 上記①(基本助成)や②(子の看護等休暇)の制度を、中学校修了までの子を養育する労働者が利用可能とした場合。
◦ 情報公開: 2万円加算(変更なし)
▪ 育児休業取得状況等の情報を指定のWEBサイト上で公開した場合。
2.2 関連する両立支援助成金
法改正への対応と合わせて、以下のコースの活用も推奨されています。
A. 出生時両立支援コース
- 概要
男性の育児休業取得を促進するための助成金。 - 主な要件:
◦ 男性労働者が子の出生後8週間以内に育児休業を取得すること
◦ 事業年度における男性の育児休業取得率が上昇すること。 - 助成額の例:
◦ 育休取得率が30ポイント以上上昇し、かつ50%以上を達成した場合: 60万円
◦ (例)事業年度①で33%(3人中1人取得)→ 事業年度②で100%(2人中2人取得)の場合に対象となり得る。
B. 育休中等業務代替支援コース
- 概要: 育休取得者や短時間勤務者の業務を代替する体制を整備する事業主を支援する助成金。
- 支援内容:
◦ 業務代替手当:
育休取得者の業務を代替する労働者に支給した手当総額の3/4を助成(上限: 月10万円、12ヶ月まで)
◦ 新規雇用・派遣:
代替要員を新規雇用した場合、代替期間に応じて9万円~67.5万円を助成。
◦ 業務体制整備経費:
体制整備にかかった経費として6万円を助成(外部専門事業者に委託した場合は20万円)。
3. ガイド:Q&A
問1. 令和7年10月以降、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、どのような措置を講じる義務を負いますか?
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、法律で定められた5つの措置の中から2つ以上を選択し、講じる義務を負います。これにより、育児期にある労働者がより柔軟な働き方を選択できるよう支援することが求められます。
問2. 事業主が選択できる「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」を5つのうち3つ挙げてください。
5つの措置のうち3つは、①フレックスタイム制または時差出勤制度、②テレワーク等、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇の付与、⑤短時間勤務制度です。事業主はこれらのうちから2つ以上を選択して導入します。
問3. 3歳未満の子を養育する労働者に対し、事業主はいつ、どのような目的で「個別の周知・意向確認」を行わなければなりませんか?
3歳未満の子を養育する労働者に対し、子が3歳になるまでの適切な時期(具体的には子が1歳11か月から2歳11か月に達するまでの1年間)に、事業主は選択した柔軟な働き方の制度を周知し、労働者の利用意向を確認する目的で行わなければなりません。
問4. 事業主が労働者の仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取すべき時期は、主に2つあります。それはいつですか?
意向聴取を行うべき時期は、①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時、②労働者の子が3歳になるまでの適切な時期(1歳11か月から2歳11か月に達するまでの1年間)の2つです。
問5. 両立支援等助成金の「柔軟な働き方選択制度等支援コース」とは、どのような目的で事業主に支給される助成金ですか?
この助成金は、育児を行う労働者のために柔軟な働き方を可能とする制度を3つ以上導入し、実際にその制度を利用した労働者が出た場合に、その取り組みを支援する目的で事業主に支給されます。
問6. 「柔軟な働き方選択制度等支援コース」において、事業主が4つ以上の柔軟な働き方に関する制度を導入し、労働者が利用した場合、いくらの助成金が支給されますか?
事業主が4つ以上の柔軟な働き方に関する制度を導入し、対象となる労働者がそれを利用した場合、25万円の助成金が支給されます。なお、支給対象は1事業主あたり5人までです。
問7. 「出生時両立支援コース」の助成金を受けるためには、男性労働者の育児休業取得に関してどのような要件を満たす必要がありますか?
男性労働者が子の出生後8週間以内に育児休業を取得すること、および事業所全体の男性育児休業取得率が前事業年度と比較して大幅に上昇する(例:30ポイント以上アップし、かつ50%以上を達成する)ことなどの要件を満たす必要があります。
問8. 「育休中等業務代替支援コース」は、事業主がどのような取り組みを行った場合に支援を受けられる制度か、2つの具体例を挙げて説明してください。
このコースでは、①育休取得者や短時間勤務者の業務を代替する他の労働者に対して手当を支給した場合、②育休取得者の業務を代替するために新たな人員を雇用、または派遣労働者を受け入れた場合に支援を受けられます。
問9. 事業主が労働者に対して柔軟な働き方の制度について個別に周知する際、伝えなければならない事項を3つ挙げてください。
周知すべき事項は、①事業主が選択した2つ以上の対象措置の内容、②対象措置の申出先(例:人事部など)、③所定外労働の免除や時間外労働・深夜業の制限に関する制度の3つです。
問10. 事業主は、労働者から聴取した仕事と育児の両立に関する意向に対して、法的にどのような対応を求められていますか?
事業主は、労働者から聴取した仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければならないと定められています。
4. 重要用語集
| 用語 | 定義 |
| 育児・介護休業法 | 労働者が育児や介護と仕事を両立できるように支援するための法律。令和7年10月に、育児期の柔軟な働き方の拡充などを内容とする改正法が施行される。 |
| 柔軟な働き方を実現するための措置 | 事業主が3歳から小学校就学前の子を持つ労働者のために、5つの選択肢(時差出勤、テレワーク等、保育施設、養育両立支援休暇、短時間勤務)から2つ以上講じなければならない制度。 |
| 時差出勤制度 | 始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度。1日の所定労働時間は変更しない。 |
| テレワーク等 | 1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上、時間単位で利用できる在宅勤務などの働き方。 |
| 養育両立支援休暇 | 子の養育と仕事の両立を容易にするための休暇。1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上、原則として時間単位で取得できる。 |
| 短時間勤務制度 | 1日の所定労働時間を短縮する制度。原則6時間とする措置を含む。 |
| 個別の周知・意向確認 | 事業主が3歳未満の子を持つ労働者に対し、子が3歳になる前の適切な時期に、導入している柔軟な働き方制度の内容を伝え、利用意向を確認する義務。 |
| 個別の意向聴取・配慮 | 事業主が、労働者からの妊娠・出産等の申出時や子が3歳になる前の時期に、仕事と育児の両立に関する意向(勤務時間、勤務地等)を個別に聴き取り、配慮する義務。 |
| 両立支援等助成金 | 仕事と家庭の両立を支援する取り組みを行う事業主に対して支給される助成金。複数のコースが存在する。 |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 育児中の労働者のための柔軟な働き方制度を3つ以上導入し、利用実績があった事業主に支給される助成金。 |
| 子の看護等休暇制度 | 育児・介護休業法第16条の2に定められた、子の看護等のための休暇制度。助成金の加算要件として、有給、年10日以上付与、「中抜け」可能などの条件が示されている。 |
| 出生時両立支援コース | 男性の育児休業取得を促進するための助成金。子の出生後8週間以内の育休取得や、事業所全体の男性育休取得率の上昇が要件となる。 |
| 育休中等業務代替支援コース | 育休取得者や短時間勤務者の業務を代替する体制を整備した事業主を支援する助成金。代替者への手当支給や、代替要員の新規雇用などが対象。 |
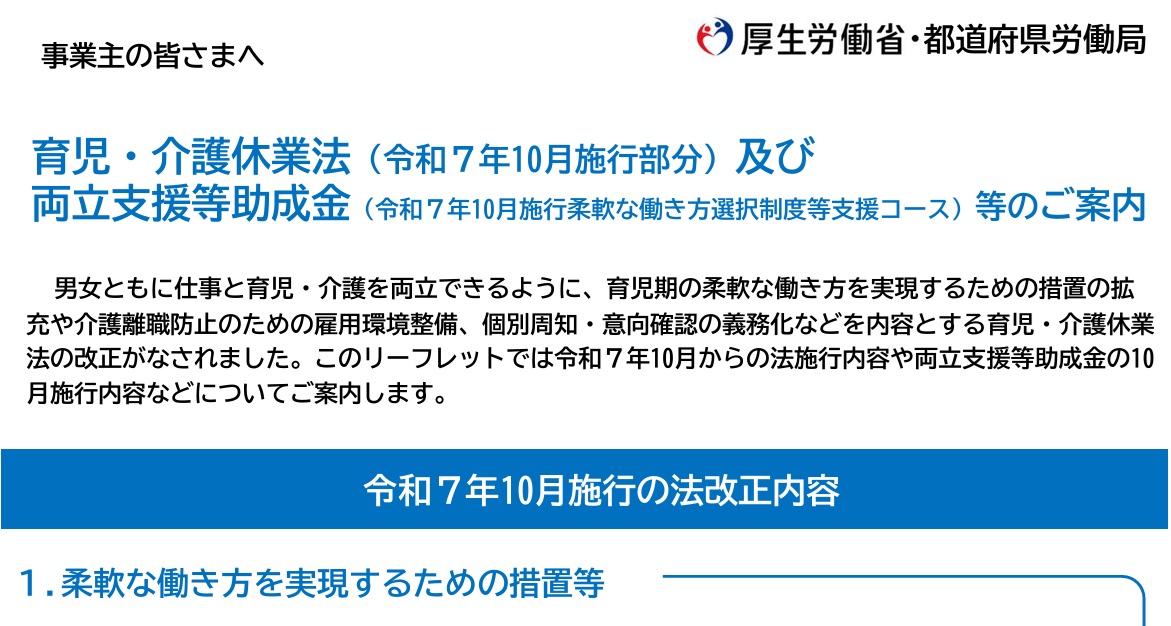
コメント