エグゼクティブ・サマリー
本記事は、「健康経営優良法人認定制度(中小規模法人部門)」に関する最新の動向、統計データ、および成功事例を統合的に分析し、その要点をまとめたものです。公表されている事例集に基づくと、本制度は中小企業における経営戦略の中核として急速に浸透しつつあります。
主要な洞察
1. 制度の急速な拡大と浸透:
中小規模法人部門における申請・認定法人 数は2017年の創設以来、一貫して増加傾向にある。2025年には申請数が2万件を超え、認定法人数は19,796法人に達するなど、健康経営が特別な取り組みから、企業の持続的成長に不可欠な経営基盤として広く認識されつつあることを示している。
2. 経営への多面的な効果:
認定法人は、健康経営の実践を通じて具体的な経営上の利益を報告している。特に、「人材確保・定着」「生産性の向上」「企業ブランド価値の向上」が顕著な効果として挙げられる。採用活動における応募者数の増加や離職率の低下、アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの改善による業績向上、取引先や金融機関からの評価向上など、その効果は多岐にわたる。
3. 成功戦略の共通項:
成功事例には、いくつかの共通する戦略が見られる。経営トップの強いリーダーシップと明確なメッセージ発信、健康診断データやアンケートに基づく課題の「見える化」、従業員との対話を通じた主体的な参加の促進、そして外部の専門家や保険者、他企業との連携が挙げられる。また、「小さな取り組みから始め、継続すること」が成果に繋がる重要なポイントとして多くの企業が強調している。
4. 経営戦略としての位置づけ:
健康経営は、単なる福利厚生の枠を超え、「人的資本経営」を実践するための具体的な経営戦略として位置づけられている。従業員の心身の健康が、組織の活性化、生産性向上、ひいては企業価値向上に直結するという認識が、認定企業の経営層に共通して見られる。
関連情報
解説動画
最初に動画で概要を把握いただくと当記事の内容が分かりやすくなると思います。
1. 認定制度の動向と統計分析
健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認定制度は、年々その規模を拡大しており、参加法人数の増加は健康経営への関心の高まりを明確に示しています。
1.1 申請・認定状況の推移
制度開始以来、申請法人数および認定法人数は一貫して増加しています。特に直近数年間での伸びは著しく、中小企業における健康経営の急速な普及を裏付けています。
| 認定年度 | 申請法人数 | 認定法人数 |
|---|---|---|
| 2017 | 397 | 318 |
| 2018 | 816 | 775 |
| 2019 | 2,899 | 2,501 |
| 2020 | 6,095 | 4,811 |
| 2021 | 9,403 | 7,934 |
| 2022 | 12,849 | 12,255 (※1) |
| 2023 | 14,401 | 14,012 |
| 2024 | 17,316 | 16,733 |
| 2025 | 20,267 | 19,796 |
1.2 都道府県別認定状況
全国的に認定法人数は増加しているが、地域によってその数には差が見られます。特に愛知県、大阪府、東京都、神奈川県などの大都市圏で認定法人数が多い傾向にあります。
| 都道府県 | 2023年認定数 | 2024年認定数 | 2025年認定数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 461 | 614 | 726 |
| 東京都 | 893 | 1,156 | 1,413 |
| 愛知県 | 1,647 | 1,871 | 2,141 |
| 大阪府 | 1,831 | 2,046 | 2,319 |
| 兵庫県 | 650 | 728 | 826 |
| 福岡県 | 348 | 484 | 576 |
| (全国合計) | 14,012 | 16,733 | 19,796 |
1.3 業種別認定状況
建設業、製造業が認定法人数の中で大きな割合を占め、継続的に増加しています。昨年度比上昇率を見ると、複合サービス事業、娯楽業、農業、学習支援業など、多様な業種で関心が高まっていることがわかります。
| 業種分類 | 2023年認定数 | 2024年認定数 | 2025年認定数 | 2025年昨年度比上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 3,130 | 3,848 | 4,620 | 20.1% |
| 製造業 | 3,039 | 3,650 | 4,474 | 22.6% |
| 運輸業 | 1,089 | 1,271 | 1,456 | 14.6% |
| 卸売業 | 1,038 | 1,249 | 1,512 (※3) | 21.1% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 1,065 | 1,209 | 1,391 | 15.1% |
| 小売業 | 602 | 750 | 876 | 16.8% |
| 情報通信業 | 549 | 679 | 798 | 17.5% |
| 保険業 | 620 | 677 | 724 | 6.9% |
| 専門・技術サービス業 | 575 | 700 | 833 | 19.0% |
1.4 法人格別認定状況
認定法人の大多数は会社法上の会社等であるが、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など、多様な法人格の組織が認定を受けています。
| 法人格の分類 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 会社法上の会社等、士業法人、その他 | 11,646 | 13,377 | 16,018 | 19,009 |
| 医療法人、社会福祉法人等 | 199 | 205 | 239 | 259 |
| 社団法人、財団法人、商工会議所等 | 357 | 368 | 411 | 449 |
| 特定非営利活動法人 | 21 | 21 | 26 | 30 |
| 公法人、特殊法人等 | 31 | 36 | 39 | 49 |
| 合計 | 12,254 | 14,007 | 16,733 | 19,796 |
2. 健康経営がもたらす経営上の効果
事例報告によれば、健康経営の実践は抽象的な理念にとどまらず、測定可能な経営上の効果をもたらしています。
2.1 人材の確保と定着
健康経営は、企業の魅力を高め、採用競争において強力な差別化要因となっています。特に若年層やその保護者からの信頼獲得に寄与し、人材の定着率向上にも直結しています。
- 山形陸運株式会社
「高卒新卒者の面接で『健康経営優良法人認定を取得しているから』という回答が多い。運輸業は良くないイメージを持たれがちだが、保護者の方にも安心して選んでいただけている。」 - 株式会社NISHI SATO
「健康経営の取り組みを外部に発信することで、求職を出した際の応募者が2日間で260人に至った。応募者の信頼を得ることができると感じている。」 - 株式会社アイザック・トランスポート
運転手不足が問題となる業界において、離職率は平均して3年に1名程度と非常に低い。 - 株式会社石井工機
2020年から離職者が一人も出ていない。「従業員の悩みを早い段階で相談・解決できることが離職防止につながっている。」
2.2 生産性の向上と業績への貢献
従業員の心身の健康状態の改善は、プレゼンティーイズム(出勤しているが生産性が低下している状態)やアブセンティーイズム(病欠)の低減を通じて、直接的に生産性や業績の向上に貢献します。
- 株式会社セルヴァンスポーツ
「生産性損失額が当初16.7万円/人から6.7万円/人まで下げることができた。健康経営は単なる福利厚生ではなく、経営戦略であることを伝えたい。」 - 株式会社長田工業所
生産性(時間当たりの粗利)を分析した結果、2021年と2022年の比較で14.7%改善した。 - 高木建設株式会社
アンケートの結果、アブセンティーズム0日の従業員が42.1%から80.1%まで改善。「現場が休みなく回るようになり生産性が向上したと実感している。」
2.3 企業ブランド価値の向上
「健康経営優良法人」の認定は、顧客、取引先、金融機関、地域社会からの信頼を高める強力なブランド資産となります。
- 有限会社宮地商店
「ブライト500を名刺に明記することで顧客から好評を得ている。健康経営を実施することで自社商品(生命保険)のPRにもつながっている。」 - 喜多機械産業株式会社
「健康経営の情報交換の場で社長や推進者が他企業と繋がりを作ることができる。会社の接点が増え、新しい顧客との接点になっている。」 - 株式会社アロー
「ブライト500に認定されたことで、健康経営に関する企業からの依頼案件が増えた。企業のブランドイメージが向上したと感じている。」
3. 成功事例に見る主要戦略と具体的取り組み
効果的な健康経営を実践している企業は、組織の状況に応じた多様な戦略と施策を展開しています。
3.1 経営層のコミットメントと推進体制
健康経営の成否は、経営層の強い意志と、それを実行する組織体制にかかっています。
トップダウン型
株式会社シアーズホームグループHDでは、会長が毎朝の朝礼でメッセージを発信し、健康経営を最重要課題として位置づけている。
ボトムアップ型
オーエス株式会社では、人事総務部が育休明けの働き方に関する従業員の不安を起点に制度改革を主導し、経営層の理解を得るために地道な努力を続けた。
従業員巻き込み型
有限会社宮地商店では、2年交代で役職者でない従業員が健康経営のリーダーを務めることで「自分事化」を促進。山八商事株式会社は、従業員アンケートや対話を重視し、従業員の声を次年度の施策に反映させている。
3.2 データ活用と課題の「見える化」
客観的なデータに基づいて課題を特定し、施策の効果を測定することが、戦略的な健康経営の鍵となります。
健康指標の可視化
株式会社セルヴァンスポーツは、体成分や姿勢の測定データをBIツールで分析し、プレゼンティーイズムとの関連を可視化。これにより「姿勢スコアの悪さ」という新たな課題を発見した。
課題の深掘り
山形陸運株式会社は、歩数計データを分析した結果、「休日の歩数が平日の半分」という事実に着目し、「Sunday 3000」という新たな取り組みを創出した。
効果測定と共有
株式会社阿蘇ファームランドは、自社の健康測定設備や保険者データを活用して課題を分析し、その結果をグループ報で社内に発信している。
3.3 コミュニケーションと組織風土の醸成
制度や施策を形骸化させず、組織文化として根付かせるためには、継続的なコミュニケーションが不可欠です。
対話の重視
山形陸運株式会社は、「会社は、従業員の健康に積極的に関与しフォローしたい」という考えを粘り強く説明し、従業員や労働組合の理解を得ている。
参加しやすい環境づくり
株式会社ワイドソフトデザインは、「いつのまにか健康になれる環境」を目指し、健康的なおやつの提供やAlexaによる姿勢改善の促しなど、日常に溶け込む工夫を行っている。
イベントを通じた活性化
株式会社福利厚生倶楽部中部は、健康アプリを活用したチーム対抗イベントを実施。これにより、健康意識の横展開とコミュニケーションの活性化を両立させている。
3.4 具体的施策の多様性
各社は自社の課題や特性に応じて、多岐にわたるユニークな施策を実践しています。
| テーマ | 企業名 | 具体的な取り組み内容 |
|---|---|---|
| 運動機会の創出 | 山形陸運株式会社 | 全額会社負担で歩数計を配布し、歩数アップ率の掲示や表彰制度を実施。 |
| 食生活改善 | 山八商事株式会社 | 毎月8日を「サラダランチデー」とし、希望者にサラダを提供。参加率はほぼ100%。 |
| 女性の健康支援 | 山八商事株式会社 | 全従業員対象の「女性の健康」研修を実施。女性従業員の意見を基に専用休憩エリアを設置。 |
| メンタルヘルス | 株式会社石井工機 | 外部の専門家チーム(作業療法士、キャリアコンサルタント等)による個別ヒアリングと改善指導を実施。 |
| 禁煙対策 | 高木建設株式会社 | 業種・地域が異なる4社で合同の「禁煙プロジェクト」を推進し、喫煙率を36%から26.6%に低下させた。 |
| 低コスト施策 | オーエス株式会社 | 毎月8日を「腹八分目運動の日」とし、イントラネットでの豆知識発信やポスター掲示を実施。金銭的負担なく開始。 |
| ユニークな休暇制度 | 株式会社HYK | 「誕生日が嬉しい、だから健康でいたい」という考えから、パート含む全従業員対象の「バースデー休暇」を導入。 |
4. 健康経営推進のための実践的Tips
資料に含まれるQ&Aや事例から、健康経営を推進するための実践的なアイデアを以下にまとめます。
4.1 関心を高める
- 情報伝達の工夫
毎月必ず見る給与封筒に健康に関するリーフレットを同封し、定期的に健康情報を届ける。 - ゲーミフィケーションの活用
年に一度「からだ測定会」を実施し、結果をランキング形式で公表・表彰することで、楽しみながら健康を意識させる。 - 成功事例の共有
健康的な生活を実践している従業員へのインタビュー記事を社内報などで紹介し、他の従業員のモチベーションを刺激する。
4.2 「自分事化」を促す
- 目標の連動
会社の健康経営計画を発表する際に、従業員一人ひとりが自身の健康目標(例:体脂肪率◯%改善)を設定し、会社の目標とリンクさせる。 - 役割の付与
推進リーダーを従業員の持ち回りにする(有限会社宮地商店)、イベント企画を従業員に任せるなど、主体的に関わる機会を作る。
4.3 参加を促し、コミュニケーションを活性化する
- 参加のハードルを下げる
ウォーキングイベント等の参加者が、取り組んでいる様子を写真付きで社内共有することで、未参加者が内容を理解し、次回の参加意欲を高める。 - ポジティブな関係構築
職場の同僚に感謝を伝える「ちょっといい話」を募集・共有する取り組みで、日々のコミュニケーションのきっかけを作る。
4.4 具体的な課題を解決する
| 課題 | アイデア |
|---|---|
| 喫煙率低下 | 「禁煙ペア制度」を導入。禁煙希望者と非喫煙者がペアを組み、成功者には報奨金を支給する。(Q7) |
| 長時間労働の雰囲気改善 | 「帰ります宣言!カード」を導入。カードを掲示するだけでスムーズに退社できる雰囲気を作り、メリハリのある働き方を定着させる。(Q8) |
| 介護と仕事の両立支援 | 現職介護士への質問会を開催し、将来介護を担う可能性のある従業員にも知識を提供する。(Q10)/オンラインで相談できる心理カウンセラーと契約する。(Q11) |
ガイド:Q&A
1. 「健康経営」とは何か、その目的と期待される効果を説明してください。
健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。従業員の健康保持・増進に取り組むことで、組織の活性化や生産性の向上、最終的には企業価値の向上といった効果が期待されます。
2. 健康経営優良法人認定制度は、どの機関が制度設計を行い、どの組織が認定していますか。また、認定されることによる主なメリットは何ですか。
この制度は経済産業省が制度設計を行い、日本健康会議が認定しています。認定されると、PR等に使用できるロゴマークが付与されるほか、自治体の公共調達での加点や金融機関からの低利子融資といったインセンティブを受けられることがあります。
3. 健康経営優良法人(中小規模法人部門)の中でも特に優れた企業を表彰する制度は何と呼ばれていますか。また、その選定基準はどのようなものですか。
「ブライト500」と呼ばれる制度です。健康経営優良法人(中小規模法人部門)の中から、「健康経営優良法人の中でも優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として、取り組みに関する地域への発信状況や評価項目における適合項目数を基に上位法人が選定されます。
4. 健康経営優良法人(中小規模法人部門)への申請・認定法人数は、制度開始以来どのように推移していますか。その傾向を具体的に述べてください。
申請・認定法人数は、2017年の制度開始以来、一貫して増加傾向にあります。例えば、2017年の認定法人数318社に対し、2025年には19,796社が認定されるなど、企業からの関心が急速に高まっていることが示されています。
5. 山形陸運株式会社が健康経営を始めたきっかけは何でしたか。また、従業員の理解を得るためにどのような点を粘り強く説明しましたか。
関連会社の従業員が業務外に突然死したことがきっかけです。従業員には、「会社が健康経営を推進するのは、従業員を守り、その家族と生活を守ることに繋がり、結果として会社を守ることになる」という点を粘り強く説明し、理解を求めました。
6. 株式会社セルヴァンスポーツは「健康指標の見える化」をどのように実践しましたか。その結果、従業員にどのような気づきをもたらしましたか。
体成分測定や姿勢測定などのデータをBIツールで分析し、プレゼンティーイズム(出勤しているが生産性が低い状態)と紐づけました。これにより、体成分は良くても姿勢のスコアが悪く、肩こりや腰痛のリスクで生産性が低下していることが可視化され、従業員自身の体のケアへの意識を高めるきっかけとなりました。
7. 株式会社HYKの事例から、小規模事業者が健康経営を推進する上での利点は何だと述べられていますか。
小規模事業者だからこそフットワーク軽くトライできることがメリットだと述べられています。大きな費用をかけずにスモールステップで、その時のフェーズに合った持続可能な取り組みを柔軟に実施できる点が強みとされています。
8. オーエス株式会社は、健康経営はどのようなことから始められると示唆していますか。具体的な取り組み例を一つ挙げてください。
取り組みやすい小さなことからコツコツと実践し、継続することが重要だと示唆しています。例として、毎月8日を「腹八分目運動の日」とし、社内イントラネットで食生活に関する豆知識を発信するなど、金銭的負担なく気軽に始められる取り組みを挙げています。
9. ソース資料に示されている、健康経営を実践するための4つのステップを挙げてください。
以下の4つのステップが示されています。STEP 1: 健康宣言を実施する。STEP 2: 実施できる環境を整える(担当者の設置など)。STEP 3: 具体的な対策をする(健康課題の把握と施策実行)。STEP 4: 取り組みを評価し、次に活かす。
10. 株式会社アイザック・トランスポートは、長距離運転手特有の課題に対し、労働時間管理においてどのような目標を設定し、どう実現を図っていますか。
法定の時間外労働(単月80時間以内)より厳しい「時間外労働と休日労働の合計で50時間未満」を目標としています。デジタル式運行記録計で労働時間を詳細に管理し、目標値を超えそうな乗務員には安全管理部から直接指導を行うなど、部署横断的に取り組んでいます。
重要用語集
| 用語 | 説明 |
| AWB(アクティビティベースドワーキング) | 仕事内容に合わせて、働く時間や場所を自由に選択する働き方のこと。オーエス株式会社の事例では、フリーアドレス運用により部署を超えたコミュニケーションの創出に繋がったとされている。 |
| アブセンティーズム | 傷病による欠勤や休職など、健康問題が原因で従業員が職場にいない状態のこと。高木建設株式会社の事例では、健康経営によりアブセンティーズムが改善し、生産性が向上したと報告されている。 |
| 健康経営 | 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。企業の生産性や価値の向上を目指す経営手法。 |
| 健康経営優良法人認定制度 | 優良な健康経営を実践している企業等を顕彰する制度。経済産業省が制度設計し、日本健康会議が認定を行う。認定法人はロゴマークの使用が許可される。 |
| 健康宣言 | 経営者が、従業員やその家族の健康管理を経営課題として認識し、組織として対策に取り組む旨を文書などを通じて意思表示すること。多くの場合、加入する保険者(協会けんぽ等)の宣言事業に参加する形で行われる。 |
| ストレスチェック | 労働者のストレス状態を調べる検査。労働者が50人以上いる事業場では実施が義務付けられている。メンタルヘルス不調の未然防止を目的とする。 |
| 特定保健指導 | 40歳から74歳を対象とした特定健診の結果、メタボリックシンドロームのリスクが高いと判断された者に対して行われる生活習慣改善のための支援。保険者の義務とされている。 |
| 日本健康会議 | 国民の健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織や自治体が連携し、実効的な活動を行うために組織された活動体。健康経営優良法人の認定を行っている。 |
| ネクストブライト1000 | 健康経営優良法人2025(中小規模部門)において新設された認定区分。詳細はソース内に記載されていないが、ブライト500に次ぐ優良法人を顕彰するものと推察される。 |
| プレゼンティーズム | 出勤はしているものの、心身の健康上の問題が原因で、労働生産性が低下している状態。株式会社セルヴァンスポーツの事例では、生産性損失額として数値化され、健康経営による改善効果が示されている。 |
| ブライト500 | 健康経営優良法人(中小規模法人部門)の中から、「健康経営優良法人の中でも優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として優良な上位500法人を表彰する制度。 |
| ヘルスリテラシー | 健康情報を入手し、理解し、評価し、活用するための知識や能力のこと。多くの企業が研修や情報提供を通じて従業員のヘルスリテラシー向上に取り組んでいる。 |
| 保健指導 | 健康診断の結果、健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師等が生活習慣の改善について助言を行うこと。 |
| ワークライフバランス | 仕事と私生活の調和のこと。健康経営の取り組みの一環として、適切な働き方の実現やコミュニケーション促進を通じて推進されることが多い。 |
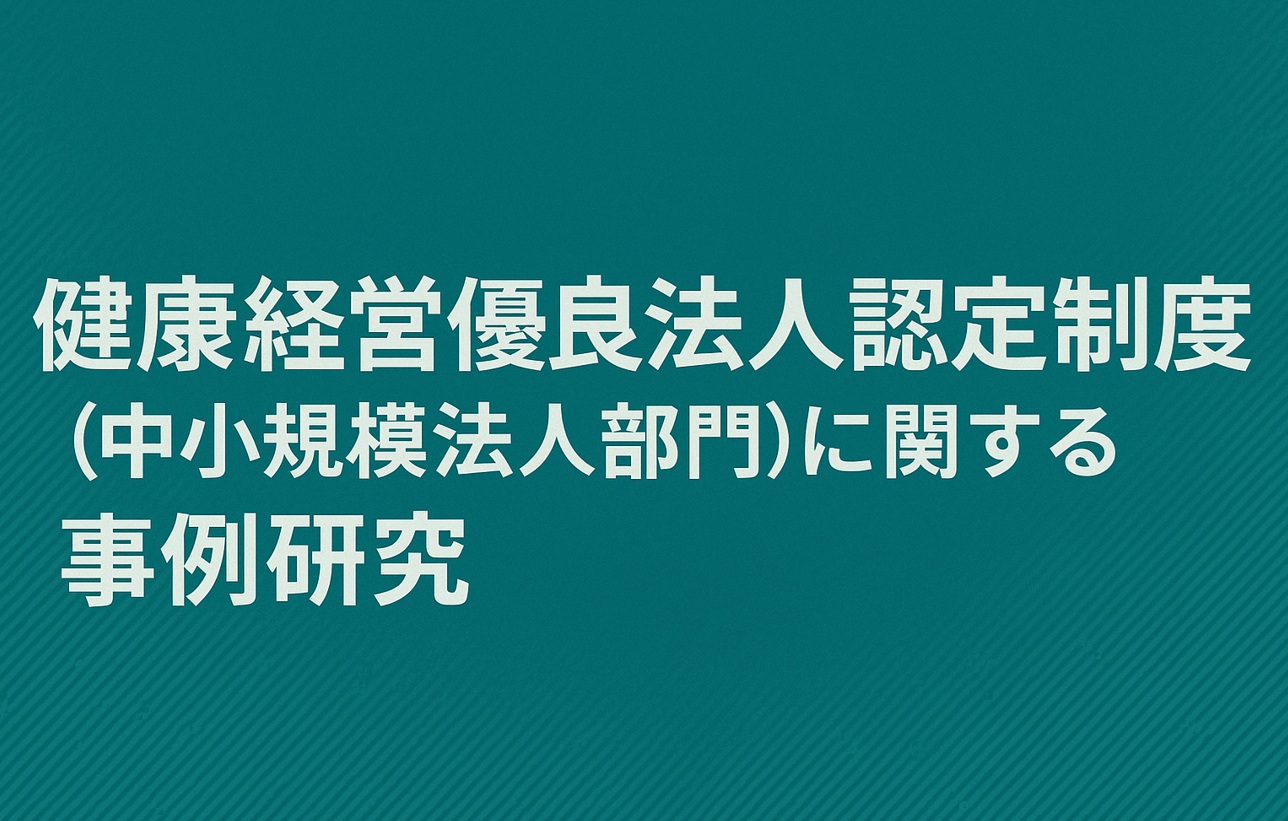

コメント