導入:今なぜ「コーチング」「1on1」が注目されるのか
近年、多くの企業で「コーチング」や「1on1ミーティング」が人材育成のキーワードとして注目を集めています。背景には、働き方や人材マネジメントの大きな変化があります。リモートワークの普及や若手社員の価値観の多様化により、上司と部下が定期的に対話する機会の重要性が増しています。
実際、1on1はシリコンバレー発の文化として広まり、日本でもYahoo!(ヤフー)など大手企業が導入して成果を上げたことで一気に広がりました。上司が部下の成長のために時間を使うという発想が注目され、現在では日本企業の7割以上が何らかの形で1on1を導入しているとのデータもあります。
一方、コーチングも再び脚光を浴びています。2000年代に一度ブームとなったコーチングは、当時「対話を通じて相手の自律性やモチベーションを高める手法」として経営者や管理職研修に取り入れられました。その後、働き手の価値観変化やパンデミックによる働き方の変革を経て、「部下の成長を支援しエンゲージメントを高める」新しいマネジメントのあり方として再注目されています。今の社員は「会社で自己成長できる実感」を求めており、上司がコーチのように対話で寄り添い成長を支援する環境が離職防止や組織力向上につながるからです。
つまり今、「対話による人材育成」が重要視される時代です。
コーチングと1on1はその代表的な手法であり、単なる流行ではなく、成果を最大化するコミュニケーション戦略として定着しつつあります。
動画解説
記事をお読みいただく前に動画で簡単に概要把握をしていただくと理解が深まります。
コーチングと1on1の違いと共通点
コーチングと1on1はいずれも「対話」を通じて相手の成長を促す点で共通していますが、その目的や運用には違いがあります。それぞれの特徴を理解し、上手に使い分けることが効果的な人材育成につながります。
コーチングと1on1の主な違い
- 目的とゴール設定
コーチングは明確な目標達成や課題解決を目的に行われ、毎回明確なゴールを設定して対話を進めます。
一方、1on1は必ずしも毎回ゴールを定めなくてもよく、日々の悩み相談やキャリア支援など幅広いテーマで行われます。
例えばコーチングでは「半年後に○○スキルを習得する」など具体的ゴールを置きますが、1on1では雑談も交えつつ「最近の困り事は?」「今後やってみたいことは?」といったオープンな対話になりやすいです。 - 関係性と役割
コーチングは専門のコーチとクライアント(部下や社員)が対等なパートナー関係で進めるケースが多く、答えを教えるのではなく相手の中から引き出すコミュニケーションです。
一方で1on1は基本的に上司と部下の関係内で行われ、上司が主導・ファシリテーション役を担います。上司部下の上下関係はありますが、1on1においては上司もコーチング的な姿勢で臨み、なるべく対等な対話になるよう努めることが重要です。 - 扱う内容
コーチングでは仕事上の目標だけでなく本人のキャリアや思考整理など内面的な成長にフォーカスします。
1on1は業務の進捗確認や目標のフォロー、フィードバックなど実務的な話題も扱います。例えばコーチングセッションなら「将来どんなリーダーになりたいか?」といった深いテーマを掘り下げますが、1on1では「今抱えている業務課題は?」「プロジェクトの進捗はどう?」といった日常業務の話もしながら、その中で成長支援の対話を行います。
以上のように、コーチングは専門的・体系的な対話プロセスであり、1on1はマネジメント手法として定期的に対話する場という違いがあります。
ただし両者は対立するものではなく、むしろ補完関係にあります。上司が1on1の場面でコーチングの手法・スキルを取り入れることで、部下の主体性をより引き出すことができるでしょう。
共通点と本質
- 対話による気づきの創出
コーチングも1on1も、一方的な指示命令ではなく双方向の対話を通じて相手に新たな気づきを与えることを重視します。上司が一方的に話す場ではなく、部下が自由に考えを語れる場を作る点で共通しています。 - 相手の成長支援
どちらも最終目的は相手の成長を促すことです。コーチングではクライアントの自己成長や目標達成を支援し、1on1では部下の成長促進や能力開発、モチベーション向上を狙います。相手の主体性を引き出し、学びの機会を提供する点は共通の本質と言えます。 - 信頼関係の重要性
コーチング・1on1いずれの場合も、安心して本音を話せる信頼関係を築くことが成功のカギです。上司(コーチ)が傾聴と思いやりの姿勢を示し、心理的安全性が確保されて初めて、有意義な対話が可能になります。日頃からの関係構築の積み重ねや、対話の場での傾聴姿勢が両者に共通して求められます。
このように、コーチングと1on1は「対話を通じて人を伸ばす」という共通の土台があります。それぞれの違いを理解しつつ、共通点である対話の極意を活かすことで、より効果的な人材育成が実現できます。
コーチング技術の基本(傾聴・質問・フィードバック)
コーチングを成功させるためには、「傾聴」「質問」「フィードバック」という3つの基本スキルが不可欠だとよく言われます。これらは上司が1on1を行う際にも非常に役立つコミュニケーション技術です。ここでは各スキルのポイントを解説します。
傾聴:安心して本音を話せる環境を作る
コーチングにおける傾聴とは、単に黙って相手の話を聞くことではありません。「安心して本音を話せる場を作る」という広い意味で捉えることが重要です。
具体的には、相手の話に耳と心を傾け、相槌やうなずき、オウム返しで共感と関心を示すこと。そして決して途中で否定・批判をせず、相手の感じていることを受け止めてあげることです。否定的な反応をされると、人は心を閉ざしてしまいます。まずは「あなたの話を尊重しています」という姿勢を示し、話しやすい雰囲気を醸成しましょう。
傾聴には相手を承認する(良いところを認める)働きも含まれます。たとえば「それは大変でしたね」「なるほど、よく考えてますね」といった言葉で相手の努力や感情に理解を示すと、相手は安心感を得てより深い話をしてくれるようになります。
なお、傾聴を支える土台として信頼関係が不可欠です。いくらテクニックを駆使しても、日頃から信頼されていなければ相手は本音を語りません。上司が部下との約束を守る、日常的に気にかける、といった地道な信頼醸成も傾聴の一部と言えるでしょう。
質問:相手の思考を引き出し視野を広げる
コーチングの質問スキルは、こちらが知りたいことを尋ねるのではなく、相手の思考整理や問題解決のヒントを引き出すことが目的です。人は悩んでいたりプレッシャー下にあると視野が狭くなりがちですが、コーチからの適切な問いかけによって新たな視点に気づくことがあります。
例えば、「今の課題を解決するために、他にどんな方法が考えられる?」と問いかければ、それまで見えていなかった選択肢に気づくかもしれません。
良い質問のポイントは、オープンクエスチョン(Yes/Noで答えられない質問)を用いることと、相手を追い詰めるのではなく寄り添う姿勢であることです。「なぜできていないのか?」と詰問調で尋ねると防衛的になりますが、「何がボトルネックになっていると感じますか?」など理由を自由に説明できる聞き方をすれば、対話が深まります。
また、「それはあなたにとってどんな意味がありますか?」「理想的にはどうなればいいと思いますか?」といった質問は、相手自身の価値観やビジョンを言語化させ、内省を促すのに効果的です。
質問によって相手の考えを引き出すことで、課題の本質がクリアになったり、新たな解決策を自分で思いついたりするきっかけが生まれます。上司がすぐ答えを教えるのではなく、部下が「自分で考える」プロセスを支援するという意識で質問を投げかけることが大切です。
フィードバック:評価ではなく客観的な鏡返し
コーチングにおけるフィードバックは、一般的な人事考課で使う「評価フィードバック」とは少し異なります。評価を伴うフィードバックではなく、コーチが感じたこと・気づいた事実をそのまま相手に伝えるイメージです。
例えば、「最近の会議であまり発言していないように見えたけど、何か気になっているのかな?」と感じたことを率直に伝えるのがコーチング型フィードバックです。ここで「発言が少なくてダメだ」など評価・批判を交えてしまうと、相手は身構えてしまいます。
フィードバックは鏡に映すイメージと言われます。自分では気づいていない癖や強み・弱みを、相手の言葉や態度をそのまま返すことで気づきを促します。「今○○と仰いましたが、かなり声のトーンが明るくなりましたね。何か良いことがあったんですか?」といった具合に、相手の変化や感情に気づいたらそれをフィードバックすることで、相手は改めて自分の内面に目を向けるきっかけを得ます。
重要なのは、決して頭ごなしの評価や主観的な批評をしないことです。良い点は素直に称賛し、改善点は「こうするともっと良くなると思う」と前向きな提案にとどめます。フィードバックによって「なるほど、そう見えていたのか」と相手に新たな視点を与えることで、自己認識が深まり成長につながります。
以上の傾聴・質問・フィードバックは相互に関連しています。まず傾聴で安心感を作り、適切な質問で相手の考えを引き出し、それをフィードバックで照らしてあげる。このサイクルが効果的な対話を生み、相手の成長を後押しします。1on1に臨む上司も、ぜひコーチングのこの3つの基本技術を意識してみてください。
1on1の運用ポイントと頻度・構成例
1on1ミーティングを効果的に機能させるには、適切な頻度で継続することと、対話の流れ・進め方に工夫が必要です。
ここでは1on1の基本的な運用ポイントと、現場で活用できるミーティング構成の一例を紹介します。
実施頻度と時間の目安
1on1は定期的に継続して実施することで初めて効果を発揮します。理想的には週1回~月1回の頻度で、1回あたり30分程度の対話時間を確保するのが望ましいとされています。新入社員や若手には週1回、ベテラン社員には月1回など、メンバーの経験値やニーズに応じて頻度を柔軟に調整している会社もあります。大切なのは組織として「○曜日の午後は1on1タイム」等と予定に組み込み、上司も部下もよほどの事情がない限りキャンセル・後回しにしない文化を作ることです。継続的な対話の場があることで、信頼関係の構築や早期の課題発見といったメリットが最大化します。
時間は30分を基本に、内容によっては1時間取るケースもあります。短すぎると雑談で終わって深い話ができず、長すぎるとお互い負担になるため、30~45分程度が現実的でしょう。リモート環境の場合はオンラインでの実施も交えて、遠隔でも対話機会を確保する工夫が必要です。
1on1ミーティングの進め方(構成例)
1on1の典型的な流れの一例を以下に示します。
- 事前準備
上司は部下の最近の業務状況や成果、悩みとして挙がっていることを把握し、話したいテーマを事前に共有します。例えば「今週は○○プロジェクトの進捗について、感じている課題を話そう」といった具合です。部下側にも事前に「話したいこと・議題」を考えてもらうと、より有意義な対話になります。準備段階で部下の人となりや最近の様子を上司がリサーチしておくことも有効ですが、先入観を持ちすぎないよう注意しましょう。 - 導入(アイスブレイク)
ミーティングが始まったら、いきなり本題に入らず雑談からスタートします。週末の過ごし方やちょっとした趣味の話、最近のニュースなど他愛のない話題で数分間会話し、部下の緊張をほぐします。いきなり仕事の話をすると部下は身構えてしまうため、「最近どう?」といった軽い問いかけから始めるのがコツです。上司が先に少しプライベートな話題(自分の趣味や週末の出来事など)を自己開示するのも、場を和ませるのに効果的です。 - テーマに沿った対話(本題)
アイスブレイクの後、事前に決めたメインテーマについて話し合います。部下に自由に話してもらうことを優先し、上司はコーチングの姿勢で傾聴と質問を意識します。部下が自己分析できるような質問を投げかけたり、感じたことをフィードバックしながら、部下の考え・本音を引き出す対話に努めましょう。例えば「今一番悩んでいることは何?」「どう解決できそうだと考える?」と問いかけ、部下の言葉に耳を傾けます。必要に応じて上司自身の経験を共有したりアドバイスをすることもありますが、答えを押し付けないよう注意します。あくまで部下が主体的に考え、上司はサポート役に徹するのが理想です。 - まとめ・次へのアクション
対話の終盤には、話した内容を簡単に振り返り、必要なフォローアップ事項を確認します。「今回は○○についてこういう話が出たけど、じゃあ次回までに何かやってみたいことある?」などと問い、部下自身に小さな目標やアクションを設定させると良いでしょう。上司からも「では私も△△をサポートするね」と支援策を伝えます。最後に次回の1on1の予定をその場で決めてカレンダーに入れておくと、継続がスムーズです。記録は機密性に配慮しつつ残し、部下の許可を得て人事システムに要点をメモする企業もあります(ツールを使えばログ管理も容易です)。対話内容の秘密は守りつつ、必要に応じて上司間で傾向を共有し組織施策に活かすケースもあります。
以上が基本的な流れですが、企業文化や上司・部下の関係性によってアレンジして構いません。
ポイントは、部下が主役で話す時間を多くすること(目安は部下8割・上司2割とも言われます)、そして継続することです。形式ばかりに捉われず、対話を通じて部下の成長につながるなら雑談中心の日があっても良いのです。
重要なのは、1on1を通じて上司と部下が信頼を深め、本音で語れる関係を築くことにあります。
抽象度の高い成功事例:対話がもたらす効果
業種を問わず、コーチングや1on1による対話を取り入れた企業では様々な成功事例が報告されています。ここでは抽象度高く共通する効果に焦点を当て、代表的な成功パターンを紹介します。
- 自律型人材の育成・社員の成長促進
継続的な対話により社員が自ら考え行動するようになった例があります。
例えば大手IT企業のヤフーでは、1on1ミーティングの実践によって社員の経験学習を促進し、「社員が自分の才能を自分で発見する」効果があったと報告しています。上司との対話を通じて、自分の強みややりたいことに気づく社員が増え、情熱を持って成長に取り組む自律型人材の育成につながったといいます。
このように、対話の場が社員の自己理解を深め、主体性を引き出す成功例は多くの企業で見られます。 - 離職率の低下・人材定着への寄与
定期的な1on1導入後に離職率が大幅に改善したケースも報告されています。
あるITベンチャー企業(株式会社テモナ)では、1on1ミーティングを導入し上司と若手社員の対話を徹底した結果、1年で離職率が20%から0%に低下したとのことです。また別の企業では、2年間にわたり社員の退職者ゼロ(離職率0%)を達成した例もあります。定期的な1on1によって組織の雰囲気が改善し、上司部下間の信頼が深まった結果、社員が働き続けたいと思える職場になったとされています。
このように、対話を重ねることで不安や不満を早期に汲み取り対処でき、結果的に人材の定着率向上につながるのです。 - 現場課題の可視化・組織力強化
1on1は現場の生の声を吸い上げ、課題を表面化させる効果もあります。
たとえば先述の離職率ゼロを実現した企業では、1on1で業務以外の悩みも早期発見しサポートできるようになりました。また中途入社社員から「前職では~だった」という改善提案が1on1で上がり、経営陣が即対処するといった組織改善サイクルも生まれています。定期的な対話の場があることで、普段は埋もれがちな現場の課題やアイデアが可視化され、組織全体の問題解決力が高まった好例と言えるでしょう。
これらは製造業でもサービス業でも共通して見られ、「対話が組織を強くする」ことを示すエピソードです。
以上のように、コーチングや1on1を通じた対話は人と組織にもたらす効果が大きいことがわかります。
自律的に成長する人材が増え、エンゲージメントが向上し、離職率が下がり、さらには現場の知見が組織学習につながる——これらはどの業界でも目指すべき成果でしょう。成功事例に共通するのは、やはり継続した対話と信頼関係の醸成である点に留意してください。
導入時の注意点と現場への浸透法
コーチングや1on1を組織に取り入れる際には、いくつか注意すべきポイントがあります。単に手法を真似るだけでは形骸化する恐れがあるため、以下の点に配慮しつつ現場に浸透させましょう。
- トップの理解と目的の明確化
経営層や人事部が「なぜ1on1やコーチングを導入するのか」を明確にし、現場に発信することが重要です。これがないと現場管理職は「また面倒な施策が増えた」と受け取りかねません。
トップダウンでのメッセージとして、「1on1は評価のためでなく部下の成長を支援するための取り組み」という方針を示し、必要なリソース(時間確保など)を提供しましょう。トップ自らコーチングを受けたり、幹部が率先して部下との対話に時間を割く姿勢を見せることも、全社的な浸透につながります。 - 形骸化の防止:評価・説教の場にしない
せっかく導入しても、1on1が単なる業務報告や説教の場になってしまっては部下の信頼を得られません。上司が一方的に指示・評価をする場にしないよう注意が必要です。心理的安全性を確保するため、1on1の場では「評価しない・叱責しない」ことを原則にしましょう。人事考課フィードバックなどは別途機会を設け、1on1では基本的に対話と傾聴に徹する運用ルールにすると安心です。
また、周囲に内容が筒抜けにならないようプライバシーに配慮した環境(個室やオンラインの個別接続など)を用意することも大切です。部下が「この場でなら本音を話せる」と感じられて初めて有益なコミュニケーションが生まれます。 - 管理職へのトレーニングと過度な期待の抑制
1on1をうまく機能させるには、実施する管理職のスキル向上が不可欠です。しかし同時に「全てのマネージャーが完璧なコーチにならねば」とプレッシャーをかけすぎないことも重要です。現実には「1on1を導入したが形式的になってしまう」「部下が本音を話してくれない」「上司のスキル不足で効果が出ない」といった悩みが多くの企業で生じています。
原因の一つは、経営・人事サイドおよびマネージャー自身がコーチングに過剰な期待を持ちすぎていることだと指摘されています。効果を急ぎすぎて「部下を劇的に変えねば」と焦ると、現場のマネージャーにストレスがかかり逆効果です。
そこで、管理職には基本的な傾聴・質問のスキル研修やロールプレイを提供し、徐々に慣れてもらう期間を設けましょう。また「最初から完璧にできなくてもOK」「まずは部下と定期的に話すことが大事」とハードルを下げ、マネージャー同士が悩みを共有できる場を作ることも有効です。小さな成功体験(「最近部下が色々話してくれるようになった」等)を共有しあい、良いプラクティスを社内ナレッジとして蓄積・展開すると現場に根付きやすくなります。 - 継続とフォローアップの仕組み
最初だけ盛り上がっても継続しなければ意味がありません。定期実施を徹底するため、1on1の実施状況を人事がモニタリングしたり、上司同士で振り返りミーティングを行うのも効果的です。
たとえば「1on1実施率」を部門評価に組み込んだり、1on1で出た課題を吸い上げ経営会議で議論する、といった仕掛けもあります。最近では1on1支援のITツールもあり、スケジュール管理や議事録テンプレート、対話を深める質問リストの提案機能などで現場を支えることができます。こうしたツールや仕組みを活用しつつ、「対話が文化として定着する」まで粘り強くフォローしていきましょう。
以上の点を踏まえれば、コーチングや1on1は単なる研修や制度で終わらず、現場に浸透していくはずです。
大切なのは、経営から現場まで一貫して「人材育成は対話から」というメッセージを共有することです。そうすればコーチング・1on1の技術は組織風土に根付き、長期的な成果へとつながっていくでしょう。
まとめ:成果につながる対話の設計
最後に、本記事のポイントを振り返ります。
コーチングと1on1は、対話によって人の可能性を引き出し成長を促す強力な手法です。それぞれ形は違えど共通するのは「上司と部下が向き合い、傾聴・質問・フィードバックを通じて信頼関係を築き、学びと気づきを創出する」という本質でした。これらの対話を上手に設計・運用すれば、社員の成長が加速し、それがひいては組織全体の成果最大化につながります。
今なぜ対話型の人材育成が求められるのかを考えると、急速な環境変化の中で自ら考え判断できる人材がますます重要になっているからです。指示待ちでなく主体的に動ける人材を育成するには、日々の1on1で経験を振り返らせ学習を促すことが効果的だと多くの企業が気づき始めています。コーチング的なコミュニケーションは、そうした自律人材を育む土壌となります。
人事・教育担当者の皆様には、ぜひ自社の文化に合った形でコーチングと1on1を取り入れてみていただきたいと思います。最初は手探りでも構いません。重要なのは「部下としっかり向き合って話を聞く」というシンプルな姿勢です。それを継続し対話を洗練させていけば、必ずや現場に良い変化が現れるでしょう。成果につながる対話をデザインし、社員の可能性を最大限に引き出せる組織を目指していきましょう。あなたの関わり方ひとつで、未来のリーダーが育ち、組織が大きく飛躍するかもしれません。ぜひ今日から実践に活かしてみてください。
以上、「成果を最大化する人材育成コーチング・1on1の技術とコミュニケーションの極意」と題して、コーチングと1on1の基本から実践ポイントまで解説しました。対話を制する者が人材育成を制します。明日からの現場での対話が、組織の明るい未来を切り開くことを願っています。
音声動画
最後に音声動画で今回の内容を振り返りたいと思います。
ガイド:Q&A
1. 近年、多くの企業で「コーチング」や「1on1ミーティング」が注目されている背景には、どのような社会的な変化がありますか?
リモートワークの普及や若手社員の価値観の多様化により、上司と部下が定期的に対話する機会の重要性が増したことが背景にあります。社員が「会社で自己成長できる実感」を求めるようになったことも、部下の成長を対話で支援するマネジメントが再注目される要因です。
2. コーチングと1on1の目的とゴール設定における主な違いは何ですか?
コーチングは明確な目標達成や課題解決を目的に毎回ゴールを設定しますが、1on1は必ずしも毎回ゴールを定めず、日々の悩み相談やキャリア支援など幅広いテーマを扱います。コーチングが特定のゴールを目指す体系的な対話であるのに対し、1on1はより柔軟なマネジメントの場と位置づけられます。
3. コーチングにおける「傾聴」とは、単に話を聞くこととどう違いますか?
コーチングにおける傾聴は、単に話を聞くのではなく、「安心して本音を話せる場を作る」という広い意味を持ちます。相槌や共感を示し、相手の話を途中で否定・批判せず受け止めることで、相手との信頼関係を築き、より深い対話を引き出すための技術です。
4. コーチングで効果的な「質問」をする目的と、そのためのポイントを説明してください。
目的は、相手の思考整理や問題解決のヒントを引き出し、新たな視点に気づかせることです。ポイントは、「はい/いいえ」で答えられないオープンクエスチョンを用い、相手を詰問するのではなく、自由に説明できるような寄り添う姿勢で問いかけることです。
5. コーチングにおける「フィードバック」は、一般的な人事考課のフィードバックとどのように異なりますか?
一般的なフィードバックが評価を伴うのに対し、コーチングのフィードバックは評価を伴わず、コーチが感じたことや気づいた事実を「鏡返し」のようにそのまま相手に伝えます。これにより、相手は自分では気づいていない癖や強み・弱みを客観的に認識し、自己理解を深めることができます。
6. 1on1ミーティングを効果的に運用するための理想的な頻度と時間の目安はどれくらいですか?
理想的な頻度は週1回から月1回で、1回あたりの時間は30分程度が望ましいとされています。メンバーの経験値に応じて頻度を調整し、継続的に実施することが信頼関係の構築や早期の課題発見につながります。
7. 1on1ミーティングを始める際の「導入(アイスブレイク)」は、なぜ重要だとされていますか?
いきなり本題に入ると部下が身構えてしまうため、雑談から始めることで緊張をほぐし、本音を話しやすい雰囲気を作るために重要です。上司が先に自己開示をすることも、場を和ませるのに効果的とされています。
8. 1on1の導入がもたらした成功事例として、具体的にどのような効果が報告されていますか?(2つ挙げてください)
一つは、ヤフー株式会社の事例で、社員が自らの才能を発見し、主体的に成長に取り組む「自律型人材」の育成につながったことです。もう一つは、株式会社テモナの事例で、離職率が1年で20%から0%に大幅に低下するなど、人材定着に大きく寄与したことが挙げられます。
9. 1on1が「単なる業務報告や説教の場」になるのを防ぐ(形骸化させない)ためには、どのような原則を守るべきですか?
1on1の場では「評価しない・叱責しない」ことを原則とすることが重要です。また、プライバシーに配慮した環境を用意し、部下が「この場でなら本音を話せる」と感じられる心理的安全性を確保する必要があります。
10. 1on1を導入する際、実施者である管理職に対して、組織はどのような支援をすることが有効ですか?
管理職に過度な期待をせず、基本的な傾聴や質問のスキル研修、ロールプレイを提供することが有効です。また、マネージャー同士が悩みを共有できる場を設けたり、スケジュール管理や質問リストを提案するITツールを活用したりして、現場の負担を軽減しつつ継続を支援することが求められます。
重要用語集
| 用語 | 定義 |
| コーチング (Coaching) | 対話を通じて相手の自律性やモチベーションを高める手法。明確な目標達成や課題解決を目的に行われ、答えを教えるのではなく、相手の中から答えを引き出すコミュニケーションを重視する。 |
| 1on1ミーティング (1-on-1 Meeting) | 上司と部下が定期的に行う1対1の対話。部下の成長支援を目的とし、業務の進捗確認、悩み相談、キャリア支援など幅広いテーマを扱うマネジメント手法。 |
| 傾聴 (Active Listening) | 単に話を聞くのではなく、「安心して本音を話せる場を作る」ためのコミュニケーション技術。相手の話に耳と心を傾け、共感や関心を示し、否定せずに受け止める姿勢を指す。 |
| 質問 (Questioning) | 相手の思考整理や内省を促し、新たな視点や解決策を自ら引き出すための問いかけ。相手を追い詰めるのではなく、寄り添う姿勢でオープンクエスチョンを用いることが重要とされる。 |
| フィードバック (Feedback) | コーチングにおいては、評価や批判を伴わず、観察した事実や感じたことをそのまま相手に伝える「鏡返し」のような手法。相手の自己認識を深め、成長を促すことを目的とする。 |
| オープンクエスチョン (Open-ended Question) | 「はい/いいえ」では答えられない質問形式のこと。相手に自由に説明する余地を与えることで、対話を深め、思考を引き出す効果がある。 |
| 心理的安全性 (Psychological Safety) | 組織内で、自分の考えや感情を安心して気兼ねなく発言できる状態のこと。1on1においては、本音の対話を実現するための重要な基盤となる。 |
| 自律型人材 (Autonomous Personnel) | 指示待ちではなく、自ら考え、主体的に判断し行動できる人材。コーチングや1on1は、社員の自己理解を深め、このような人材を育成する効果があるとされる。 |
| エンゲージメント (Engagement) | 社員が組織に対して抱く愛着心や貢献意欲のこと。コーチングや1on1による対話は、社員のエンゲージメントを高め、離職防止につながると考えられている。 |
| 経験学習 (Experiential Learning) | 自身の経験を振り返り、そこから学びや教訓を引き出して次の行動に活かす学習プロセス。1on1は、上司との対話を通じて部下の経験学習を促進する場となる。 |

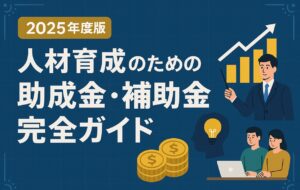




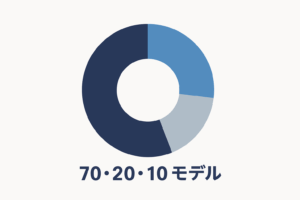
コメント