1. はじめに:なぜ今、「サステナビリティ情報」がこれほど重要なのか?
気候変動、人権問題、従業員のウェルビーイングといった「サステナビリティ」や「人的資本」に関する情報は、もはや企業の社会的責任(CSR)活動の報告書に留まるものではありません。これらは企業の長期的な成長性やリスク耐性を測る上で不可欠な要素として、投資家が投資判断を行う際の重要な情報インフラとなっています。
優れた取り組みは企業価値向上に直結し、逆に見過ごされたリスクは経営の根幹を揺るしかねません。だからこそ、これらの非財務情報を正確かつ分かりやすく開示することは、現代企業にとって極めて重要な経営課題なのです。
この情報の質と透明性を担保するため、金融庁は毎年、上場企業が提出する「有価証券報告書」の内容を審査する「レビュー」を実施しています。これは、企業の開示が定められたルールに準拠しているかを確認し、より良い開示に向けた改善を促すための重要な仕組みです。
本稿では、金融庁が公表した最新の「令和6年度 有価証券報告書レビュー」の結果、特に「サステナビリティ情報」と「人的資本」の開示に焦点を当てます。多くの企業が陥りがちな共通の課題を「7つの落とし穴」として整理し、専門家でなくても理解できるよう、その原因と対策を分かりやすく解説していきます。
関連情報
解説動画(金融庁レビューの全般について)
2. すべての始まり:2023年に導入された情報開示の「新ルール」とは
今回の金融庁レビューは、2023年1月に施行された新しい開示ルール(改正開示府令)に本格的に基づく、初の本格的な審査となりました。この新ルールは、サステナビリティや人的資本に関する情報開示を大きく拡充・義務化したものであり、その内容を正しく理解することが、多くの企業が陥った失敗を避けるための第一歩となります。
2.1. サステナビリティ情報開示の4つの柱
改正開示府令は、国際的な潮流を踏まえ、サステナビリティ情報を以下の4つの構成要素で整理し、開示することを求めています。
ガバナンス
サステナビリティ関連のリスクや機会を、取締役会などがどのように監督・管理しているかという体制やプロセスを開示します。
戦略
企業が特定したサステナビリティ関連のリスクや機会が、自社の事業や経営戦略にどのような影響を与えるか、そしてそれにどう対処していくのかを開示します。
リスク管理
サステナビリティ関連のリスクや機会を、全社的にどのように特定・評価・管理しているかの具体的なプロセスを開示します。
指標及び目標
戦略の進捗やリスク管理の実効性を評価・管理するために用いる具体的な指標と、それに基づく目標・実績値を開示します。
ポイント
「ガバナンス」と「リスク管理」は全企業に開示が義務付けられていますが、「戦略」と「指標及び目標」は、各企業が自社にとっての「重要性(マテリアリティ)」を判断した上で開示することとされています。この重要性の原則は、企業が自社のビジネスモデルや長期的価値に真に影響を与えるサステナビリティ課題に集中し、形式的な「チェックリスト対応」に陥るのを防ぐ上で極めて重要です。
2.2. 特に注目される「人的資本」と「多様性」に関する開示項目
新しい枠組みの中でも、投資家の関心が特に高いのが「人的資本」と「多様性」に関する情報です。具体的には、以下の項目についての方針や指標の開示が求められています。
- 人材育成方針
- 社内環境整備方針
さらに、これらの方針と関連付けて、具体的な指標や目標、実績を開示する必要があります。また、個別の多様性指標として、以下の3項目は「従業員の状況」の欄で記載が必須となりました。
- 女性管理職比率
- 男性の育児休業等取得率
- 男女間賃金格差
これらの新しい要請に対し、多くの企業がどのように応え、そしてどのような課題に直面したのか。金融庁の審査結果は、その実態を浮き彫りにしています。
3. レビューで判明!サステナビリティ情報開示によくある7つの「落とし穴」
金融庁のレビューによって、業種や規模を問わず、多くの企業で共通する課題が繰り返し指摘されていることが明らかになりました。これらは単なる記載ミスではなく、サステナビリティへの取り組み姿勢そのものが問われる根深い問題を含んでいます。
ここでは、それらの典型的な失敗事例を7つの「落とし穴」として分類し、改善への道筋を探ります。
落とし穴①:具体的プロセスの欠如。「やっています」だけの形骸化したガバナンス・リスク管理
金融庁が指摘した最も基本的な課題の一つが、ガバナンスとリスク管理に関する記述の具体性の欠如です。
多くの企業が、「サステナビリティ推進担当部を設置し、取り組みを推進しています」といった体制の「建付け」や抽象的な考え方を説明するに留まっています。しかし、投資家が本当に知りたいのは、「取締役会は、サステナビリティ課題をどのように監督しているのか」「リスクを特定し、評価し、管理するための具体的なプロセスや方法論は何か」といった、実効性を担保するための具体的な仕組みです。
この「プロセス」の記述が欠けていると、経営層がサステナビリティ課題に本気で向き合っているのか、その体制が実質的に機能しているのかが伝わらず、開示そのものが形骸化しているとの印象を与えかねません。
落とし穴②:ストーリーの欠如。「リスク、戦略、目標」がバラバラで繋がらない
サステナビリティ情報開示で最も本質的かつ重要なのは、各要素が論理的に一貫した「物語(ストーリー)」を成していることです。しかし、多くの開示ではこの繋がりが欠落していました。
• 典型的な失敗パターン1:リスクは挙げているが、対応が不明瞭
気候変動のリスクとして「炭素税の導入」や「自然災害の増加」を列挙しているが、それらに対して具体的にどのような戦略で対応し、何を目標としているのかが書かれていない。
• 典型的な失敗パターン2:戦略や目標はあるが、背景が不明瞭
例えば、ある不動産会社の報告書で「入居率100%を目指します」という目標が掲げられていましたが、それがどのようなサステナビリティ関連のリスクや機会に対応するための戦略なのかが全く説明されていない。
このように、特定した「リスク・機会」、それに対処する「戦略」、進捗を測る「指標・目標」が三位一体となっていない開示は、単なる情報の断片に過ぎません。この「物語の断絶」は、多くの場合、社内における思考の分断を反映しています。
サステナビリティ担当、リスク管理担当、事業部門が連携せず、戦略がサイロ化していることの表れなのです。これでは、投資家が企業のサステナビリティ戦略の全体像を理解することは著しく困難になります。
落とし穴③:機会の見落とし。リスク管理は「リスク」だけではない
開示府令が求める「リスク管理」の項目は、その名の通りリスクへの言及が中心となりがちです。しかし、金融庁は「機会」を特定・評価・管理するプロセスについても同様に開示が求められると明確にしています。ところが、多くの企業でこの「機会」に関するプロセスの記述が抜け落ちていました。
サステナビリティへの取り組みは、コストや制約といった側面だけでなく、新しい事業機会の創出や競争優位性の源泉にもなり得ます。
例えば、環境規制の強化は「リスク」ですが、同時に省エネ技術や新素材開発といった「機会」を生み出します。投資家は、企業が未来の価値創造に繋がる「機会」をどのように見出し、戦略に組み込んでいるかを知りたがっています。リスクへの対応プロセスだけを語り、機会創出のプロセスを語らない開示は、守りの姿勢しか見せず、企業の成長ポテンシャルを十分に伝えきれていません。
落とし穴④:重要情報の欠落。「統合報告書には書いた」は通用しない
多くの企業が、統合報告書や自社のサステナビリティサイトなど、任意開示の媒体では豊富な情報を発信しています。しかし、その内容が法定開示書類である有価証券報告書に反映されていないケースが散見されました。
例えば、統合報告書では「気候変動」を最重要課題と位置づけ、詳細な戦略や目標を開示しているにもかかわらず、有価証券報告書ではそれらの情報が記載されず、「詳細は当社ウェブサイトをご覧ください」と参照するだけの事例が見られます。
金融庁のスタンスは明確です。有価証券報告書に「本質的かつ重要な情報」を記載した上で、「補完的な詳細情報」について他媒体を参照することは許容されます。しかし、本来記載すべき重要な情報を丸ごと省略し、外部参照に委ねることはできません。法定開示と任意開示では読者層や目的が異なりうるとしても、投資判断に不可欠な情報が有価証券報告書から抜け落ちていては本末転倒です。
落とし穴⑤:「方針」と「実績」の乖離。データで裏付けられない人的資本戦略
人的資本に関する開示では、掲げた「方針」と、それを裏付ける「指標・目標・実績」が全く対応していないという、特有の課題が指摘されました。
• 金融庁が示した事例:
- 方針(戦略): 「DX人材の育成」および「多様性の確保」
- 指標・目標: 「エンゲージメントスコアの向上に取り組んでおり、当期末はBランクです」
この例では、企業が重要方針として掲げた「DX人材育成」や「多様性確保」の進捗が、提示された「エンゲージメントスコア」という指標から全く評価できません。
これでは、方針が単なる「お題目」に終わっているのではないかとの疑念を抱かせてしまいます。
投資家が知りたいのは、掲げた方針が具体的な成果(アウトカム)に結びついているかを示す客観的なデータです。方針と指標の間に明確な繋がりがなければ、その戦略の実効性を判断することは不可能です。
落とし穴⑥:「連結ベース」の原則無視。グループ全体の実態が見えない
人的資本に関する指標は、原則として連結グループ全体で開示することが求められます。しかし、提出会社(親会社)単体の数値しか記載していない企業が多数見られました。
グローバルに事業を展開し、グループ経営が主流となっている現代において、親会社単体のデータだけでは人的資本の実態を大きく見誤る可能性があります。主要な事業を担う重要な子会社が複数存在するにもかかわらず、そのデータを開示しなければ、投資家はグループ全体の人的資本の状況を把握できません。
金融庁は、連結ベースでの開示が困難な場合の対応も示しています。その場合、企業は以下の4点を明記すべきです。
- 連結ベースでの開示が困難である旨
- なぜ困難なのかという理由
- 実際に開示している範囲(例:提出会社と主要子会社A)
- なぜその範囲を選んだのかという理由
単に提出会社単体の数値を記載するだけでは、説明責任を果たしたことにはなりません。
落とし穴⑦:定義の誤解。「女性管理職比率」の不正確な計算
人的資本・多様性開示の中でも、特に技術的な誤りが多かったのが「女性管理職比率」の算出方法です。レビューでは、多くの企業が女性活躍推進法で定められた「管理職」の定義を正しく理解せず、比率を計算していることが判明しました。
法律上、管理職は原則として「課長級」以上の役職者と定義されています。しかし、多くの企業が「課長代理」や「課長補佐」といった、法律上の管理職には含まれない役職者まで分母・分子に含めて比率を計算していました。
一見些細な誤りに見えるかもしれませんが、有価証券報告書は法律に基づく法定開示書類です。そこに記載される数値は、法律で定められた厳密な定義に従って算出されることが絶対条件となります。自社の独自基準で算出した数値をそのまま開示することは認められません。
4. コンプライアンス遵守から、企業価値向上のための「対話のツール」へ
金融庁のレビューから浮かび上がった数々の課題は、単なる「開示の作法」の問題ではありません。これらは、企業が自社のサステナビリティへの取り組みをいかに深く理解し、それをステークホルダーに論理的に説明できるかという、経営の本質的な能力を映し出す鏡と言えます。
情報開示の最終目的は、単に法令を遵守する(コンプライアンス)ことではありません。自社の非財務的な取り組みが、いかに長期的な企業価値向上に結びつくのか。そのストーリーを投資家や社会に分かりやすく説明し、建設的な「対話」を生み出すための戦略的ツールとして活用することこそが、本来の目的なのです。
4.1. 企業担当者が明日から実践すべき3つのポイント
今回の指摘事項を踏まえ、企業の開示担当者がすぐに実践すべきアクションプランを3つにまとめました。
一貫したストーリーを構築する
自社のサステナビリティ開示全体を見渡し、「ガバナンス」から「リスク・機会の特定」、「戦略」、「指標・目標」までが、一本の論理的な線で繋がっているかを確認しましょう。特定の目標がどのリスク・機会に対応し、どの戦略の一部なのかを明確に説明できるかが鍵です。
「プロセス」を具体的に語る
「取締役会で審議しています」といった抽象的な表現を避け、取締役会が「どのように」監督し、リスクや機会を「どのように」評価・管理しているのか、その具体的な過程(プロセス)を記述しましょう。誰が、いつ、何を使って、どう判断しているのかが分かるレベルを目指すべきです。
定義と範囲の正確性を期す
「女性管理職比率」における「管理職」の定義や、人的資本データの「連結」報告範囲など、技術的な要件を改めて確認しましょう。法令やガイドラインの定義を正確に理解し、それに準拠した情報開示を徹底することが、信頼性の基盤となります。
4.2. これからの情報開示の向かう先
今、サステナビリティ情報の開示基準は、世界的に統一化・厳格化される大きな潮流の中にあります。ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が公表した国際基準をベースに、日本国内でもSSBJ(サステナビリティ基準委員会)が日本の開示基準の策定を進めており、今後、有価証券報告書で求められる開示はさらに拡充される見込みです。
今回の金融庁レビューで指摘された課題は、日本企業がこの大きな潮流に対応していくための「基礎体力」を養う絶好の機会と捉えるべきです。開示を単なる義務や「コスト」と捉えるのではなく、自社の企業価値を語るための「投資」へと転換させること。その意識改革こそが、これからの時代を勝ち抜くための重要な第一歩となるでしょう。
5.「サステナビリティに関する企業の取組の開示」における主な課題
| 主な課題 | 課題となる事項の概要 | |
|---|---|---|
| 1 | サステナビリティ関連のガバナンスに関する記載がない又は不明瞭 | ガバナンスの基本的な考え方や執行体制(サステナビリティ推進部等)の記載に留まり、取締役会等による監督を含めたリスク・機会の監視・管理の「過程、統制及び手続」が記載されていない。 |
| 2 | サステナビリティ関連のリスクを識別、評価及び管理するための過程に関する記載が不明瞭 | 個別のリスクや対策は記載されているが、それらを体系的に「識別、評価、管理するプロセス」についての説明が欠落している。 |
| 3 | サステナビリティ関連の機会を識別、評価及び管理するための過程に関する記載がない | リスク管理に関する記載はあるものの、機会(オポチュニティ)を識別・評価・管理するための過程についての記載が全くない。 |
| 4 | 識別したリスク及び機会に対応する戦略並びに指標及び目標に関する記載がない又は不明瞭 | 複数のリスク・機会を列挙しているにもかかわらず、それぞれに対応する具体的な戦略や指標・目標が網羅的に記載されていない。 |
| 5 | リスク及び機会の記載がないため、戦略並びに指標及び目標に関する記載が不明瞭 | 戦略や目標(例:入居率の向上)は記載されているが、それがどのようなサステナビリティ関連のリスクや機会に対応するものなのかが不明確。 |
| 6 | 戦略並びに指標及び目標のうち重要なものについて記載がない | 統合報告書等では気候変動を「重要課題(マテリアリティ)」と位置づけ戦略等を開示しているにもかかわらず、有価証券報告書には記載がない。 |
| 7 | 人的資本に関する方針、指標、目標及び実績のいずれかの記載がない又は不明瞭 | 方針として「DX人材の育成」「多様性の確保」を掲げているが、指標が「エンゲージメントスコア」のみであるなど、方針と指標等の対応関係が不明瞭。 |
| 8 | 人的資本に関する指標、目標及び実績が連結会社ベースの記載になっていない | 連結ベースでの開示が原則であるにもかかわらず、提出会社単体の数値のみを記載し、重要な連結子会社を含めていない。また、その理由も記載されていない。 |
| 9 | 有価証券報告書内の他箇所への参照における記載不備 | 「ガバナンスはCG報告書の箇所を参照」と記載しても、参照先にサステナビリティ関連のガバナンス体制についての記載がない。 |
| 10 | 他の開示書類等への参照における記載不備 | 「TCFD提言に沿った情報はウェブサイト参照」と記載し、有価証券報告書本体には具体的な戦略や目標を記載していない。有価証券報告書に記載すべき基本情報が欠落している。 |
6.「従業員の状況及びコーポレート・ガバナンスの状況等」の開示における主な課題
| 主な課題 | 課題となる事項の概要 | |
|---|---|---|
| 1 | 女性管理職比率を女性活躍推進法の「管理職」の定義に従って算定・開示していない | 厚生労働省の解釈では「管理職」と見なされない「課長代理」を管理職に含めて比率を算出している。 |
| 2 | 取締役会、指名・報酬委員会、監査役会等の活動状況の記載がない | 開催方針は記載されているが、当事業年度における開催頻度、具体的な検討内容、個々の役員の出席状況といった「実績」が記載されていない。 |
| 3 | 内部監査が取締役会に直接報告を行う仕組みの有無に関する記載がない | 監査役会への報告体制は記載されているが、取締役会への直接報告を行う仕組みの「有無」について記載が漏れている。(仕組みがない場合はその旨を記載する必要がある) |
| 4 | 政策保有株式の銘柄ごとの保有目的が具体的に記載されていない | 保有目的が「営業上の取引関係の維持・強化」と記載されているが、どのような取引かの概要が記載されていない。 |
| 5 | 政策保有株式の銘柄ごとの保有目的が安定株主の確保にあるにもかかわらず、当該目的が記載されていない | 実際の保有目的が株式の持ち合いによる安定株主確保であるにもかかわらず、その旨が記載されていない。 |
| 6 | 取締役会等における政策保有株式の保有の適否に関する検証についての開示と実態に乖離がある | 「保有効果を毎年検証し、取締役会に報告している」と記載しているが、実際には報告が行われていない。 |
| 7 | 銘柄ごとの定量的な保有効果の記載が困難な場合において、保有の合理性を検証した方法の記載が不明瞭 | 定量効果の記載が困難である旨は記載されているが、代替として記載すべき「保有の合理性を検証した方法」が具体的でなく、内容を読み取ることができない。 |
| 8 | 売却可能時期等について発行者と合意をしていない状態で純投資目的の株式に変更している | 政策保有株式縮減の方針を示しながら、実質的に売却の目処が立っていない株式を純投資目的に区分変更しており、実態として政策保有を継続していることと差異がない。 |
| 9 | 発行者から売却の合意を得た上で純投資目的の株式に区分変更したが、長期間売却に取り組む予定がない | 売却合意を得て区分変更したものの、実際には長期間売却する予定がなく、実質的に政策保有を継続していることと差異がない。 |
7. ガイド:Q&A
問1. 金融庁が実施する「有価証券報告書レビュー」の主な目的と、その中心となる2つの審査区分は何ですか?
有価証券報告書レビューは、提出された報告書の記載内容の適正性確保と充実化の促進を目的としています。その審査は、改正法令等への準拠性を確認する「法令改正関係審査」と、特定のテーマ(例:サステナビリティ開示)について対話形式で深掘りする「重点テーマ審査」の2つを柱として実施されます。
問2. 令和5年1月に施行された改正開示府令により、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載項目が新設されました。この中で、全ての企業に開示が義務付けられている要素と、企業の重要性判断に委ねられている要素をそれぞれ挙げてください。
全ての企業に開示が義務付けられているのは、サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視・管理する体制を示す「ガバナンス」と、それらを識別・評価・管理するプロセスを示す「リスク管理」です。一方、「戦略」および「指標及び目標」については、各企業が自社の状況に照らして重要性を判断した上で開示することが求められます。
問3. 人的資本に関する開示において、企業は具体的にどのような情報を記載することが求められていますか?
企業はまず、「人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針」および「社内環境整備に関する方針」を記載する必要があります。その上で、これらの方針に関連する指標の内容、ならびに当該指標を用いた目標および実績を具体的に開示することが求められています。
問4. 改正開示府令に基づき、「従業員の状況」の項目で開示が求められるようになった、多様性に関する3つの具体的な指標は何ですか?
女性活躍推進法または育児・介護休業法に基づき情報を公表する企業に対して、「女性管理職比率」「男性の育児休業等取得率」「男女間賃金格差」の3つの指標を開示することが求められています。
問5. サステナビリティ関連の「リスク管理」の開示に関して、レビューで識別された主な課題を2点挙げてください。
主な課題として、サステナビリティ関連のリスクを識別、評価、管理するための「過程」に関する記載が不明瞭である点が挙げられます。また、リスクだけでなくサステナビリティ関連の「機会」を識別、評価、管理するための過程に関する記載がない、という点も課題として識別されています。
問6. 「コーポレート・ガバナンスの状況等」の開示において、取締役会や監査役会などの活動状況として、具体的にどのような実績情報の記載が求められていますか?
取締役会、監査役会、および任意に設置された委員会などについて、当事業年度における実績として「開催頻度」「具体的な検討内容」「個々の取締役や監査役等の出席状況」を記載することが求められています。方針の記載だけでは不十分であり、具体的な実績を示す必要があります。
問7. いわゆる「政策保有株式」について、銘柄ごとの保有目的を開示する際に、特に留意すべき点は何ですか?
銘柄ごとに保有目的を具体的に記載することが求められます。特に、保有目的が発行会社との営業上の取引、業務上の提携、その他これらに類する事項である場合には、単に「取引関係の維持・強化」と記載するだけでなく、当該事項の概要まで具体的に含めて記載する必要があります。
問8. 改正内部統制府令では、訂正内部統制報告書において、評価結果を「有効」から「有効でない」へと訂正する場合、「訂正の理由」に特定の事項を記載するよう求めています。その中で最も重要な「元の報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由」とは、具体的に何について記載することですか?
元の報告書における経営者の「評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」が適切であったかどうか、また、訂正報告書で開示する重要な不備が、元の評価の範囲に含まれていたかどうかを記載することが求められます。これにより、なぜ当初の評価で見逃されたのかを明らかにします。
問9. 企業が「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載事項について、自社のウェブサイトや統合報告書などの他の公表書類を参照する場合、どのようなルールに従う必要がありますか?
開示府令で定められた事項の記載は、まず有価証券報告書本体で行うことが原則です。他の公表書類を参照できるのは、有価証券報告書に記載した事項を「補完する詳細な情報」に限られており、本体に記載すべき基本情報を丸ごと外部参照にすることは認められていません。
問10. レビューの審査過程で識別された、政策保有株式の縮減を妨げる「売らせない圧力」とは、どのような事例ですか?
政策保有株式の発行会社が、保有会社に対して株式の売却意向が示された際に、既存の取引を縮減することを示唆するなどして、売却等を妨げようとする圧力をかける事例です。これは発行会社の安定株主確保を主な理由として行われ、政策保有株式の縮減を妨げる要因となっています。
8. 用語集
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 有価証券報告書レビュー | 金融庁が上場会社等から提出された有価証券報告書の記載内容の適正性確保及び充実化の促進の観点から実施する審査。主に「法令改正関係審査」と「重点テーマ審査」を柱とする。 |
| 法令改正関係審査 | 全ての有価証券報告書提出会社を対象に、改正された府令等(改正開示府令、改正内部統制府令など)の規定への準拠性(開示の漏れや誤りの有無)を審査するもの。 |
| 重点テーマ審査 | 審査対象会社を選定し、特定のテーマ(例:「サステナビリティに関する企業の取組の開示」)について、形式的な記載だけでなく、開示の趣旨に照らして十分な情報が開示されているかを対話形式で審査するもの。 |
| 改正開示府令 | 令和5年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」。主にサステナビリティに関する企業の取組やコーポレート・ガバナンスに関する開示の拡充を定めている。 |
| 改正内部統制府令 | 令和6年4月に施行された「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」。訂正内部統制報告書における記載事項の充実化を定めている。 |
| サステナビリティに関する考え方及び取組 | 改正開示府令により有価証券報告書に新設された記載欄。「ガバナンス」「リスク管理」「戦略」「指標及び目標」の4つの構成要素から成る。 |
| 人的資本 | 企業の持続的な価値創造の源泉となる従業員の能力や経験、多様性など。開示府令では、「人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針」および「社内環境整備に関する方針」と、それらに関する指標・目標・実績の開示が求められる。 |
| 政策保有株式 | 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のこと。取引関係の維持・強化や安定株主の確保などを目的として保有される株式を指す。 |
| 訂正内部統制報告書 | 提出済みの内部統制報告書の内容を訂正するために提出される報告書。財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正する場合などに提出される。 |
| 開示すべき重要な不備 | 財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備。これが存在する場合、内部統制は有効でないと評価される。 |
| ISSB(国際サステナビリティ基準審議会) | 資本市場向けのサステナビリティ関連財務情報の開示に関するグローバルな基準を設定する組織。 |
| SSBJ(サステナビリティ基準委員会) | ISSBが公表した開示基準をベースに、日本国内のサステナビリティに関する開示基準を開発する組織。 |
| コーポレートガバナンス・コード | 上場企業が遵守すべき企業統治に関する原則・指針。東京証券取引所が定めており、政策保有株式の縮減に関する方針なども含まれる。 |
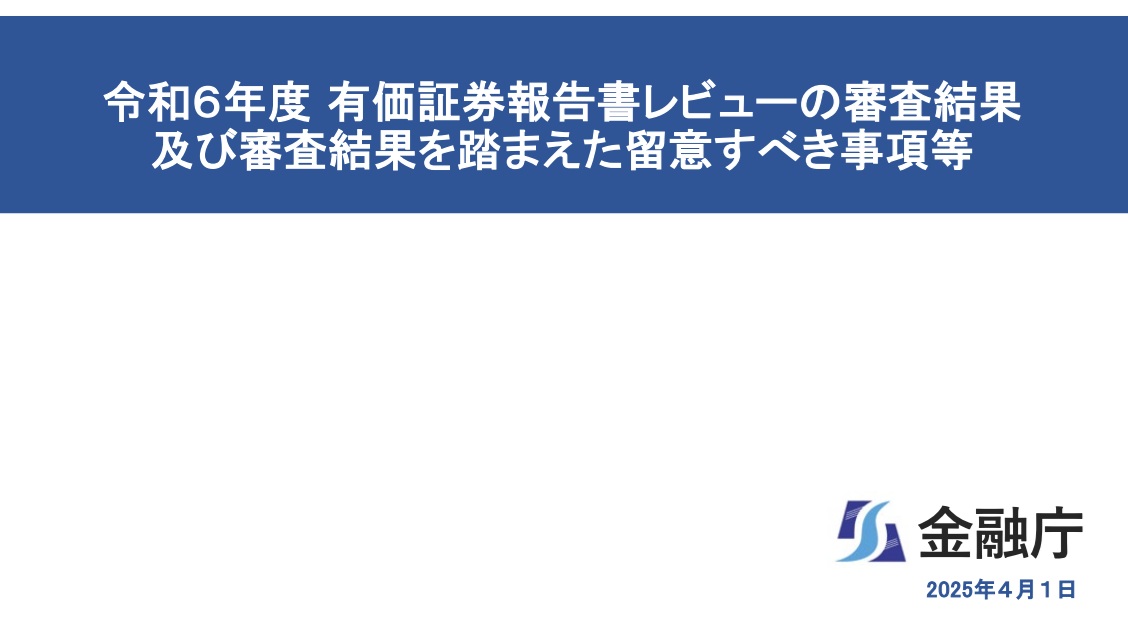

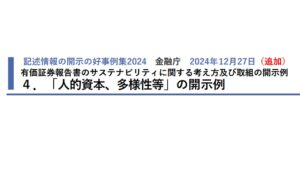
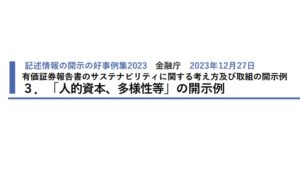
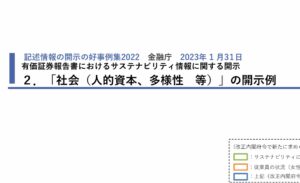
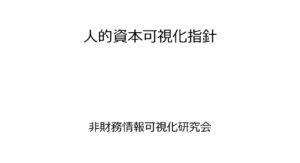
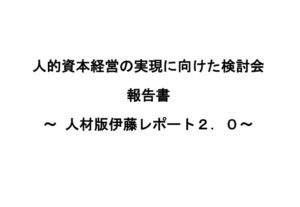
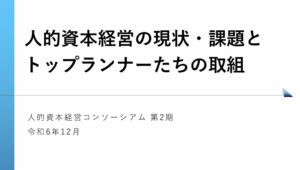
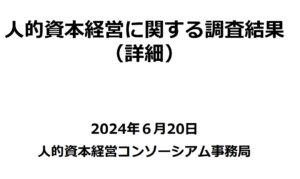
コメント