要旨
本記事は、日本企業における人的資本経営への移行を促す主要な議論、フレームワーク、および現状の課題を統合的に解説するものです。企業の競争優位性の源泉が有形資産から無形資産へと移行する現代において、その中核をなす「人的資本」の最大化は、持続的な企業価値向上のための最重要経営課題として位置づけられています。
経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート」(2020年)および「人材版伊藤レポート2.0」(2022年)は、この変革の羅針盤となっています。これらの報告書は、従来の「管理」対象としての人的資源(Human Resource)から、価値創造のための「投資」対象としての人的資本(Human Capital)へのパラダイムシフトを提唱しています。
その中核的フレームワークとして「3P・5Fモデル」が提示された。
これは、人材戦略が持つべき3つの視点(Perspectives)と、戦略に含めるべき5つの共通要素(Factors)を体系化したものである。
3つの視点
①経営戦略と人材戦略の連動
②As is-To beギャップの定量把握
③企業文化への定着
5つの共通要素
①動的な人材ポートフォリオ
②知・経験のダイバーシティ&インクルージョン
③リスキル・学び直し
④従業員エンゲージメント
⑤時間や場所にとらわれない働き方
しかし、「人的資本経営に関する調査」(2022年)の結果は、多くの企業がこれらの概念の重要性を認識しつつも、具体的な実践には至っていないという「実行の壁」を浮き彫りにしました。特に、「動的な人材ポートフォリオ」の構築、人的資本投資の対効果(ROI)の把握、投資家との対話、および取締役会による監督機能の発揮といった領域での進捗の遅れが顕著です。
結論として、日本企業にとって人的資本経営への移行は、単なる人事制度改革ではなく、経営戦略、コーポレートガバナンス、そして企業文化を巻き込んだ全社的な変革です。経営陣、取締役会、投資家がそれぞれの役割を果たし、企業と個人が互いに選び選ばれる関係を構築することが、今後の持続的成長の鍵を握る。
関連資料
- 人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書(人材版伊藤レポート2.0)(PDF形式:1,213KB)
- 実践事例集(PDF形式:7,240KB)
- 人的資本経営に関する調査 集計結果(PDF形式:1,887KB)
動画解説(約7分)
I. 人的資本経営へのパラダイムシフト
A. 価値創造の源泉の変化
企業価値を決定づける要因は、歴史的に大きく変化してきました。かつては工場や設備といった有形資産が価値の源泉でしたが、今日ではブランド、技術、そして人材といった無形資産がその中心となっています。「伊藤レポート2.0」で示されたデータによれば、米国S&P500構成企業の市場価値に占める無形資産の割合は年々増加しており、有形資産を大きく上回っています。
この変化を背景に、人材に対する捉え方も根本的に見直す必要があります。
- 人的資源(Human Resource)
従来の見方。人材を「管理」し「消費」するコストとして捉える。 - 人的資本(Human Capital)
新しい見方。人材を教育や経験を通じて価値が高まる「資本」と捉え、価値創造に向けた「投資」の対象とする。
この「人的資源」から「人的資本」への転換こそが、現代の経営における最も重要なパラダイムシフトです。
B. 「人材版伊藤レポート」の登場と影響
このパラダイムシフトを日本企業に浸透させるべく、経済産業省は2020年9月に「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書(通称:人材版伊藤レポート)」を公表しました。同レポートは、デジタルトランスフォーメーション(DX)、ESG投資の拡大、新型コロナウイルス感染症による働き方の変革といった環境変化を踏まえ、人的資本の重要性をコーポレートガバナンスの文脈で論じています。その影響は大きく、「人材版伊藤レポート2.0」では「“破壊力”といってもいいくらいのインパクト」と評されています。
2022年5月には、実践への移行をさらに促すため「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書(人材版伊藤レポート2.0)」が公表された。これは初版のコンセプトを深掘りし、企業が具体的なアクションを起こすためのアイディアや先進企業の事例を豊富に盛り込んだ、より実践的なガイドブックとなっています。
II. 中核フレームワーク:「3P・5Fモデル」の詳解
「人材版伊藤レポート」は、企業が経営戦略と連動した実効性の高い人材戦略を構築するための共通言語として「3P・5Fモデル」を提唱しました。
A. 3つの視点 (The 3 Perspectives – 3P)
人材戦略を策定・実行する上で俯瞰的に確認すべき3つの視点。
1. 経営戦略と人材戦略の連動
人材戦略が単独で存在するのではなく、自社のビジネスモデルや経営戦略を達成するための手段として、完全に同期しているかという視点。人材戦略自体が経営戦略の可能性を広げる双方向の関係性も重要視される。
2. As is-To beギャップの定量把握
目指すべきビジネスモデルや経営戦略(To be)と、現状の人材やスキル(As is)との間に存在するギャップを、感覚ではなくデータに基づいて定量的に把握する視点。このギャップをいかに埋めるかが人材戦略の骨子となる。
3. 企業文化への定着
人材戦略は制度の導入だけでなく、実行プロセスを通じて組織や個人の行動変容を促し、最終的に企業の競争優位につながる文化として定着しているかという視点。企業文化は人材戦略のアウトカムと位置づけられる。
B. 5つの共通要素 (The 5 Common Factors – 5F)
多くの企業の人材戦略に共通して見られる具体的な構成要素。
1. 動的な人材ポートフォリオ
経営戦略の実現に必要な人材を質・量の両面から定義し、現状とのギャップを埋めるために、採用、配置、育成、外部人材の活用などを通じて、人材構成を動的に最適化すること。
2. 知・経験のダイバーシティ&インクルージョン
性別や国籍といった属性の多様性にとどまらず、キャリアパス、専門性、価値観など、多様な「知と経験」を組織内に取り込み、それらが化学反応を起こしてイノベーションにつながる環境を構築すること。
3. リスキル・学び直し
事業環境の急速な変化に対応するため、社員が既存のスキルをアップデートし、新たなスキルを習得する機会を企業が戦略的に提供すること。個人の自律的なキャリア形成を支援する側面も持つ。
4. 従業員エンゲージメント
社員が企業の目指す姿に共感し、自発的に貢献しようとする意欲を持つ状態。企業のパーパスと個人の働きがいを結びつけ、組織全体の活力を高めることが目的。
5. 時間や場所にとらわれない働き方
新型コロナウイルス感染症への対応で加速したリモートワークなどを活用し、多様な人材が能力を最大限発揮できる柔軟な労働環境を整備すること。事業継続計画(BCP)の観点からも重要性が高い。
III. 主要ステークホルダーの役割とアクション
人的資本経営の実現には、特定の部署だけでなく、経営陣、取締役会、投資家といった主要ステークホルダーが連携し、それぞれの役割を果たすことが不可欠です。
A. 経営陣
経営陣は人的資本経営の最も重要な推進役であり、以下の役割が期待されます。
| 役割分類 | 主なアクション |
| 理念・戦略の明確化 | 企業理念や存在意義(パーパス)を明確化し、それに基づいた経営戦略の目標を具体的に示す。 |
| 人材戦略の策定・実行 | 経営戦略からバックキャストし、重要な人材アジェンダを特定。KPIを設定し、ギャップを埋める戦略を策定・実行する。 |
| 推進体制の構築 | CEOの戦略パートナーとしてCHRO(最高人事責任者)を設置・選任し、CEO、CSO、CHRO、CFO、CDOからなる経営トップ5Cが密接に連携する。 |
| 積極的な発信・対話 | 人材戦略の内容や進捗を、従業員および投資家に対して積極的に発信し、対話を通じて得たフィードバックを戦略に反映させる。 |
事例
KDDIは、事業部門で豊富な経験を持つ人材を人事部門トップに登用し、経営層や事業部門との密な対話を通じて、経営戦略と人事戦略の連動を強化している。
B. 取締役会
取締役会は、経営陣の人的資本に関する取り組みを監督・モニタリングするガバナンスの要です。
- 戦略の監督
経営戦略と人材戦略が整合しているか、企業価値向上につながるかという観点から、経営陣が策定した人材戦略を承認し、KPIを用いて実行状況を監督する。 - サクセッションプランの監督
CEO等の後継者計画(CxOサクセッション)だけでなく、将来の幹部候補となる人材パイプラインが適切に構築・運用されているかを監督する。 - 企業文化のモニタリング
人材戦略の実行プロセスで醸成される企業文化が、経営戦略の実現に適しているかを議論・モニタリングする。
事例
日立製作所の取締役会では、エンゲージメントサーベイの結果やデジタル人材の育成状況、サクセッションプランについて活発な議論が行われている。
C. 投資家
中長期的な企業価値向上を促す資本市場の担い手として、投資家も重要な役割を担います。
- 建設的対話
ESG要因、特にS(社会)の重要性を認識し、企業の持続的成長の観点から、人材戦略について経営陣と建設的な対話を行う。 - 情報開示の促進
企業に対し、経営戦略と連動した人材戦略に関する情報(考え方、KPI、進捗)の「見える化」と開示を促す。 - 投資判断への活用
開示された情報や対話の内容を、企業の将来性やリスクを評価する材料として投資判断に活用する。
事例
ニッセイアセットマネジメントは、企業との対話の視点として人材戦略を明記し、スチュワードシップ活動の中で積極的に関与している。
IV. 実践における現状と課題:調査データからの洞察
「人材版伊藤レポート」が提唱する人的資本経営は、日本企業にどの程度浸透しているのでしょうか。「人的資本経営に関する調査」(2022年)は、その現状と課題をデータで示しています。
A. 全体的な進捗状況
調査結果は、多くの企業で「重要性の認識」と「実行」の間に大きなギャップがあることを示しています。「企業理念・経営戦略の明確化」といった抽象度の高い項目では進捗が見られるものの、それを具体的な人材戦略に落とし込む段階で足踏み状態となっています。
また、経営陣と従業員の間には認識の差が存在し、役職が下がるほど「取組が進んでいない」と感じる割合が高くなる傾向が見られました。これは、経営トップの方針が現場まで十分に浸透していない可能性を示唆しています。
B. 特に遅れている領域
調査で特に進捗が遅れていると経営陣が認識している領域は以下の通りです。
- 動的な人材ポートフォリオ
全項目の中で最も進捗が遅れていると認識されている。経営陣・従業員双方で進捗度が最も低く、「将来必要となる人材像を定義し、現状とのギャップを埋める」という中核的な活動に着手できていない企業が多い。自由回答では「何から手をつければよいかわからない」「緻密な目標設定に至っていない」といった声が挙がっている。 - 投資対効果の把握
人的資本への投資を「コスト」ではなく「投資」と捉える上で不可欠なROIの把握について、「対応策が未検討」と回答した企業が最も多く、具体的な測定方法の確立が大きな課題となっている。 - 投資家との対話
人材戦略に関する情報を投資家と積極的に対話している企業はまだ少数派であり、一部の企業では「重要性を認識していない」との回答も見られた。 - 取締役会の役割
「取締役会の役割の明確化」や、CEO以外の「経営人材育成の監督」といった項目で進捗が遅れており、取締役会がガバナンス機能を十分に発揮できていない状況が窺える。
C. 先進企業の取り組み事例
一方で、課題を乗り越え、人的資本経営を実践している先進企業も存在します。「実践事例集」からは、以下のような特徴が見て取れました。
ソニーグループ
グループ全体のパーパスを求心力としつつ、多様な事業体の特性に応じて各社CHROに人事運営の権限を委譲。エンゲージメントスコアを経営陣の報酬に連動させている。
SOMPOホールディングス
社員の自律性を促すため、会社主導の異動を廃止しジョブ型人事制度へ移行。「MYパーパス」と会社のパーパスを重ね合わせることを重視し、1on1を通じて浸透を図っている。
サイバーエージェント
全社員のコンディションを毎月定量的に把握し、専任者がケア。社内異動を活発化させることで、個人の成長と事業ニーズのマッチングを図る。
旭化成
経営戦略に基づき毎年必要な人材の質と量を洗い出し、採用・育成に加え、M&AやCVC投資も活用して人材ポートフォリオを構築している。
V. 結論と今後の展望
人的資本経営は、もはや一部の先進企業だけの取り組みではなく、すべての企業が持続的成長のために向き合うべき経営そのものです。「人材版伊藤レポート」シリーズは、そのための明確なビジョンとフレームワークを提供しました。
しかし、調査データが示す通り、多くの企業にとってその実践は道半ばです。特に「動的な人材ポートフォリオ」の構築は、現状分析、将来予測、戦略策定、実行という一連のサイクルを回す必要があり、経営陣の強いコミットメントと組織的な能力が問われます。
今後の展望として、以下の点が重要となります。
- 経営の最重要課題としての位置づけ
人的資本経営を人事部に任せるのではなく、CEOやCHROが主導し、取締役会が監督する、経営の中核アジェンダとして取り組む必要がある。 - データに基づいた意思決定
人事情報基盤を整備し、「As is-To beギャップ」の可視化と定量的モニタリングを徹底する。 - 対話を通じた浸透
経営陣から現場社員、そして投資家まで、一貫したメッセージを発信し、対話を通じてエンゲージメントと理解を深める。 - 文化への変革
制度改革だけでなく、社員一人ひとりが自律的にキャリアを考え、挑戦できる企業文化を醸成することが、最終的な成功の鍵となる。
企業が人材への投資を本格化させ、個人の能力を最大限に引き出すことができれば、それは個々の企業の価値向上にとどまらず、日本経済全体の活性化とイノベーション創出につながる大きなポテンシャルを秘めています。
音声解説:詳細版(約22分)
ガイド:Q&A
問1: 「人的資源(Human Resource)」と「人的資本(Human Capital)」の捉え方の違いと、それがマネジメントに与える影響について説明してください。
「人的資源」は既に持っているものを消費するという考え方で、管理が目的となり、資金は「費用」と捉えられます。一方、「人的資本」は価値創造の担い手として成長するもので、マネジメントは「価値創造」が目的となり、資金は「投資」と捉えられます。この転換により、人材への関わり方が管理から価値創造へと変わります。
問2: 人材戦略に求められる「3P・5Fモデル」とは何か、その構成要素を簡潔に説明してください。
「3P・5Fモデル」とは、企業価値向上につながる人材戦略を特徴づけるフレームワークです。3つの視点(Perspectives)は「①経営戦略との連動」「②As is-To beギャップの定量把握」「③企業文化への定着」です。5つの共通要素(Common Factors)は「①動的な人材ポートフォリオ」「②知・経験のダイバーシティ&インクルージョン」「③リスキル・学び直し」「④従業員エンゲージメント」「⑤時間や場所にとらわれない働き方」を指します。
問3: 経営陣のコアメンバーとして連携が必要とされる「5C」とは誰を指しますか?また、その連携がなぜ重要だとされていますか?
「5C」とは、CEO(最高経営責任者)、CSO(最高経営戦略責任者)、CHRO(最高人事責任者)、CFO(最高財務責任者)、CDO(最高デジタル責任者)を指します。人材、資金、技術・情報に関する戦略がバラバラに策定・実行されるのではなく、一元的に策定・実行されるよう、これらの経営陣が密接に連携することが重要だとされています。
問4: 人材戦略の策定において、「As is-To beギャップ」を定量的に把握することがなぜ重要だと述べられていますか?
「As is-To beギャップ」を定量的に把握することは、人材戦略がビジネスモデルや経営戦略と連動しているかを客観的に判断するために重要です。これにより、現状の課題が明確になり、どのような時間軸でどのようにギャップを埋めていくかという具体的な戦略策定が可能になります。また、PDCAサイクルを通じて人材戦略を不断に見直すためや、ステークホルダーとの対話においても重要な基盤となります。
問5: 「従業員エンゲージメント」とは何か、また、なぜ日本企業にとって重要な課題だと指摘されていますか?
「従業員エンゲージメント」とは、「企業が目指す姿や方向性を、従業員が理解・共感し、その達成に向けて自発的に貢献しようという意識を持っていること」を指します。Gallup社の調査によれば、日本の「熱意あふれる社員」の割合は世界各国と比較して著しく低く、従業員が自律し、自発的な貢献意欲に溢れているとは言えない状況にあるため、重要な課題だと指摘されています。
問6: レポートで言及されている「動的な人材ポートフォリオ」とはどのような概念ですか?また、「人的資本経営に関する調査」では、この取り組みの進捗についてどのような結果が示されましたか?
「動的な人材ポートフォリオ」とは、現在の経営戦略の実現や新たなビジネスモデルへの対応に必要な人材を、将来的な目標からバックキャストして質・量の両面で定義し、獲得・育成・再配置を通じて適時最適な状態を維持する概念です。「人的資本経営に関する調査」では、経営陣・従業員ともに、この「動的な人材ポートフォリオ」に関する取り組みの進捗が最も遅れていると認識している結果が示されました。
問7: 人材戦略に関して、取締役会が果たすべき主な役割を2つ挙げてください。
取締役会の主な役割は、第一に、経営陣が策定した人材戦略が経営戦略と連動し、企業価値向上につながるかを確認し承認することです。第二に、CxOのサクセッションプランや経営戦略に不可欠な人材パイプラインの構築・運用が適切に行われるよう、KPI等も活用しながら実効的に監督・モニタリングすることです。
問8: 「人材版伊藤レポート2.0」で、経営戦略と人材戦略を連動させるための最も重要なステップとして挙げられている2つの取り組みは何ですか?
「人材版伊藤レポート2.0」では、最も重要なステップとして「CHROの設置」と「全社的経営課題の抽出」が挙げられています。経営トップと人材戦略の責任者(CHRO)を中心に、経営戦略実現の障害となる人材面の課題を整理し、対話を深めることが、両戦略の連動につながる第一歩であるとされています。
問9: 「ジョブ型雇用」への移行が求められる背景と、そのアプローチについてレポートではどのように述べられていますか?
「ジョブ型雇用」は、事業環境の急速な変化や非連続的なイノベーションが頻発する中で、変化に対応した人材の育成・獲得や従業員の専門性向上が課題となっている背景から求められています。レポートでは、メンバーシップ型とジョブ型のハイブリッド型や、組織全体で順次移行していくアプローチなど、業種や会社の状況に応じた経営判断が必要であると述べられています。
問10: 投資家は、人的資本経営においてどのような役割を果たすことが期待されていますか?
投資家には、中長期的な視点から投資先企業の持続的成長を促す目的で、建設的な対話を行うことが期待されています。特に、ESG要因の中でもS(ソーシャル)要因としての人材戦略が企業価値向上に不可欠であるとの認識のもと、企業からの情報開示(見える化)を踏まえ、CEOやCHROと人材戦略について積極的に対話し、それを投資先の選定に活かす役割が求められます。
用語集
| 用語 | 説明 |
| 人的資本 (Human Capital) | 人材を、消費される「資源」ではなく、教育や研修、日々の業務等を通じて成長し、価値創造の担い手となる「資本」として捉える考え方。この考え方では、人材への資金投下は「費用」ではなく「投資」となる。 |
| 人材版伊藤レポート | 経済産業省の「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」が2020年9月に公表した報告書。持続的な企業価値向上のために、ビジネスモデル、経営戦略と連動した人材戦略の重要性を提言した。 |
| 人材版伊藤レポート2.0 | 2022年5月に公表された、「人材版伊藤レポート」の内容をさらに深掘り・高度化した報告書。「経営戦略と連動した人材戦略をどう実践するか」に主眼を置き、具体的なアイディアや施策、先進企業の事例を提示している。 |
| 3P・5Fモデル | 人材戦略に求められる3つの視点(Perspectives)と5つの共通要素(Common Factors)を整理したモデル。企業価値向上につながる人材戦略を策定・実行するためのフレームワーク。 |
| 3つの視点 (Perspectives) | ①経営戦略と人材戦略が連動しているか、②目指すべきビジネスモデルや戦略と現状の人材戦略とのギャップ(As is-To beギャップ)を把握できているか、③人材戦略が実行される中で企業文化として定着しているか、という3つの観点。 |
| 5つの共通要素 (Common Factors) | ①動的な人材ポートフォリオ、②知・経験のダイバーシティ&インクルージョン、③リスキル・学び直し、④従業員エンゲージメント、⑤時間や場所にとらわれない働き方。 |
| CHRO (最高人事責任者) | Chief Human Resource Officerの略。経営陣の一員として、CEOの戦略パートナーとなり、経営戦略と連動した人材戦略の策定・実行を主導する責任者。従来の人事部長とは役割が異なる。 |
| 5C | 経営戦略の実行において密接な連携が求められる経営陣のコアメンバー。CEO(最高経営責任者)、CSO(最高経営戦略責任者)、CHRO(最高人事責任者)、CFO(最高財務責任者)、CDO(最高デジタル責任者)を指す。 |
| As is-To beギャップ | 人材戦略において、目指すべき将来の姿(To be)と現在の姿(As is)との間の差分。このギャップを定量的に把握し、それを埋めるための戦略を策定することが重要とされる。 |
| 従業員エンゲージメント | 「企業が目指す姿や方向性を、従業員が理解・共感し、その達成に向けて自発的に貢献しようという意識を持っていること」を指す。従業員満足度とは異なり、会社の目指す方向性を物差しとする。 |
| 動的な人材ポートフォリオ | 経営戦略の実現に必要な人材を質・量の両面で定義し、そのギャップを埋めるために、平時からリスキル、再配置、外部人材の獲得などを行い、人材構成を適時最適な状態に維持する考え方。 |
| 知・経験のダイバーシティ&インクルージョン | 性別や国籍といった属性だけでなく、経験や感性、価値観、専門性といった「知と経験」の多様性を積極的に取り込み、イノベーションの創出につなげること。 |
| リスキル・学び直し | 事業環境の急速な変化に対応するため、個人が新たなスキルを獲得したり、既存のスキルを時代に合わせて更新したりすること。企業は個人の自律的なキャリア構築を支援することが求められる。 |
| ジョブ型雇用 | ポストに求められる職務内容を明確にし、その職務の遂行に必要なスキルを有する人材の活躍を促す雇用形態。従来のメンバーシップ型雇用と対比される。 |
| サクセッションプラン | 後継者計画のこと。取締役会が、CxO(経営幹部)の交代と後継者の指名・育成計画が適切に策定・運用されるよう実効的に監督することが求められる。 |
| KPI (重要業績評価指標) | Key Performance Indicatorの略。人材戦略の文脈では、目指すべき姿を定量的に示す指標として設定し、As is-To beギャップの把握や進捗のモニタリングに活用される。 |
| パーパス (Purpose) | 企業の存在意義。自社が何のために存在し、社会においてどのような価値を提供するのかを定義したもの。企業理念の核となり、従業員のエンゲージメントを高める上でも重要となる。 |
| アルムナイ | 企業の退職者・卒業者のこと。退職後も優良な関係を築き、ネットワークを活用することで、再雇用やビジネス連携につなげ、人的資本の範囲を拡大する考え方。 |
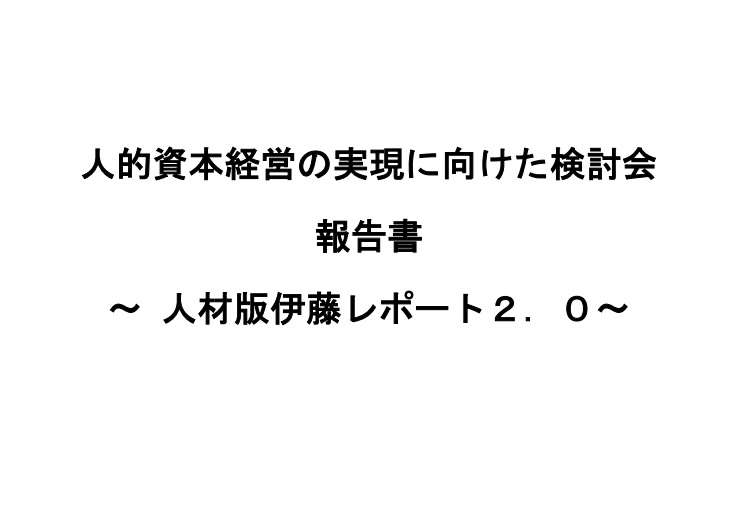

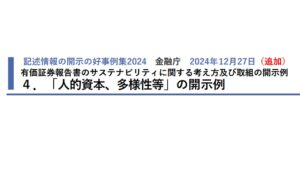
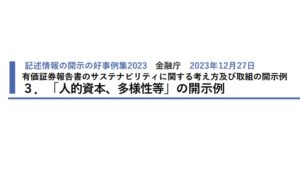
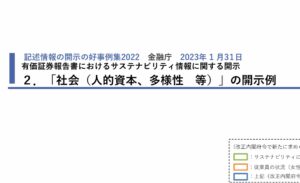
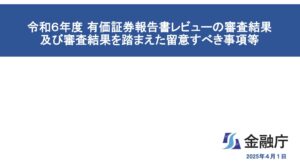
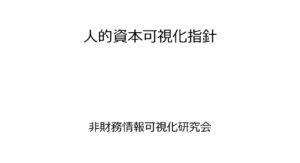
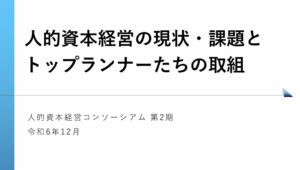
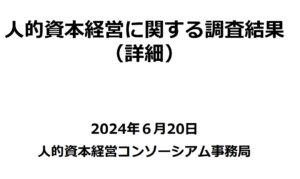
コメント