はじめに
近年、企業の人的資本(従業員のスキルや知識、経験、働きがい等)の情報開示がグローバルに重要視されています。投資家や規制当局は、人材への投資や多様性・育成状況などを企業価値やサステナビリティ評価の観点から重視し始めており、各国で関連ルールの整備やガイドライン策定が進んでいます。
本記事では、アメリカ、EU諸国(含むイギリス)を中心に、日本や特徴的な動きを見せるシンガポール、オーストラリア、カナダも含めて、人的資本開示に関する法規制・ガイドライン、政策動向、企業実践例、国際フレームワークとの連携状況を概観します。
また各国間の共通点・相違点も整理し、比較しやすい表形式でまとめます。
動画簡易解説
アメリカ(米国)における人的資本情報開示
法的義務・ガイドライン
米国では上場企業に対し、証券取引委員会(SEC)規則によって人的資本情報の開示が求められています。2020年のSEC規則改正により、企業は年次報告書(Form 10-K)で「従業員数」と「事業の理解に重要な範囲での人的資本リソースに関する事項」を開示することが義務付けられました。具体的な項目は定めず原則ベースで、「人材の育成・確保・維持」に関する指標や目標など、各社が重要と考える情報を記載する柔軟な内容です。このため企業間で開示項目がまちまちになり、比較可能性の欠如が指摘されてきました。
2023年現在、SECは人的資本開示の標準化に向けたルール改訂を検討中です。新ルール案では開示すべき具体的指標の明確化が議論されており、もし施行後2年以内にSECが基準策定を完了しない場合はISO 30414(人的資本報告の国際ガイドライン)が開示基準として適用される条項も検討されています。これは米国議会や規制当局が国際標準との調和を意識していることを示唆します。
もっとも、この新ルール案の公開は度重なる延期となっており(当初2022年10月予定→2024年以降に後ろ倒し)、2024年7月時点でも正式提案は出されていません。SECの規制方針は政権交代による影響も受けており、直近では気候開示規則など他のESG分野を優先する中で人的資本ルールの行方は不透明になっています。
ただしSECの投資家助言委員会などからは人的資本情報の定量指標導入や開示強化を求める勧告も出ており(2023年9月に勧告採択)、今後の動向が注目されています。
政策動向・支援策
米国政府全体として人的資本開示を直接義務付ける法律は現時点でありませんが、投資家団体による働きかけや官民イニシアティブが存在します。たとえば人材マネジメント連合(Human Capital Management Coalition)など機関投資家グループはSECに対し人的資本開示の強化を継続的に請願しており、人的資本を「価値創造に不可欠な要素」と位置付ける声が高まっています。
また企業側もSECルールを見据えて自発的開示を進める動きがあります。米労働省などが直接関与した支援策は限定的ですが、代わりに投資家のエンゲージメント(議決権行使指針で開示要求をする等)や、業界団体による人材指標のベストプラクティス共有など、民間主導の動きが政策的な後押しとなっています。
企業の実践例
原則主義の開示義務にもかかわらず、多くの米国大手企業は人的資本に関する定量データや目標を自主的に公開し始めています。S&P100企業では従業員の多様性(人種・性別構成)や研修投資額、従業員エンゲージメント調査結果などを年次報告書やサステナビリティ報告で言及する例が増えました。
ある調査によれば、才能開発、D&I(多様性と包摂)、人材の採用・定着、従業員報酬・福利厚生といった項目はほぼすべての大企業で言及されており、過半の企業が従業員の数値データ(例えばジェンダー多様性や従業員離職率など)も開示しつつあります。
例えばテクノロジー企業や金融機関では、従業員のスキル向上プログラムや多様性目標を詳細に報告するケースが一般的です。また、マイクロソフトやセールスフォースといった先進企業は人的資本レポートを別途発行し、従業員の多様性指標や研修時間、従業員満足度の推移等を公開しています。こうした自主的な開示の背景には、投資家からの情報要求や優秀な人材確保のため自社の働きがいを示す必要性があると考えられます。
もっとも、開示内容は各社の判断に委ねられているため、具体的離職率を示す企業は2割弱に留まるなどばらつきも見られます。米国では業種横断的な統一指標はまだ確立していない状況です。
国際的イニシアティブとの連携
米国企業は主にSASB標準やGRI基準などを任意で参照しつつ、自社に関連が深い人的資本指標を選択する傾向があります。また、ISO 30414についてはSEC新ルール検討過程で参照基準として明示されるなど注目が高まっています。米国発のイニシアティブでは、企業の人材投資を会計上資本化して測定する「人的資本会計(HCA)」の概念も議論されています。
さらに、世界経済フォーラム(WEF)のステークホルダー資本主義指標にも多くの米国企業が賛同しており、150社超のグローバル企業(IBM、マスタカード、ペイパル、セールスフォース、ユニリーバ等を含む)が多様性・賃金・健康安全など人材関連の共通KPIを自主開示しています。
総じて米国では、規制面では原則主義である一方、国際的な枠組みへの企業の自主対応や投資家主導の動きが人的資本情報開示を牽引している状況です。
欧州連合(EU)における人的資本情報開示
法的義務・ガイドライン
EUは世界で最も人的資本開示ルールが厳格とされ、詳細な法定開示を段階的に導入しています。
2017年施行の非財務情報開示指令(NFRD)では、大企業に対し「従業員や多様性、雇用条件、人権等」に関するポリシーや成果指標の開示を義務付けました。
さらに2022年には改正指令である企業サステナビリティ報告指令(CSRD)が成立し、2024年から順次適用開始となります。CSRDでは開示範囲を大幅に拡大し、従業員関連情報を含むESG情報を詳細かつダブル・マテリアリティ(企業への影響と企業から社会・環境への影響の双方)の観点で報告することを求めています。
具体的には、EUが策定した「欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)」に沿って、企業は自社の「自社従業員(Own Workforce)」に関する定量・定性情報を網羅的に開示しなければなりません。ESRSの一つ「ESRS S1(自社従業員)」は17~26項目もの開示要求を定めており、多様性(ジェンダーや年齢構成)や公正な賃金、労働条件、労働安全衛生、従業員エンゲージメント、研修と能力開発、労働組合との関係、苦情処理制度など幅広い指標が含まれます。
例えば従業員の離職率や平均研修時間、男女別の賃金差等の開示も求められており、各社は定量データを含めた詳細報告が必要です。これらの報告は財務報告と同様に監査(アシュアランス)の対象ともなるため、信頼性確保も義務付けられます。要件の対象企業は上場・非上場を問わず一定規模以上(例:従業員250人超などの基準を2つ以上満たす企業)に及ぶため、EU域内の多数の企業が人的資本情報の詳細開示義務を負うことになります。
政府・規制当局の政策動向
欧州委員会および各国当局は、人的資本開示を含むサステナビリティ情報の開示充実を政策的優先事項と位置づけています。CSRDの成立・施行に伴い、欧州委員会はEFRAG(欧州財務報告助言グループ)に委託して詳細基準(ESRS)の策定を進め、企業への周知・研修も実施しています。
各国でもCSRDを国内法化する動きがあり、例えばドイツやフランスは国内法で人権・人的資本に関するデューデリジェンスや報告義務を強化する法案を可決しています。またEUは「グリーンディール」政策の一環として社会的公正も重視しており、サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)やEUタクソノミーとの連動で、人材に関する指標(例えば男女賃金差や取締役会の多様性等)も投資商品開示の評価項目に組み込まれています。
政府機関による支援策としては、中小企業向けの開示ガイダンス提供や、各国の企業に対するベストプラクティス事例の共有、労働組合・従業員代表との対話促進などが挙げられます。全体として、欧州ではトップダウンの規制によって企業の人的資本開示を強力に推進している状況です。
企業の実践例
欧州企業は法令遵守として人的資本情報を詳細に報告するだけでなく、統合報告書やサステナビリティ報告書で先進的な人材戦略を発信する企業が多く見られます。
例えば、製薬大手ノバルティスはWEFの人材指標を自社レポートに組み込み、従業員エンゲージメントスコアやスキル研修時間、社内昇進割合などを開示しています。独SAP社は人的資本ROIや従業員活力指数といった独自指標を開発し、年次報告で公表しています。また、ユニリーバは長年にわたり「人的資本報告書」を発行し、人材多様性目標(経営陣の男女比や新興市場出身の幹部比率など)の進捗や従業員の健康・福祉施策の成果を詳細に説明しています。
欧州では伝統的に労使協議制度が発達しており、企業は従業員との対話内容(従業員満足度調査結果や労働協約内容)も報告書で触れる傾向があります。
さらに、フランスのダノンは人的資本会計の考え方を取り入れ、従業員研修への投資額や離職による機会損失を定量化して報告するなどの先進事例も見られます。
EU域内の企業は概して、法令順守を土台に自主的な情報発信を競い合う状況にあり、従業員の多様性指標(男女比・国籍比など)や労働安全指標(労災発生率等)の開示は大企業では標準的です。
国際イニシアティブとの連携
欧州の基準策定はGRI(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)や国連持続可能な開発目標(SDGs)とも整合しています。ESRS自体、GRI基準やISO30414の指標セットを参照しており、国際的なフレームワークとの親和性が高くなっています。
さらにEUはISSB(国際サステナビリティ基準審議会)のグローバル基準策定にも積極的に関与しており、将来的な統合を視野に入れています。欧州企業の多くは既にWEFの共通指標やISO30414を自社報告に取り入れ始めています。
例えばドイツのシーメンスやイギリスのHSBC、オランダのDSMなどはWEFのステークホルダー資本主義指標にコミットし、人的資本KPIを国際ベースラインに合わせています。このように欧州は、厳格な地域規制で先導しつつ国際標準化にも寄与することで、各国の人的資本開示ルールの調和を進める立場にあります。
イギリス(英国)における人的資本情報開示
法的義務・ガイドライン
イギリスはEU離脱後も人的資本や多様性に関する開示規制を積極的に維持・強化しています。
まず、大企業には2006年会社法(Companies Act 2006)に基づき年次ストラテジックレポートの作成が義務付けられていますが、その中で「環境、社会、コミュニティ、人権事項」への影響に関する情報開示が要求されます。特に上場企業(quoted companies)は、社員に関する事項として男女別の従業員数(取締役、経営陣、全従業員の性別構成)を報告しなければなりません。
また、従業員500人超かつ売上高5億ポンド超の大企業等にはノンファイナンシャル情報開示ステートメントの作成が義務付けられ、環境・社会・人権・腐敗防止に関する方針・成果を包括的に報告する必要があります。これはEUのNFRDを引き継いだ国内法整備といえます。
さらに英国独自の規制として、2015年現代奴隷法(Modern Slavery Act 2015)により年商3,600万ポンド以上の企業は毎年、自社とサプライチェーンにおける奴隷労働防止の取り組みを説明する「現代奴隷に関する声明」を公表する義務があります。これは強制労働や人身取引への対応を透明化させるものです。
加えて、2017年男女賃金格差報告規則(Equality Act 2010 (Gender Pay Gap) Regulations 2017)により、従業員250人以上の企業は年次の男女平均賃金格差データを政府サイトおよび自社サイトで公開することが義務付けられています。
以上のように、英国では個別項目ごとの開示義務(多様性、賃金格差、現代奴隷など)と包括的な非財務情報開示義務の双方が存在します。さらにコーポレートガバナンス・コード(企業統治コード)でも上場企業に対し「従業員を含むステークホルダーとの協調」や「企業文化・従業員待遇の開示」を求める原則が盛り込まれており、人的資本開示を促進するソフトなガイドラインとなっています。
政府・規制当局の政策動向
英国政府はサステナビリティ開示全般の枠組みとしてサステナビリティ開示要件(SDR: Sustainability Disclosure Requirements)を導入予定で、これは国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準を英国向けに認証・適用するものです。
まず気候関連開示(TCFD対応)が上場企業等に義務化されましたが、今後ISSBの一般的サステナビリティ基準(IFRS S1)が国内基準化されれば、人的資本も含む「サステナビリティ関連リスク・機会」の開示が要請される可能性があります。政府は2024年~2025年にISSB基準を採用する方針を公表しており、これにより人的資本や人権に関する開示も国際基準と整合的に進む見通しです。
規制当局FRC(財務報告評議会)や金融行動監視機構FCAも、人材多様性や社内文化に関する記述の質向上を促すレポートを発行するなど、企業への働きかけを強めています。また英国政府は「良好な就業(Good Work)」や「人的資本経営」を政策課題として掲げ、企業の人的投資拡大や従業員参加の促進策(例:従業員株式所有やスキル訓練への税制優遇)を講じています。
これらは間接的に企業の人的資本開示内容(スキル開発投資額や従業員参加度合い等)の充実につながるものです。
企業の実践例
英国の企業は上述の法規制を遵守しつつ、自主的に充実した人的資本情報を開示する例が多くあります。特にFTSE100企業では、年次報告書の中で従業員に関する章を設け、社員の多様性指標(例:管理職に占める女性比率や民族的マイノリティ比率)、従業員エンゲージメントスコア(年次従業員意識調査の結果)、研修・人材開発への支出額、安全衛生統計(労働災害件数など)を詳細に報告するのが一般化しています。
例えば、HSBCホールディングスは年次報告で社員の地域別・男女別構成や研修時間を開示し、バークレイズ銀行は人材戦略レポートで多様性目標の進捗(例:女性役員数の推移)を公開しています。BPやシェルといったエネルギー大手も、サステナビリティ報告書に安全文化や労働環境の改善目標を掲げ、進捗を測定するKPI(安全インシデント発生率等)を公表しています。
また英国では「ワークフォース・ディスクロージャー・イニシアチブ(WDI)」と呼ばれる投資家主導の枠組みに多数の企業が参加しており、企業はWDIの調査を通じて詳細な労働慣行データ(賃金体系、育児休業取得率、人材定着戦略など)を提供しています。これにより投資家との対話が進み、開示水準の底上げが図られています。
全体として、英国企業は法定項目+αの自主開示に積極的であり、従業員関連の情報を統合報告や指名委員会報告など多様な報告チャネルで発信しています。
国際イニシアティブとの連携
英国は欧州離脱後もグローバル基準へのコミットを強めています。ISSB基準の国内実装方針は上述の通りですが、英国の大企業はそれ以前からGRIスタンダードやSDGsを報告に反映させてきました。
また、ISO30414についても、英国規格協会(BSI)は早くから国内でISO30414の認証スキームを導入し、三井物産(日本企業)やグローバル企業の英国拠点がISO30414認証を取得する動きもあります。
さらに、WEFの共通指標にもBPやユニリーバなど英国企業が参画しており、人材の多様性・公正な賃金・健康推進などの指標について国際比較可能なデータ開示を進めています。英国規制当局も国際監査・保証基準審議会(IAASB)と連携し、人的資本を含むESG情報の保証基準策定に関与しています。
総じて英国は、国内規制の枠内で国際標準を積極的に取り入れ、欧米の架け橋的役割を果たしていると言えます。
日本における人的資本情報開示
法的義務・ガイドライン
日本では2023年3月期決算(令和5年)から、上場企業に対し人的資本情報の開示が正式に義務化されました。具体的には、有価証券報告書の「企業情報」欄において人材戦略や人的資本に関する事項を記載することが求められています。
金融庁が改正した開示府令により、「従業員に関する重要な方針及びその状況」等の開示が明記され、例えば人材育成方針、ダイバーシティ推進施策、従業員のエンゲージメント向上策などを文章で説明する必要があります。また、具体的なKPIとして中途採用比率や女性管理職比率等の開示も促されています。
日本政府(内閣官房)が策定したガイドラインでは、人的資本情報の開示項目として「7分野19項目」が示されており、企業はこれらを参考に情報開示を行います。
7分野とは以下の項目になります。
①人材育成
②エンゲージメント
③流動性(人材の流動・配置)
④ダイバーシティ
⑤健康・安全
⑥労働慣行(働き方改革等)
⑦コンプライアンス・倫理
例えば「人材育成」ではリーダー育成施策や従業員のスキル向上状況、「流動性」では中途採用者比率や離職率、「ダイバーシティ」では女性管理職比率や外国人社員比率、「健康・安全」では労働災害件数や有給取得率、といった具体的指標が念頭に置かれています。
これら19項目はあくまで指針ですが、東京証券取引所もコーポレートガバナンス・コードの補充原則において人的資本や多様性に関する開示を要請しており(2021年改訂版)、上場各社は実質的に対応を求められています。
政府・規制当局の政策動向
日本政府は「新しい資本主義」の柱として人への投資を掲げ、人的資本経営・開示の促進策を次々と打ち出しました。2022年6月の「新しい資本主義」実行計画で人的資本情報の開示拡充が明記され、これを受け金融庁が開示ルールを改正した経緯があります。
加えて経済産業省は「人材版伊藤レポート」(2020年)を発表し、人材戦略と経営戦略の統合や情報開示の在り方を提示しました。2023年には経産省主導で人的資本経営コンソーシアムが設立され、企業・投資家・有識者が連携して開示項目の標準化や優良事例の共有に取り組んでいます。政府は企業による人材投資(リスキリングや賃上げ)を税制優遇などで後押ししつつ、その成果や取り組みを開示させることで資本市場からの評価向上を図ろうとしています。
また金融庁はサステナビリティ開示基準の検討も進めており、将来的にISSB基準や国際基準を取り入れたより詳細な人的資本開示ルール策定の可能性も示唆されています。
政策的支援としては他に、経済産業省が日本健康会議と連携して「健康経営優良法人認定制度」を運営しており、企業がこの認定を取得・開示することが社会的評価や企業価値向上につながる仕組みを整えています。一方で、厚生労働省は労働安全衛生や健康診断、メンタルヘルス対策などの実務的施策を所管しており、経産省の健康経営施策を実務面で支える役割を担っています。
全体として日本は政府主導でガイドライン整備と義務化を急速に進めた点が特徴であり、その背景には「欧米に比べ出遅れた開示を挽回しないと日本市場が評価されない」という強い危機感があったと指摘されています。
企業の実践例
日本企業の人的資本開示は義務化初年度の2023年から大きく前進しました。有価証券報告書の該当欄には多くの企業が2,000字程度を割いて自社の人材戦略を説明しており、93%の企業が個社ベース(単体)で情報開示を行ったとの調査結果があります。
具体的には、「人材育成方針と施策」「従業員多様性の状況」「働き方改革の取組」「人材に関する定量KPI(例:女性管理職〇%、中途採用比率〇%、研修費用〇円など)」を列挙する企業が多いです。
例えば、トヨタ自動車は有報で「多様な人材の活躍」と題し女性管理職比率(2022年度時点で○%)や従業員の平均在社年数等を記載しました。また日立製作所は人財育成投資額や社員エンゲージメントスコアを開示しています。さらに先進的な企業は統合報告書や独立した人的資本レポートを発行し、より詳細な情報発信を始めました。
三井物産は2024年に「人的資本レポート2024」を公開し、従業員の多様性や成長を重視する取り組みを明示しています。三井物産はまたISO 30414の第三者認証も2024年に取得し、人的資本の定量化・分析をグローバル標準で進めていることを表明しました。同社は「未来をつくる人をつくる」というビジョンのもと、人的資本経営を企業価値向上の要と位置づけています。
他にも、双日は統合報告書で「事業と人材のギアチェンジ」をコンセプトに、人材KPIとして2030年代に女性課長比率50%を目標設定するなど具体的数値目標を示しました。ニデック(日本電産)は統合報告書で財務資本・製造資本・知的資本・人的資本・社会関係資本・自然資本の6資本ごとに情報開示する手法をとり、人的資本パートでは人事制度改革(評価・報酬制度の整備)やグローバル人材育成策を詳述しています。
このように、日本企業の人的資本開示は定性的な説明に加え、徐々に定量データや将来目標の提示へと深化しつつあります。ただし現状では、企業ごとに開示フォーマットや指標の選択にばらつきもあり、投資家からは「各社バラバラではなく比較可能性を高めてほしい」との声も上がっています。
今後はガイドラインに沿った開示項目の標準化と、開示した人材データの戦略的活用が課題となっています。
国際イニシアティブとの連携
日本企業・政府も国際的枠組みへの対応を積極化しています。上述のISO30414認証取得はその一例で、他にも経産省はISO30414の活用を企業に推奨しています。また日本政府はISSBやWEFにも参画し、世界共通の人的資本開示基準作りに関与しています。
日本企業ではGRIスタンダード(労働慣行や人権に関する指標)を統合報告に採用するケースが増えており、例えば花王や資生堂はGRI基準に沿った労働指標(従業員区分別の離職率や多様性データ等)を公開しています。さらに、世界経済フォーラムのステークホルダー資本主義指標にもトヨタやソニーなど日本企業が支持を表明し、一部指標を自社報告に取り入れています。国際的な投資家からの要請もあり、TCFDにならぶ人的資本版の情報開示フレームへの期待も高まっています。
日本は現時点では各国基準を参照しつつ独自の枠組み(7分野19項目)を設けていますが、将来的にはグローバル基準との整合を図りながら自国の実情を織り込む形でアップデートしていくものと見られます。
その他の国・地域の動向
シンガポール
アジアの金融ハブであるシンガポールも、人的資本開示を含むESG報告の強化に動いています。シンガポール取引所(SGX)は上場企業に対しサステナビリティ報告の年次提出を義務付け(「遵守か説明か」原則)ており、その中で27のコアESG指標を推奨しています。
これらには「社会」分野の指標として多様性・インクルージョン(社員の性別・年齢構成等)、人材育成(平均研修時間など)、労働安全衛生(労災件数等)が含まれています。
SGXのガイドラインにより、多くの企業がGRI基準や世界経済フォーラム指標に沿って従業員の男女比やトレーニング実績を報告し始めました。また政府は人材開発奨励プログラム(Human Capital Partnership Program)を通じて企業の従業員育成投資を認証・表彰し、その情報開示を促しています。
今後はISSB基準の導入検討も進んでおり、地域のハブとして国際基準への適合を急ぐ動きです。
オーストラリア
オーストラリアでは包括的な人的資本開示の法制化はまだですが、一部領域に特化した開示義務があります。
代表例が「職場男女平等法(Workplace Gender Equality Act 2012)」で、従業員100人超の民間企業に対し毎年、男女の雇用状況や賃金格差等に関する詳細データを政府機関(WGEA)へ報告することを義務付けています。これにより各社の男女比、管理職に占める女性割合、育児休業復帰率等が政府年次レポートで公表され、社会からの監督を受けています。
また2018年施行の現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018)では、オーストラリアでも年商基準を満たす企業に対しサプライチェーンの奴隷労働リスクに関する年次開示を義務付けました。企業の自主的な動きとしては、ASX企業が統合報告やサステナビリティ報告で従業員多様性や先住民雇用方針などを開示する例が増えています。
例えばテルストラ(通信)は従業員エンゲージメント指数や健康安全指標を年次報告に掲載し、BHP(資源)は先住民の雇用者数目標や研修プログラム成果を報告しています。オーストラリア証券取引所はコーポレートガバナンス原則の中で「役員会は企業文化や従業員行動規範を監督すべき」などの原則を掲げ、人的資本に関する開示を間接的に促しています。
今後、ISSB基準採用の検討(豪会計基準審議会が議論中)や、人権デューデリ法制化の動きもあり、人的資本開示が一層制度化されていく可能性があります。
カナダ
カナダでは人的資本開示について連邦レベルの統一規制はまだ整っていません。ESG開示全般が現状任意で、企業ごとに提供情報は様々だと指摘されています。もっとも証券規制当局(CSA)は気候開示義務化を進める一方で、取締役会の多様性開示に関する規則を整備してきました。
例えばカナダの上場企業は、取締役会および上級管理職における女性比率や多様性方針を年次情報通告で「説明責任原則(comply or explain)」の下で開示する必要があります。また2024年には現代奴隷労働に関する報告法案も審議されており、可決されれば大企業に人権・労働リスクの開示義務が生じます。企業の自主的取組としては、カナダロイヤル銀行(RBC)やトロント・ドミニオン銀行(TD)がD&Iレポートを発行し人種・性別多様性データや従業員アンケート結果を公開するなど、北米のベストプラクティスに倣った開示が増えています。
カナダ政府は2024年10月、気候関連開示を大企業の義務にする方針を発表しましたが、人的資本に関しては今のところ指針的措置(例:従業員の権利章典策定の推奨等)に留まっています。ただしカナダは多文化社会であり、企業も先住民コミュニティ支援や移民労働力の統合に関する情報をレポートで言及する傾向が強いです。
今後はグローバル投資家の要求に合わせ、自主ガイドライン(例えばカナダCSR基準)の整備やISSB基準の導入により人的資本開示が充実していくと見込まれます。
各国の比較:人的資本開示の制度と取組状況
上述の内容をまとめ、主要国・地域における人的資本情報開示の状況を比較表に整理します。
各国の法的義務やガイドラインの有無・内容、政策的支援策、企業実践の特徴、国際枠組みへの対応を一覧で示します。
| 国・地域/観点 | 法的義務・基準 | 政策動向・支援策 | 企業の実践例 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | SEC規則により2020年から人的資本情報の開示義務(従業員数と重要な人材事項の記述)。現在は原則ベースで明確な指標規定なし。新たな詳細ルール案を検討中だが提案未了(ISO30414適用条項含む可能性)。 | SECが開示強化を課題認識(投資家助言委の勧告あり)。政権交代でESG規制の優先度変動。政府として直接支援策少ないが、投資家団体(HCMC)の請願など民間圧力強。人的資本会計導入の議論も。 | S&P100の全社がHCM記載あり。多くは多様性指標(女性・マイノリティ比率)や研修/福利厚生等を言及。一部企業は人的資本レポートや詳細データ(離職率、従業員満足度等)を自主開示。例:マイクロソフト(D&Iレポート)、スターバックス(人材多様性と賃金公平性公開)など。 |
| EU (欧州連合) | 法令で義務化。2017年NFRDで社会・人材に関する開示を義務付け。2024年開始のCSRDでESRS S1等詳細基準に基づき人的資本の網羅的報告が必須(ダブルマテリアリティと詳細KPI)。監査必須。 | 欧州委員会/EFRAGが詳細基準策定・周知。加盟国も国内法で追従し広範な企業に適用。社会的公正重視の政策(グリーンディール)で人権デューデリジェンス法等も推進中。中小企業支援ガイドや教育も実施。 | 大企業は詳細開示が標準。多様性・賃金・安全・労組対応等のKPIを年次報告書や統合報告で網羅。例:ノバルティス(人材KPIとWEF指標報告)、ユニリーバ(人材報告書発行)、SAP(従業員エンゲージメント指数開示)。 |
| イギリス | 法令で複数義務。会社法に基づく戦略報告で環境・社会・人権事項開示(性別構成含む)。年商規模要件で非財務情報ステートメント義務。現代奴隷法で年次声明義務、男女賃金格差公開義務(従業員250人超)。 | 政府はISSB基準導入(SDR)方針。FRC/FCAが報告指針・レビュー発行で質改善誘導。現代奴隷法改正(報告強化)検討中。人的資本開示はコーポレートガバナンス改革の一部として推進。 | FTSE企業中心に積極開示。年次報告の「People」章で従業員エンゲージメント指数や研修投資額等を報告。WDI経由で労働データ提供企業も多数。例:BP(安全指標と労働者エンゲージメント公開)、HSBC(地域別人員構成と多様性目標公表)。ガバナンス報告で従業員との対話状況を説明する企業も。 |
| 日本 | 法令で義務化。2023年から有価証券報告書で人的資本情報の開示を義務(人材戦略方針や多様性施策等)。ガイドラインで7分野19項目の具体例提示。CGコード補充原則でも人的資本開示を要請。 | 政府主導で開示促進(新資本主義計画に明記)。金融庁が開示府令改正、経産省が人的資本経営コンソーシアム設立。人的投資促進のため税制支援も。ISSB基準検討WG発足し国際調和模索。 | 上場企業は有報で人材戦略を記述(平均2千字規模)。中途採用比率・女性管理職比率など定量開示も増加。統合報告等でさらなる情報発信を行う先進企業あり。例:三井物産(人的資本レポート・ISO30414認証取得)、トヨタ(従業員多様性データ開示)、資生堂(人材育成投資額開示)。 |
| シンガポール | 取引所ルールでサステナビリティ報告義務(遵守or説明)。SGXが27のコアESG指標(人材多様性・研修時間・安全等)を推奨。法的強制力は限定的だが実質的遵守率高。 | 政府は人材開発を重視(人材育成助成や雇用パス制度)。ESG報告は金融庁MASが監督。ISSB基準の早期導入検討を表明(地域ハブ戦略)。 | 主要企業はGRI準拠報告で従業員指標を公表。銀行や不動産など多くがサステナビリティ報告に雇用多様性・研修実績を掲載。例:DBS銀行(従業員男女構成と育成プログラム成果報告)、シンガポール航空(従業員訓練時間と安全記録を開示)。 |
| オーストラリア | 法令で部分義務。WGEA法で企業(従業員100人超)に男女雇用指標の年次報告義務。現代奴隷法で人権リスク声明義務。包括的HCM開示義務は未整備(気候開示は検討中)。 | 政府は新たにGender Equality推進で企業の男女平等目標設定を奨励。現代奴隷レジストリ構築など透明性向上策。ISSB基準採用検討中で人的資本も将来包含の可能性。 | 多くは自主ESG報告で対応。鉱業・金融などは先住民雇用や安全実績を積極開示。例:RIO Tinto(労働安全統計とダイバーシティ目標公表)、コモンウェルス銀(従業員多様性・働きがい調査結果を開示)。法定項目(男女比等)以外も先進企業は報告。 |
| カナダ | 法令で部分義務。明確なHCM開示法はないが、証券規則で取締役会の多様性開示を事実上義務化。気候開示義務化方針あり。人的資本は自主報告段階。現代奴隷法案が審議中。 | 政府は気候に注力(グリーンボンド発行等)。人的資本は審議会で議論段階。多文化政策の一環で先住民雇用推進(企業に自主開示奨励)。証券庁がESG情報の任意開示ガイド発行。 | 開示先進企業と遅れの二極化。一部大企業(RBCなど)はD&Iレポート発行し人種・性別構成や従業員意識調査結果を公表。一般にはGRIやSASBに沿った開示は任意。資源企業は先住民支援策等を報告書で強調する傾向。全体として自主性に委ねられ標準化途上。 |
表より明らかなように、EUと日本が法定開示の網の広さ・細かさで突出しており、米国とカナダは制度面では緩やかながら企業自主努力や投資家圧力が重要な役割を果たしています。
英国やシンガポール、オーストラリアは国際標準を積極的に取り込みつつ、自国内の重点課題(英:現代奴隷・ジェンダー、豪:ジェンダー平等、星:国際整合)にフォーカスした義務を課している点が特徴です。
おわりに~各国の共通点と相違点~
各国の人的資本開示への取り組みには、「何をどこまで義務化するか」というスタンスの違いが表れています。
各国のスタンス
欧州型(EU・英国)は詳細かつ広範な情報開示を法律で強制し、企業に比較可能なデータ提出を求める傾向があります。一方、米国型は「重要な情報は自主的に開示させる」原則主義であり、市場のニーズに応じ企業が競って開示を充実させるアプローチです(もっとも近年は米国でも具体的指標導入の議論が高まっています)。
日本は欧州に近い積極姿勢で法定開示を導入しましたが、まだ指標の標準化は途上であり、今後は欧州のESRSや国際基準との整合が課題です。シンガポールやカナダ、オーストラリアは欧米の動きを睨みつつ、自国市場の特性に応じた部分的義務化(例:ジェンダーや人権)から着手している段階です。
共通点
共通点として、どの国でも「企業価値にとって人材が重要」との認識が広がり、投資家・ステークホルダーから情報開示を求める圧力が高まっていることが挙げられます。そのため各国政府・規制当局は程度の差こそあれ、人的資本開示をESG政策や資本市場改革の一環として推進しています。
またISO 30414やGRI、WEF指標、ISSBなど国際的フレームワークが各国で参照・活用され始めており、開示項目の国際統一化に向けた動きも共通しています。特にISSBは今後2024-26年に人的資本と人権の開示基準策定を進める計画で、これが実現すれば各国基準を横断するグローバル標準が整う可能性があります。
相違点
相違点としては、法制度のアプローチ以外に開示の深度や焦点の違いがあります。
例えば欧州では労働者の権利・人権(労組との関係や人権デューデリ)が重視され、米国では人的資本の投資効果(人材が業績に与える影響や生産性)が関心事となりがちです。日本やアジアでは従業員のエンゲージメントや健康経営といったテーマが強調される傾向があります。
さらに、企業文化や雇用慣行の違いから、生データの意味合いにも差があります(例:終身雇用慣行の日本では離職率は低く出るが、それをどう評価するか等)。したがって、単純な数値比較ではなく各国の文脈を踏まえた分析が必要です。
人的資本情報の開示はまだ発展途上の分野ですが、「人への投資なくして持続的成長なし」との共通認識のもとで世界的な潮流が形成されています。企業にとっては、自社の人材戦略をストーリーとして示し、定量データで裏付けることで投資家や社会からの信認を得る好機です。今後は各国で培われたベストプラクティスを共有し合い、国際的に調和の取れた人的資本開示基準が確立されていくことが期待されます。
音声動画
今回の内容を動画で振り返ることで理解が深まります。
ガイド:Q&A
1. 日本で2023年3月期決算から上場企業に義務付けられた人的資本情報開示について、政府が策定したガイドラインが示す枠組みの名称と、その具体的な内容を説明してください。
政府が策定したガイドラインでは「7分野19項目」の枠組みが示されています。これは、①人材育成、②エンゲージメント、③流動性、④ダイバーシティ、⑤健康・安全、⑥労働慣行、⑦コンプライアンス・倫理の7分野にわたり、女性管理職比率や離職率などの具体的な指標例を示し、企業が開示を行う際の参考となるものです。
2. EUの「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」が導入した「ダブル・マテリアリティ」とはどのような考え方ですか。また、CSRDは開示情報に対して何を義務付けていますか。
「ダブル・マテリアリティ」とは、企業価値に対する外部環境の影響(財務的マテリアリティ)だけでなく、企業活動が社会や環境に与える影響(インパクト・マテリアリティ)の双方の観点から重要性を判断する考え方です。CSRDは、この考え方に基づき開示された情報が、財務報告と同様に第三者による監査(アシュアランス)を受けることを義務付けています。
3. アメリカの証券取引委員会(SEC)が定める人的資本開示ルールは「原則主義」と呼ばれますが、これはどのようなアプローチですか。また、このアプローチが抱える課題は何ですか。
「原則主義」とは、開示すべき具体的な項目を定めず、各企業が自社の事業にとって重要と考える人的資本に関する事項を柔軟に記載するアプローチです。このため、企業間で開示項目にばらつきが生じ、投資家が企業間比較を行うことが困難になるという課題が指摘されています。
4. イギリスの人的資本開示には、他の国にはない特徴的な法的義務が複数存在します。その中から2つの具体的な法律または規則の名称と、その内容を挙げてください。
イギリスの特徴的な法的義務として、「2015年現代奴隷法」と「2017年男女賃金格差報告規則」が挙げられます。前者は企業に対しサプライチェーンにおける奴隷労働防止の取り組みに関する年次声明の公表を義務付け、後者は従業員250人以上の企業に男女間の平均賃金格差データの公開を義務付けています。
5. 国際ガイドラインである「ISO 30414」とは何ですか。また、アメリカや日本の規制・企業活動において、どのように参照または活用されていますか。
「ISO 30414」は、人的資本報告に関する国際的なガイドラインであり、開示すべき指標などを標準化しています。アメリカではSECの新ルール案で参照基準として適用される可能性が検討されており、日本では経済産業省が活用を推奨し、三井物産などの企業が第三者認証を取得する動きが見られます。
6. 人的資本開示における「欧州型」と「米国型」のアプローチの主な違いを、規制の観点から説明してください。
「欧州型」は、CSRDのように詳細かつ広範な開示項目を法律で定め、比較可能なデータの提出を企業に強制するアプローチです。一方、「米国型」は、SEC規則のように開示の原則のみを示し、市場のニーズに応じて企業が自主的に情報開示を充実させることを促すアプローチを取っています。
7. オーストラリアが人的資本に関連して法的に義務付けている報告内容の中で、特にジェンダーに関するものは何ですか。
オーストラリアでは「職場男女平等法(Workplace Gender Equality Act 2012)」に基づき、従業員100人超の民間企業は毎年、男女の雇用状況や賃金格差に関する詳細なデータを政府機関へ報告することが義務付けられています。これにより、管理職の女性比率や育児休業復帰率などが公表されます。
8. ソースコンテキストで言及されている日本企業の先進的な開示例として、三井物産が2024年に実施した2つの具体的な取り組みを挙げてください。
三井物産は2024年に、詳細な情報発信を行うための独立した「人的資本レポート2024」を公開しました。さらに、人的資本の定量化と分析をグローバル標準で進めていることを示すため、人的資本報告の国際ガイドラインである「ISO 30414」の第三者認証を取得しました。
9. シンガポール取引所(SGX)は、上場企業に対して人的資本情報を含むサステナビリティ報告をどのように促していますか。その原則と推奨される指標について説明してください。
シンガポール取引所(SGX)は、「遵守か説明か(Comply or Explain)」の原則に基づき、上場企業にサステナビリティ報告の年次提出を義務付けています。その中で、人材の多様性(性別・年齢構成)、平均研修時間、労働安全衛生などを含む27のコアESG指標を推奨し、企業の情報開示を促しています。
10. 国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、今後の人的資本開示においてどのような役割を果たすと期待されていますか。
ISSBは、2024年から2026年にかけて人的資本と人権に関する開示基準の策定を進める計画です。これが実現すれば、各国の規制や慣行を横断するグローバルな標準が確立され、人的資本情報の国際的な比較可能性が大きく向上することが期待されています。
重要用語集
| 用語 | 定義 |
| 7分野19項目 | 日本政府(内閣官房)が策定した人的資本可視化指針で示された開示項目のフレームワーク。「人材育成」「ダイバーシティ」「健康・安全」など7つの分野と、それに対応する19の開示項目例から構成される。 |
| CSRD (企業サステナビリティ報告指令) | 2024年からEUで順次適用が開始された、企業のサステナビリティ情報開示を大幅に強化する指令。NFRDを改正したもので、ダブル・マテリアリティの観点に基づく詳細な報告と第三者監査を義務付ける。 |
| ダブル・マテリアリティ | 企業のサステナビリティ情報を評価する際の考え方の一つ。企業活動が社会・環境に与える影響(インパクト)と、社会・環境の変化が企業に与える影響(財務)の双方の重要性を考慮することを指す。 |
| ESRS (欧州サステナビリティ報告基準) | CSRDに基づき企業が開示すべき情報の詳細を定めたEUの基準。人的資本に関しては「ESRS S1(自社従業員)」があり、多様性や賃金、研修など多岐にわたる具体的な開示要求項目が含まれる。 |
| Form 10-K | 米国の上場企業が証券取引委員会(SEC)に毎年提出する年次報告書。2020年の規則改正以降、本書類で「従業員数」と「事業の理解に重要な人的資本リソース」に関する事項を開示することが義務付けられている。 |
| GRI (グローバル・レポーティング・イニシアチブ) | サステナビリティ報告書に関する国際的な基準を策定している非営利団体、またはその基準のこと。世界中の多くの企業が、労働慣行や人権に関する情報開示を行う際に参照している。 |
| ISSB (国際サステナビリティ基準審議会) | 資本市場向けのサステナビリティ開示基準のグローバルなベースラインを策定するために設立された国際機関。将来的に人的資本に関する統一基準を策定することが期待されている。 |
| ISO 30414 | 人的資本報告に関する国際標準化機構(ISO)のガイドライン。人材の採用、離職、生産性、多様性など11領域にわたる指標を定義しており、情報開示の標準化に貢献する。 |
| NFRD (非財務情報開示指令) | 2017年にEUで施行された、大企業に対し環境、社会、従業員、人権などに関する情報開示を義務付けた指令。後にCSRDによって改正・強化された。 |
| SASB (サステナビリティ会計基準審議会) | 投資家にとって財務的に重要なサステナビリティ情報を業種別に特定し、その開示基準を策定していた米国の団体。現在はISSBに統合されているが、その基準は引き続き多くの企業に参照されている。 |
| SEC (米国証券取引委員会) | アメリカの証券市場を監督する連邦政府機関。上場企業に対し、Form 10-Kを通じて人的資本情報の開示を義務付けている。 |
| WDI (ワークフォース・ディスクロージャー・イニシアチブ) | 投資家が主導する、企業に対して労働慣行に関する詳細なデータ開示を求める国際的な枠組み。イギリスなどで多くの企業が参加している。 |
| WEF (世界経済フォーラム) | ステークホルダー資本主義の実現を掲げ、企業が報告すべき共通のESG指標(ステークホルダー資本主義指標)を提唱している国際機関。人的資本に関する指標も含まれる。 |
| 現代奴隷法 | イギリス(2015年)やオーストラリア(2018年)で制定された法律。一定規模以上の企業に対し、自社およびサプライチェーンにおける強制労働や人身取引のリスクを評価し、その防止に向けた取り組みを年次で報告することを義務付ける。 |
| 人的資本 | 従業員が持つスキル、知識、経験、健康、働きがいなど、企業にとって価値の源泉となる無形の資本。近年、企業価値を評価する上で重要な要素と見なされている。 |
| 人的資本経営コンソーシアム | 日本の経済産業省が主導して設立された、企業、投資家、有識者が連携し、人的資本経営の実践と情報開示に関する優良事例の共有や標準化に取り組むための組織。 |

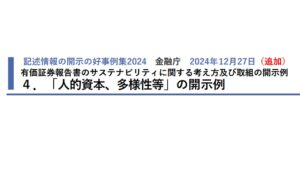
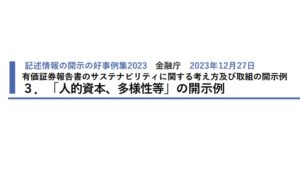
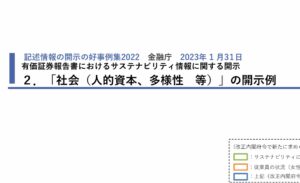
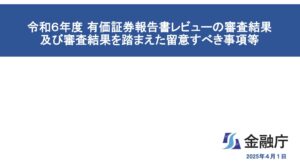
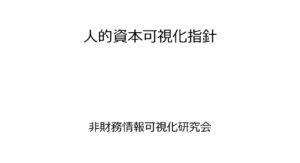
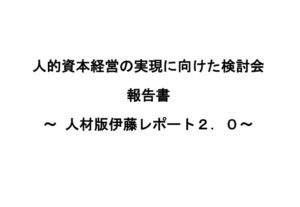
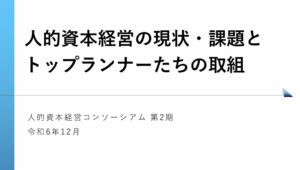
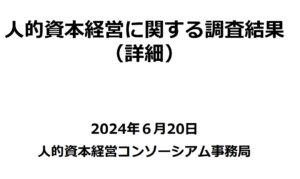
コメント