導入:なぜ人材育成には「計画」が必要なのか
人材不足が深刻化する中、多くの企業で人材育成計画の重要性が認識されています。しかし実際には「計画を作ったが現場で活用されない」「研修が形骸化している」「何から始めればよいかわからない」といった課題も少なくありません。計画書の作成方法がわからず手探りで作成した結果、実効性の低い計画になってしまうケースも多いのです。
実は、人材育成の成否を分ける最大の要因は計画の質にあります。研修が失敗する原因の40%は研修前の準備(計画)の段階にあるとも報告されており、計画内容が不適切では期待する効果を得ることは難しいのです。裏を返せば、研修やOJTなど育成施策の効果は計画段階で決まると言っても過言ではありません。
そのため、人材育成計画を立案する際には現状分析から目標設定、育成手法の選定、効果測定まで体系的に練り上げることが重要です。上層部の協力も得ながら質の高い計画を作ることで、従業員のスキル向上と企業成長を同時に実現する土台が築かれます。
解説動画
人材育成計画とは(定義・目的)
人材育成計画とは、組織の成長戦略に対応するために必要な人材を「いつ」「何人」「どのように」育成するかを具体的に定めた計画のことです。計画を立案する過程では、例えば社員のスキルの現状を整理・把握し、必要な育成方法(集合研修やOJTなど)を検討し、人材育成の全体的な仕組み(スキーム)を決める、といった取り組みが含まれます。
人材育成計画を策定することで、受講者である従業員に「何を習得させるか」だけでなく、提供者である企業側が「どのレベルまで」「どのように教えるか」まで明確になります。これによって人材育成の効率化が図られ、研修が単なるイベントで終わってしまう(形骸化する)のを防止できるというメリットもあります。
なお「人材育成計画」とよく似た言葉に「人材育成ロードマップ」があります。一般的な育成計画が短期的視点で特定のスキル習得に焦点を当てるのに対し、ロードマップは3〜5年スパンの中長期的視点でキャリア段階に応じた成長プロセス全体を設計したものです。単なるスキル研修の計画にとどまらず、企業理念の理解や組織文化の浸透、リーダーシップ育成など総合的な人材成長を計画的に実現するための「羅針盤」の役割を果たします。
効果的な人材育成にはロードマップと具体的な育成計画の両方が必要であり、まずロードマップで中長期の方針を描いた上で、その方針に基づいた研修計画やOJT計画といった 年間の育成計画 に落とし込んでいくことが重要です。
人材育成計画立案のステップ:現状把握・目標設定・ロードマップ策定
人材育成計画を効果的に機能させるには、闇雲に研修メニューを並べるのではなく、順を追った計画策定のステップを踏むことが大切です。ここでは基本となる「現状把握」「目標設定」「ロードマップ策定」の3ステップを解説します。
- 現状把握(自社の状況分析)
まず最初に、自社の経営戦略やビジョンを改めて確認し、「どのような企業を目指しているのか」「そのために必要な組織力・人材像は何か」を明確にします。この段階で経営層にも参画してもらい、中長期の経営戦略と人材育成の方向性を一致させることがポイントです。企業理念から乖離した人材育成をしても企業成長に寄与しない可能性があるため、まず経営戦略と人材育成を連動させる土台を作ります。
次に、現在の社員のスキルや知識レベル、行動特性などを客観的に洗い出します。スキルマップなどのツールを活用して組織全体の強み・弱みを可視化し、「理想」と「現実」のギャップ(スキルギャップ)を分析します。この際、上司評価だけでなく自己評価や360度評価を併用すると、より公平で正確な現状把握が可能です。こうした分析により、既存の人材に不足しているスキルや組織課題が明らかになり、計画の出発点となる現状認識が得られます。 - 目標設定(育成のゴール定義)
現状の分析結果と経営戦略に基づき、育成の目標(あるべき人材像)を具体的に設定します。各職位や職種ごとに「理想の人材像」を定義し、抽象的ではなく具体的な行動や成果で表現することが重要です。例えば「リーダーシップがある人材」ではなく「チームメンバーの強みを引き出し目標達成に導ける人材」のように記述します。理想像と現状のギャップから、どの能力を優先的に育成するかを決めましょう。
一度に全ての課題を解消するのは現実的でないため、経営戦略上の重要度や緊急度、リソース制約を考慮して育成テーマに優先順位を付けます。また「何を育成するか」だけでなく「誰を対象に育成するか」も検討します。新入社員なのか中堅・管理職なのか、役割や成長段階に応じて育成内容を変える方が効果的だからです。
設定した目標はできるだけ定量的・具体的に落とし込みます。SMARTの原則(Specific具体的・Measurable測定可能・Achievable達成可能・Relevant関連性・Time-bound期限設定)のように、例えば「◯ヶ月以内に●●できるようにし、顧客満足度スコアを○点向上させる」といった形で目標を定めると進捗管理がしやすくなります。明確な目標設定によって、後続の研修設計や教材選定もブレなく行えるようになります。 - ロードマップ策定(施策とスケジュールの具体化)
育成のゴールと優先課題が定まったら、いつまでに何をどのように実施するかを時系列で示したロードマップを作成します。例えば「6ヶ月後までに○○のスキルを基礎習得」「1年後までに△△プロジェクトを担当できるようにする」「3年以内に✕✕人のリーダーを育成する」といった具合に、時間軸に沿って具体的な育成アクションと達成基準を配置します。
ロードマップ上には、研修やOJT、メンター制度、自己啓発など複数の育成施策を組み合わせ、各施策の実施時期・頻度を盛り込みます。あわせて各施策の効果測定方法(KPI)も設計しておくと良いでしょう。計画策定後はそれを「作りっぱなし」にせず、定期的に進捗を管理・振り返ります。半年や1年ごとに計画と実績のギャップを分析し、必要に応じて計画をアップデートすることで、環境変化にも対応した実効性の高い育成計画へと進化させていきます。
このようなPDCAサイクルを回すことで、計画段階で立てた仮説を検証しつつ常に計画の精度を高めていくことができます。
ロードマップの構成要素(年間・3年・5年など)
効果的な人材育成ロードマップは短期から中長期にわたる複数のプランで構成されます。
一般的には、会社の経営計画に合わせて 5年程度の長期ビジョン を描き、それを踏まえた 3カ年の中期計画、さらに年間計画(年度計画)へとブレイクダウンしていく形を取ります。最終的には年次計画を四半期ごとのスケジュールや個別の研修プログラムにまで落とし込み、日々の育成行動につなげます。
ここでは代表的な時間軸ごとの計画要素について解説します。
- 年間計画
1年間(または四半期ごと)に実施する育成施策の計画です。新入社員研修や年間の研修カレンダー、OJTの実施スケジュールなど、直近の12ヶ月で「誰に何を実施するか」を具体的に示します。年間計画は中期ロードマップを現場で実行に移すための アクションプラン であり、各研修の日時・対象者・内容・担当者・評価方法などを明記します。
これによって「今年度はどのスキル強化に注力するのか」「いつどの部署で研修が行われるのか」を社内で共有できます。 - 3カ年計画(中期計画)
3年程度のスパンで策定する中期的な育成計画です。企業の中期経営計画と連動させて、人材育成面で達成すべき目標を設定します。「3年後に○○部門のマネージャー候補を△人育成する」「主要技術者の世代交代に備えて若手の専門スキルを底上げする」といった 中期目標を掲げ、その達成に向けた年次ごとのステップを定めます。3カ年計画には各年の重点施策やマイルストーンが示され、進捗を測るための 育成KPI(例:資格取得者数、昇進率、定着率など)も設定します。
中期計画があることで、年度ごとの施策が企業のビジョンに沿った連続性のある取り組みとなり、場当たり的な研修実施を防ぐ効果があります。 - 5年計画(長期計画)
5年先を見据えた長期的な育成ロードマップです。経営層のビジョンを反映し、「5年後にどんな組織・人材像を実現したいか」を描きます。例えば「海外展開に対応できるグローバル人材を○年で▲人育成する」「次世代の経営リーダー候補を輩出する」といった長期ゴールを定め、それを達成するための段階的プロセスをロードマップ化します。長期計画を策定したら、次に3年計画・1年計画・3ヶ月計画といった形で徐々にスパンを短くした具体的アクションプランを決定していきます。
長期ビジョンをこのようにブレイクダウンすることで、遠い目標も日々の具体的な行動に結びつき、着実に前進することが可能になります。
上記は、新入社員向けに5年間の育成ロードマップを策定した一例です。1年目から5年目まで各年次の育成テーマと目標が設定されており、例えば1年目は「OJTによる実務習得」、2年目は「Off-JT研修による専門知識の習得」、3年目は「専門分野の知識強化研修」、4年目は「後輩指導スキルの習得」、5年目は「リーダーシップ研修」など、年次に応じた育成施策と到達目標が一覧化されています。
このように、ロードマップに沿って段階的に能力開発を行えば、従業員それぞれが明確な成長の道筋を描けるようになります。短期的な研修に終始せず長期ビジョンと結びついた育成を行うことで、社員のモチベーション維持・向上にも繋がり、将来的に企業を担う人材を計画的に育てることができるのです。
よくある失敗パターンとその対策
人材育成計画を立てても、「計画倒れ」になってしまうケースは少なくありません。ここでは企業が陥りがちな失敗パターンと、その改善策(対策)をいくつか紹介します。
自社の状況に思い当たる点がないかチェックし、必要に応じて計画の見直しに役立ててください。
- パターン1:計画や研修が形骸化して現場で機能しない
研修や育成計画を作って実施しても、内容が現場の業務とかけ離れていたり座学中心の詰め込みになっていたりして、実務に活かされないケースです。新人研修や定期研修を実施しても「研修内容と実務にギャップがある」と感じる若手社員は68%にも上るとの調査もあり、形式だけの研修では人材の成長につながりません。
対策:
現場のニーズに即した実践的な内容に研修を見直すことが必要です。計画策定時に各部署の声を拾い、研修カリキュラムを業務課題に直結させましょう。例えば机上の講義だけでなく、自社の商品やサービスに即した演習・ケーススタディを取り入れる、研修後に現場での実践課題を与えて定着を図る、などの工夫が有効です。また研修内容は定期的にアップデートし、古いプランを現状の課題に即した内容へ見直すことも大切です。 - パターン2:人事部だけで計画を作り、経営戦略と連動していない
人材育成計画が企業の経営ビジョンや事業戦略と結びついていない場合、せっかく育成しても会社の成長に活きなかったり、肝心の人材が不足したりする事態に陥ります。また経営層のコミットメントが得られず、現場の協力も不十分で計画が机上の空論になりがちです。
対策:
計画策定の初期段階から経営層や各部門の管理職を巻き込み、経営戦略に沿った人材要件の洗い出しを行いましょう。経営層と人材育成担当者の認識をすり合わせ、育成の目的・優先順位を共有することで、計画に一貫性と説得力が生まれます。経営トップからメッセージを発信してもらう、定期的に計画の進捗を経営会議で報告するなど、上層部の協力を得る仕組みを作ることも有効です。計画が企業ビジョンと直結しているほど、現場も「なぜこの育成が必要か」を理解しやすくなり、全社的な取り組みとして推進できます。 - パターン3:フィードバックやフォローが不足して終わりっぱなしになる
研修を受けっぱなしで現場に戻され、その後の上司からのフィードバックや継続的な指導が無いケースです。社員の成長には適切なフィードバックが不可欠ですが、忙しさを理由に上司が部下の育成フォローをしていない企業は少なくありません。年1回の評価面談のみでは日々の課題が放置されがちで、社員のモチベーション低下や離職にも繋がります。
対策:
現場でのフォロー体制を強化しましょう。上司と部下の1on1ミーティングを定期的に実施して業務上の課題や成長度合いを話し合う、メンター制度を導入して若手が相談しやすい環境を整えるなどの方法があります。フィードバック文化を根付かせ、良い点は認め課題は的確に指摘することで、社員は自分の成長を実感できます。実際、定期的にフィードバックを受けている社員の離職率は、そうでない社員に比べ約40%低いとのデータも報告されています。忙しい中でも部下育成に時間を割くことが、長期的には組織力の向上と人材定着に寄与するのです。 - パターン4:キャリアパスが不透明で将来像を描けない
社員が「この会社で成長し続けたらどんなキャリアを積めるのか」が見えないまま日々の業務をこなしていると、モチベーション低下を招きます。特に入社3〜5年目の若手は将来への不安から転職を考えやすく、転職理由の上位に「キャリアの将来性への不安」が挙げられています。明確なキャリアパスを示せない企業では、将来性を求める優秀な人材から先に流出してしまうのです。
対策:
ロードマップを活用して社員にキャリアビジョンを提示しましょう。育成計画の中に「◯年後にはリーダー職へ」「将来的に海外拠点で活躍できる人材へ」といった道筋を盛り込み、社員と面談を通じて共有します。「この会社でどこまで成長できるのか」「自分は将来どのポストで貢献できるのか」といった将来像が見えることで、社員の主体的な学習意欲が生まれます。実際にロードマップを PDFなどで文書化して全員に共有すれば、育成担当者だけでなくマネージャー層や当の社員自身も含め、組織全体で同じビジョンを持って取り組むことが可能です。将来のキャリア見通しを示すことは、人材の定着率向上にも直結する重要な要素です。 - パターン5:「育成=研修」と考えて現場での成長機会を軽視する
人材育成というと研修プログラムを実施することだと思い込み、日常業務の中での育成をおろそかにしているケースです。多くの企業がこの 「育成」と「研修」の混同 という勘違いに陥りがちで、研修はあくまで知識やスキルを教える場に過ぎず、真の人材育成は日々のOJTや現場での経験を通じて継続的に行われるものです。研修だけでは実務への定着が難しいため、トヨタやソニーなど人材育成で成功している企業は単発研修に頼らず日常業務に組み込まれた育成システムを構築しています。また「一律の研修さえしておけば良い」という姿勢では、社員一人ひとりの強み・弱みに向き合った真の成長は望めません。
対策:
70:20:10の法則が示すように(※70%は現場での経験学習、20%は他者からのフィードバック、10%が研修等の形式学習という経験則)、日常業務での挑戦課題や上司・先輩からの指導機会を十分に設けることが重要です。例えばジョブローテーションで様々な経験を積ませたり、ストレッチアサイン(敢えて少し難易度の高い職務を任せる)を行ったりして、研修外でも成長の場を提供しましょう。また、人事評価制度と育成計画を連動させることも見落とせません。評価と育成が切り離されていると社員の学習意欲は高まりませんが、育成目標の達成を評価や昇進に反映すれば「学べばきちんと報われる」という動機付けになります。マッキンゼーの調査によれば、評価と育成が連動している企業は人材の定着率が約40%高いとの報告もあります。研修+現場経験+公正な評価が一体となった環境を整備することで、社員の成長スピードとエンゲージメントは飛躍的に向上します。 - パターン6:計画しっぱなしで見直し・改善が行われない
立派な人材育成計画を作っても、その後のモニタリングや更新をせず放置してしまうケースです。環境変化や事業戦略の転換により、人材に求められるスキルや育成優先度は時間とともに変わります。計画策定時には想定しなかった課題が新たに発生することもあるでしょう。物事は基本的に計画通りには進まないものです。計画策定時点では最善と思われた育成施策も、実行段階で効果が上がらなかったり現場の負荷が高すぎたりする場合もあります。
対策:
計画は常にアップデート前提と考え、定期的な見直しの仕組みを設けましょう。少なくとも半年~1年に一度は育成計画の進捗を振り返り、目標達成状況をKPIで測定して、計画の修正・改善を行います。また「計画通りに進まない余裕(バッファ)をあらかじめ設けておく」ことも有効です。例えば5カ年計画であれば+半年~1年分の余裕期間を見込んでおくと、予期せぬ遅れが生じてもリカバリーできます。常に現場や受講者の声に耳を傾け、計画の仮説検証を行いながら柔軟に軌道修正することで、人材育成計画の精度と実効性は一段と高まるでしょう。
活用しやすいテンプレートとその使い方
ゼロから人材育成計画書を作成するのは大変ですが、テンプレートやフレームワークを活用すると効率的かつ抜け漏れのない計画策定が可能です。ここでは人事担当者に役立つテンプレートとその使い方を紹介します。
厚生労働省提供ツール
まず、人材育成計画を体系的に作るために厚生労働省が提供しているツールを活用する方法があります。代表的なものに「職業能力評価基準」と「キャリアマップ・職業能力評価シート」があります。
「職業能力評価基準」は各職業・職種ごとに必要な能力やスキルを定義し、仕事の内容や求められるスキル、成果に繋がる職務行動例などが網羅された指標です。これを使うことで各社員のスキルや知識の習得状況を見える化でき、育成計画の立案や進捗管理の助けとなります。
また「キャリアマップ・職業能力評価シート」は職業能力評価基準を簡易化したチェックリスト形式のシートで、職種ごと・レベルごとに必要な経験や知識を一覧できるようになっています。各職種で「どの時点で何ができるべきか」を明確に示したもので、このシートを使えば現状のスキルギャップを洗い出し、目標設定や研修計画の作成に役立てることができます。
例えば若手営業職に求められるスキルをレベル1~5で定義し、現在レベル2なら3に上げるにはどんな研修や経験が必要か、といった検討がしやすくなります。これら厚労省のツールは無料公開されており、自社の育成計画策定の下地資料として非常に有用です。
ツール
自社オリジナルの「人材育成計画書テンプレート」
次に、自社オリジナルの「人材育成計画書テンプレート」を用意しておく方法もあります。
表形式のテンプレートに沿って、育成計画の要素を埋め込んでいくことで計画を見える化できます。一般的な育成計画書の項目には、育成対象者(誰に)、育成内容・施策(何を)、目標(到達レベル)、現状(ギャップ)、スケジュール(いつまでに)、担当者、評価指標、課題・留意点などがあります。
実際のテンプレートでは「実施内容」「目標」「現状」「課題」等の欄が設けられており、例えば「新入社員研修」「○月までに基本業務を独力で遂行できるようにする」「現状:知識不足で先輩のフォローが必要」「課題:主体性を引き出す必要あり」…といった具合に記入していきます。
こうして計画を一枚のシートにまとめると、関係者間で共有しやすくなるのも利点です。人材育成ロードマップ自体をPDFなどにまとめて社内チャットで共有すれば、経営層から現場の上司、育成担当者、そして育成される本人までが共通認識を持つことができます。
テンプレートはExcelやPowerPoint形式で提供されているものも多く、自社のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。ぜひ使いやすいフォーマットを活用し、計画策定の第一歩としてください。
まとめ:育成成果につながる実践的な設計へ
人材育成は一朝一夕には成果が出ませんが、その成否の大半は計画の段階で決まると言っても過言ではありません。最初に現状と目標をしっかり見定め、経営戦略とリンクした質の高い育成計画・ロードマップを策定することで、研修やOJTなど個々の施策が生きてきます。
逆に計画が不十分なまま走り出してしまうと、どんなに豪華な研修を実施しても期待する効果は得られないでしょう。
本記事で解説したステップに沿って計画を立案し、定期的な見直し・改善を行っていけば、計画倒れを防ぎ「絵に描いた餅」ではない実践的な人材育成が可能になります。ロードマップによって社員一人ひとりが自身の成長ビジョンを描き、モチベーション高く日々の業務と学習に取り組むようになるでしょう。その結果、企業全体としての人材力が底上げされ、中長期的な競争力強化につながるはずです。
ぜひテンプレートやツールも活用しながら、自社に最適な人材育成計画を策定・運用してみてください。人材育成の成功は計画から始まる――綿密に練られた計画こそが、未来の成果を生み出す鍵となります。
音声動画
最後に今回の内容について、音声動画で振り返りです。
ガイド:Q&A
1. 人材育成の成否において、なぜ「計画」の段階が最も重要だとされていますか?
研修が失敗する原因の40%は計画段階にあると報告されており、計画の質が育成の成否を分けます。質の高い計画は、研修やOJTの効果を最大化し、従業員のスキル向上と企業成長を実現するための土台となるため、極めて重要です。
2. 「人材育成計画」と「人材育成ロードマップ」の主な違いを、時間的視点と目的の観点から説明してください。
「人材育成計画」は、特定のスキル習得に焦点を当てた短期的な計画です。一方、「人材育成ロードマップ」は3〜5年という中長期的な視点で、キャリア段階に応じた成長プロセス全体を設計するもので、企業の「羅針盤」としての役割を果たします。
3. 人材育成計画を立案する最初のステップである「現状把握」では、具体的に何を分析する必要がありますか?
まず自社の経営戦略やビジョンを確認し、目指すべき人材像を明確にします。次に、スキルマップなどのツールを用いて社員の現在のスキルや知識レベルを客観的に洗い出し、「理想」と「現実」のギャップ(スキルギャップ)を分析します。
4. 効果的な目標設定に用いられる「SMARTの原則」とは何か、その5つの要素を挙げてください。
SMARTの原則は、目標設定のフレームワークであり、その5つの要素は「Specific(具体的)」「Measurable(測定可能)」「Achievable(達成可能)」「Relevant(関連性)」「Time-bound(期限設定)」です。これにより、目標の進捗管理が容易になります。
5. 人材育成ロードマップを構成する「年間計画」「3カ年計画」「5年計画」は、それぞれどのような役割を担っていますか?
「5年計画」は経営ビジョンを反映した長期的な人材像を描き、「3カ年計画」は中期経営計画と連動して達成すべき目標とステップを定めます。そして「年間計画」は、それらを現場で実行に移すための具体的なアクションプランとしての役割を担います。
6. 研修が「形骸化」してしまう失敗パターンを防ぐためには、どのような対策が有効ですか?
研修内容を現場のニーズに即した実践的なものに見直すことが有効です。例えば、自社の業務課題に直結した演習やケーススタディを取り入れたり、研修後に現場での実践課題を与えて知識の定着を図ったりする工夫が挙げられます。
7. なぜ人材育成計画は、人事部だけでなく経営層を巻き込んで策定する必要があるのですか?
経営層を巻き込むことで、人材育成計画を企業の経営ビジョンや事業戦略と確実に連動させることができます。これにより、計画に一貫性と説得力が生まれ、全社的な協力も得やすくなり、計画が机上の空論になるのを防ぎます。
8. 社員に対して明確なキャリアパスを示せない場合、企業はどのようなリスクに直面しますか?
社員が自社での将来像を描けず、モチベーションの低下を招きます。特に、将来性を求める優秀な若手人材は「キャリアの将来性への不安」を理由に離職しやすく、人材流出のリスクが高まります。
9. 「育成=研修」という考え方が失敗につながる理由と、その対策として推奨されているアプローチを説明してください。
人の成長の70%は現場での経験から得られるため、研修のみに頼る育成は効果が限定的です。対策として、OJTやストレッチアサイン(少し難易度の高い職務を任せる)といった日常業務での成長機会を意図的に設け、評価制度と育成を連動させることが推奨されます。
10. 厚生労働省が提供している、人材育成計画の策定に活用できるツールを2つ挙げ、それぞれの特徴を説明してください。
「職業能力評価基準」と「キャリアマップ・職業能力評価シート」があります。前者は職種ごとに必要な能力を網羅的に定義した指標で、後者はそれを簡易化したチェックリスト形式のシートであり、スキルギャップの分析や目標設定に役立ちます。
用語集
| 用語 | 定義 |
| 360度評価 | 上司だけでなく、同僚や部下など複数の視点から評価を行う手法。より公平で正確な現状把握に役立つ。 |
| 70:20:10の法則 | 人の成長の70%は現場での経験学習、20%は他者からのフィードバック、10%が研修等の形式学習によってもたらされるという経験則。 |
| OJT | On-the-Job Trainingの略。日常業務を通じて行われる実践的な教育訓練。 |
| Off-JT | Off-the-Job Trainingの略。職場を離れて行われる研修やセミナーなどの教育訓練。 |
| PDCAサイクル | 計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクルを回すことで、継続的に業務を改善していく手法。 |
| SMARTの原則 | 目標設定のフレームワーク。具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限設定(Time-bound)の頭文字。 |
| アクションプラン | 目標達成のための具体的な行動計画。年間計画は中期ロードマップを実行に移すためのアクションプランと位置づけられる。 |
| 育成KPI | Key Performance Indicatorの略。人材育成の進捗や成果を測定するための重要業績評価指標。例:資格取得者数、昇進率、定着率など。 |
| キャリアマップ・職業能力評価シート | 厚生労働省が提供するツール。職種ごと・レベルごとに必要な経験や知識を一覧にしたチェックリスト形式のシートで、スキルギャップの洗い出しに役立つ。 |
| 形骸化(けいがいか) | 実質的な意味や内容を失い、形式だけが残ること。人材育成においては、研修が単なるイベントで終わってしまう状態を指す。 |
| スキルギャップ | 企業が目指す理想の人材像に必要なスキルと、従業員が現在保有しているスキルの差。 |
| ストレッチアサイン | 従業員の能力よりも少し難易度の高い職務を意図的に任せること。成長を促すための手法。 |
| 職業能力評価基準 | 厚生労働省が提供するツール。各職業・職種ごとに必要な能力やスキルを網羅的に定義した指標。 |
| 人材育成計画 | 組織の成長戦略に対応するために必要な人材を「いつ」「何人」「どのように」育成するかを具体的に定めた計画。 |
| 人材育成ロードマップ | 3〜5年スパンの中長期的視点で、キャリア段階に応じた成長プロセス全体を設計したもの。総合的な人材成長のための「羅針盤」となる。 |

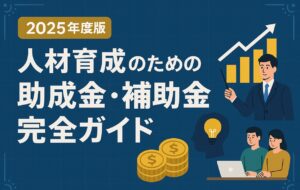




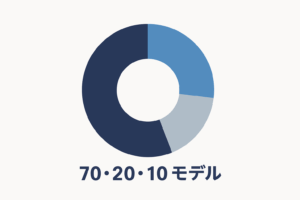
コメント