導入:よくある悩みと人材育成の重要性
新人を採用して研修してもすぐ辞めてしまう、研修の効果が見えず現場で活かされていない、忙しくて人材育成に時間を割けない――。
人材育成担当者や管理職の方なら、こうした悩みに心当たりがあるのではないでしょうか?
実際、企業の人材育成には共通する課題が多く存在し、若手社員の早期離職や将来の幹部候補の育成、人事評価制度の見直しなど数えきれないほどの問題点が指摘されています。人材は企業にとって「財産」であり、社員の成長なくして企業の成長はありません。それだけに、人材育成を成功させることは企業の競争力向上に直結する重要課題なのです。
しかし、人材育成の重要性は理解していても、具体的に何が問題となっているのか整理できていないケースも少なくありません。また、課題は把握していても「どう解決すればいいのか」が分からず、一歩を踏み出せない現場も多いでしょう。
本記事では、企業規模や業種を問わず直面しがちな人材育成の「10大課題」を網羅的に取り上げ、それぞれに対する具体的な解決策と成功事例を紹介します。実名企業の事例から得られた知見や、専門調査のデータも交えながら、課題解決の糸口を探っていきましょう。
動画簡易解説
人材育成の10大課題:まずは全体像を把握
次世代リーダーの不足や優秀人材の採用難といった外部要因に加え、若手社員の定着率低下やOJTの機能不全など社内の育成環境に関わる問題も上位に挙がっています。
これらを踏まえ、本記事では以下の10項目を人材育成の「10大課題」として取り上げます。
- 若手社員の定着率が低い
– 新人や若手が早期に離職してしまい、人材が定着しない問題。 - 人材育成に割くリソース(時間・予算)の不足
– 日常業務が忙しく教育の時間が取れない、研修予算が足りない等のリソース制約。 - 育成担当者・現場指導者のスキル不足
– 人材育成のノウハウを持つ専門人材がいない、または現場のOJT指導者に指導スキルが不足している。 - 体系的な研修制度・計画の未整備
– 育成方針やカリキュラムが体系立てられておらず、場当たり的な研修に留まっている。 - OJTの形骸化・機能不全
– 単に現場任せになりOJTが形式化している、計画的なスキル伝承ができていない。 - 教育効果の測定・評価ができていない
– 研修後の効果検証や学習定着度の評価指標がなく、育成施策の改善につながらない。 - 経営戦略との不整合・経営層のコミット不足
– 人材育成の目的が経営目標と紐づいておらず、経営陣の理解や支援が十分でない。 - 従業員の学習意欲低下・教育の定着文化不足
– 受け身の研修参加が多く、自発的に学ぶ風土が醸成されていない。 - デジタル化・DX時代への対応遅れ
– オンライン研修の環境整備が不十分、DX・ITスキル育成に追いつけていない。 - 次世代リーダー・管理職層の育成停滞
– 将来の幹部候補や管理職人材が育たず、世代交代や組織力強化に不安が残る。
課題ごとの詳細と成功事例
それでは、上で挙げた課題それぞれについて、具体的な状況と解決のポイント、さらに実際の成功事例を見ていきましょう。
課題1:若手社員の定着率が低い
課題の詳細
新人や若手社員が早期に離職してしまい、人材が定着しない問題です。厚生労働省の調査によれば、新卒入社3年以内の離職率は3割を超えており、看護など専門職の世界でも育成途上で人材が流出するケースが報告されています。定着率が低い職場では、経験が蓄積されず常に人手不足になります。
先輩から後輩への技能継承が滞り、計画的な人材育成も困難です。その結果、現場の負担が増えて新人がさらに定着しないという悪循環に陥ります。
解決策・成功事例
根本原因に目を向け、若手が「この会社で成長できる」と実感できる環境づくりが鍵です。
例えば、ヤフー株式会社では上司と部下が定期的に対話する「1on1ミーティング」を導入し、若手が抱える悩みや目標をこまめに共有できる場を設けています。これにより不安や不満の早期解消につながり、離職防止に効果を上げています。
また、スターバックスではアルバイトを含む全従業員に企業理念やミッションを徹底教育し、短期間で現場戦力化する仕組みを整えています。こうした取り組みによって組織へのエンゲージメントが高まり、結果的に定着率向上につながることが期待できます。
課題2:人材育成に割くリソース(時間・予算)の不足
課題の詳細
教育に充てる時間やコストが確保できない問題です。特に従業員数の少ない企業では「日々の業務が忙しく、人材育成が後回しになる」傾向があります。その結果、研修の計画が立てられず場当たり的になったり、必要な研修を実施できずに課題が先送りされがちです。
また、研修費用を捻出できず外部セミナーや講師を呼べないため、教育の機会そのものが不足するケースもあります。こうしたリソース不足は、人材育成の重要性は理解しながらも実践に移せないジレンマを生みます。
解決策・成功事例
ポイントは、経営層が育成を優先事項として位置づけ、業務設計を見直すことです。例えば繁忙期と閑散期でメリハリをつけて研修日を確保したり、ルーチン業務を外部委託して社員の学習時間を捻出する工夫が考えられます。
実際に、ある企業では社内に講師役となる人材が不足していたため、eラーニングシステムを導入して基礎研修をオンライン化しました。その結果、「基本的なビジネスマナーを学べる場が欲しい」という若手社員の要望に応え、全社員が積極的にオンライン研修を受講するようになったという成功事例があります。
このようにデジタル教材の活用や短時間でできるマイクロラーニングを組み合わせれば、限られた時間・予算内でも継続的な人材育成を実現できるでしょう。
課題3:育成担当者・現場指導者のスキル不足
課題の詳細
人材育成の担い手となる人材やノウハウが不足している問題です。専門の教育担当者が社内におらず、人事部や現場管理職が手探りで育成を行っているケースも多々あります。また、OJTで新人を指導する現場リーダー自身が教え方を学んでおらず、育成が属人的・偶発的になりがちです。
実際、ある調査では半数以上の企業が「OJTのレベルアップ」が課題だと回答しています。育成ノウハウが社内に蓄積されていないと、「自分が苦労して身に付けた経験を頼りに部下を育てるしかない」状態に陥りかねません。
解決策・成功事例
この課題への対策は、育成するための教育を行うことです。具体的には、現場指導者向けにコーチングやOJT手法の研修を提供し、「教えるスキル」を育てることが重要です。
古河電気工業では、新人教育と次世代リーダー育成を両立させる目的で「OJTリーダー制度」を導入しました。選抜された社員を育成担当リーダーと位置づけ、研修を通じて指導スキルを身につけさせています。その結果、育成する側・される側の双方がスキルアップできる仕組みを実現しています。
また他社の事例や外部セミナーから学んだ育成手法を自社用にドキュメント化し、ナレッジ共有することも効果的です。育成担当者の底上げが、人材育成全体の底上げにつながります。
課題4:体系的な研修制度・計画の未整備
課題の詳細
社内に人材育成の体系や計画が整っておらず、行き当たりばったりの研修になっている問題です。新人研修は行うものの、その後の継続教育や中堅・管理職向けの研修が無い、といったケースも少なくありません。計画や仕組みが確立されていないと、人材育成を進めても途中で効果を検証できず、手応えがないまま進行してしまいます。
実際、約半数の企業が自社の教育計画を見直す必要性を感じているとの調査結果もあります。裏を返せば、体系立ったプログラムなしに成果を上げ続けることは難しいと言えるでしょう。
解決策・成功事例
まず人材育成の目的と全体計画を明確化することが出発点です。企業として「どのような人材をいつまでに育成したいのか」というビジョンを設定し、それを達成するための研修カリキュラムや評価指標を設計します。
例えば、小田急電鉄では職種や階層別に細かく研修体系を整え、社員研修センターを設置して現場職向けの専門教育まで包括的に実施しています。
また、ニトリホールディングスでは社内に「ニトリ大学」を設立し、グローバルに活躍できるスペシャリスト育成を目指した体系的プログラムを展開しています。従業員が自らキャリアプランを定期的に策定する仕組みも導入しており、一人ひとりの成長ロードマップと企業の育成計画を連動させています。
このように、組織ニーズと個人キャリアを織り交ぜた育成のロードマップを描くことで、人材育成の抜本的な強化が可能になります。
課題5:OJTの形骸化・機能不全
課題の詳細
本来、職場での実地研修(OJT)は新人にとって貴重な学習機会ですが、計画や仕組みがないまま現場任せにすると形骸化しがちです。新人は先輩について仕事を覚えますが、先輩ごとに教え方が異なり内容にばらつきが出る、忙しさのあまり「仕事を見て覚えろ」になってしまう、といった問題が起こります。
その結果、重要な知識やスキルが十分に伝わらず、習得できる内容も担当業務の範囲に限られてしまいます。またOJTだけに依存して計画的なOff-JT研修を併用しない場合、体系だった教育がなされないままとなるリスクもあります。
解決策・成功事例
OJTを制度化し標準化することが有効です。具体的には、OJT担当者を正式に任命して育成計画書を作成する、進捗を人事部とも共有してフォローする、といった仕組みを整えます。また、OJTで補いにくい知識は集合研修やeラーニングで補完し、OJTとOff-JTを組み合わせることが重要です。
例えば、スターバックスコーヒーではアルバイトも含めてOJT教育に注力し、企業理念や歴史に基づく統一されたプログラムを短期間で実施しています。店舗スタッフ同士で自社の価値観について議論するワークショップも組み込まれており、現場全体で考え方を共有する仕掛けづくりに成功しています。
このように、内容と手順をあらかじめ設計した「教える仕組み」を用意することで、属人的になりがちなOJTを組織的な人材育成ツールへと高めることが可能です。
課題6:教育効果の測定・評価ができていない
課題の詳細
研修や学習施策を実施しても、その効果を測定する仕組みがないために改善につながらない問題です。研修参加者の満足度アンケート程度は行っても、業務成績の向上やスキル定着度を数値で捉えていない企業は少なくありません。
評価指標がなければ、「研修をやりっぱなし」で終わってしまい、経営層にとって人材育成はコストに見えてしまう恐れもあります。実際には育成にもPDCAサイクルが必要であり、途中過程で成果を測る指標や目標値を設定しておくことが重要です。
解決策・成功事例
研修前後で測定可能なKPIを設けることが第一歩です。
例えば研修テストの得点、資格試験の合格率、研修後3ヶ月の業績指標変化(売上やエラー減少率など)を追跡するなど、定量データを集めて効果を検証します。また、LMS(学習管理システム)を活用すれば、一人ひとりが「何を」「どれだけ」学習したかを詳細に記録できます。
ある企業では、eラーニング上でテスト機能や視聴履歴をレポートで可視化し、誰がどのコンテンツを何回受講したかまで把握できるようにしました。これにより各社員の弱点分析が可能となり、研修内容の改善にも役立てています。定性的な面でも、上司との面談で研修の学びをどう実践したか振り返りを促す仕組みを取り入れるなど、多面的に効果検証することで人材育成の投資対効果を最大化できるでしょう。
課題7:経営戦略との不整合・経営層のコミット不足
課題の詳細
人材育成の方針が企業の経営戦略やビジョンと結びついていない問題です。本来、人材育成は経営戦略の一部として位置づけられるべきですが、「とりあえず現場の必要に応じて研修をやっている」程度で終わっているケースもあります。経営トップが人材育成に関心を示さず、人事部任せになっている組織では、研修内容が企業の将来的な方向性とズレてしまいがちです。
実際、約半数の企業が自社の人材育成ビジョン策定に「取り組めていない」と回答しており、経営戦略・人事制度・育成ビジョンの連動が喫緊の課題だとされています。この不整合は、社員にも「何のために勉強するのか」が伝わらず、モチベーション低下の一因ともなります。
解決策・成功事例
経営層が人材育成に本気で向き合い、ビジョンを示すことが不可欠です。自社の経営目標を支える人材像を定義し、「なぜ育成が必要か」を全社に発信します。その上で、従業員一人ひとりのキャリア目標と会社のビジョンを結び付けるアプローチが有効です。
例えば、北上信用金庫では「地域に密着して寄り添える人材の育成」を目的に掲げ、研修で信用金庫の歴史や職員としての心構えを教えるとともに、若手職員には通信講座や書籍購入費の補助を行うなど、経営方針に沿った育成支援を徹底しています。
経営トップ自ら育成方針を示し支援策を講じることで、社員は自分の成長が会社の発展と直結していると実感でき、学習意欲の向上やエンゲージメント強化に繋がります。
課題8:従業員の学習意欲低下・教育の定着文化不足
課題の詳細
研修を実施しても受講者が消極的で、学んだ内容が現場に活かされない問題です。受け身で研修を「受けさせられている」状態では、知識は定着しづらく、せっかくの教育投資も無駄になってしまいます。自主的に学ぶ社員が少なく、社内にナレッジを共有・蓄積する文化が育っていない組織では、変化への対応力も弱くなります。
事実、約6割もの企業が「自発的に学ぶ風土づくり」が課題だと感じているとの調査があります。こうした学習マインドの低下は、人材育成の成果を半減させる大きな障壁です。
解決策・成功事例
心理的安全性の高い学習文化を醸成することが重要です。社員が互いに教え合い学び合えるよう、失敗や質問を許容し、挑戦を称賛する風土を作ります。
株式会社LIFULL(ライフル)では「失敗を積極的に讃える」文化を社内に浸透させることで、従業員のモチベーション向上に成功しました。経営層が「失敗は挑戦した結果であり、ほめられるべきもの」と定義していて、失敗を恐れない環境づくりを徹底しています。小さなミスも共有するなど、組織全体でコミュニケーションを取り、従業員のモチベーション向上に役立てています。
また従業員の声を基に作成した人事施策を実践するなど、従業員の声を積極的に取り入れています。こうした取り組みにより、社員が主体的にスキルアップに取り組み、組織全体の成長スピードが上がっていきます。
課題9:デジタル化・DX時代への対応遅れ
課題の詳細
急速に進むデジタル化に人材育成が追いついていない問題です。オンライン研修の環境整備が不十分でリモート下で研修が滞ったり、社内のDX推進に必要なデジタル人材が育たないといった課題が顕在化しています。実際、IT・DXが企業成長の鍵となる中で「DX人材を育成できていない」と回答した企業は過半数にも上りました。
またコロナ禍以降にオンライン研修が増加する一方、「受講者が真剣に取り組んでいるかどうかの確認が難しい」「通信環境、アクセス、機器などのトラブルが多い」といった声も多く、デジタル時代の人材育成には新たな課題が伴います。
解決策・成功事例
デジタル技術を積極的に活用した育成体制の構築が必要です。具体的には、eラーニングや社内ナレッジ共有ツールを導入して地理的・時間的制約を超えた学習環境を整備します。さらに、研修受講をKPIに組み込んだり、小テストや課題提出を組み合わせることで、オンラインでも参加度合いを把握できるようにします。
ある企業では、対面での集合研修が困難になる中で自社制作の動画研修を導入し、受講後に「いつまでに何ができるようになるか」を本人に記入させ上長にサインして提出する仕組みを運用しました。これにより、オンライン研修でも受講者の主体性と実践行動を引き出すことに成功しています。
加えて、DX時代に求められる新スキル習得の機会を社内公募制度や社内デジタル人材アカデミーの設立などによって提供し、継続的に社員のリスキリングを支援していくことも重要です。
課題10:次世代リーダー・管理職層の育成停滞
課題の詳細
将来の経営幹部や管理職となる人材が十分に育っていない問題です。ベテラン層の退職が進む一方で、その後継となる若手・中堅が社内に不足している企業は少なくありません。事実、人材開発の直面課題では「次世代リーダー層の人材不足」や「管理職の人材不足」が常に上位に挙げられています。
リーダー候補が育たないままでは、組織力の維持や事業継承に不安が生じ、中長期的な企業競争力にも影響します。また、女性管理職やグローバル人材の育成が進まず、リーダー層の多様性が確保できていないことも課題となっています。
解決策・成功事例
計画的な次世代リーダー育成プログラムを導入することが有効です。ハイポテンシャル人材を早期に見極め、ジョブローテーションやメンター制度で様々な経験を積ませることで、将来の幹部候補を計画的に育成します。
例えば、ソフトバンクグループでは新入社員研修だけでなく、30代・40代の中堅社員を対象に改めてキャリア研修を実施し、意欲ある社員に成長の機会を提供しています。これにより、中堅層の視野拡大やリスキリングを促し、次世代のリーダー候補を社内から生み出す狙いがあります。
また、社内公募によるチャレンジポストや、管理職候補者同士が切磋琢磨するリーダーシップ研修(アクションラーニング等)を実施している企業も多く、幹部人材を自前で育てる仕組みが重視されています。重要なのは、単発の昇格研修だけでなく、継続的にフォローアップしながらリーダー候補者を支援していく体制を構築することです。
解決策と実務上のポイント
人材育成上の課題を乗り越えるためには、上記の事例に共通するような基本ポイントを押さえておくことが重要です。以下に、現場で実践しやすい解決策の要点をリストアップします。
- 経営層による明確な育成方針と支援
会社として「どんな人材を育てたいか」を明文化し、トップ自らメッセージを発信します。経営層が研修計画の策定や評価に関与し、リソースをしっかり確保することで、全社的に人材育成を推進しやすくなります。 - 体系的な育成計画の策定
年間の研修スケジュールや各階層・職種ごとのカリキュラムをあらかじめ設計します。育成ゴールと達成時期を定め、ロードマップに沿って研修を配置することで、場当たり的な指導を避けて継続的な育成が可能になります。 - OJT・Off-JT・自己啓発の組み合わせ
職場での実践的指導(OJT)だけでなく、集合研修やオンライン講座(Off-JT)、従業員自ら学ぶ自己啓発もバランスよく取り入れます。例えば、日中はOJT中心で、定期的に外部セミナー受講やeラーニング受講期間を設けるなど、複数手法を組み合わせて相乗効果を狙います。 - 育成担当者・現場指導者への教育
部下を指導する管理職やOJT担当者に対して、コーチング研修や育成手法のトレーニングを実施します。「教えるスキル」を持った人材を増やすことで、組織全体の育成力を底上げできます。 - 学習を促す制度・文化づくり
社員が自主的に学び挑戦できるよう、制度面で後押しします。例として、資格取得支援制度、社内表彰(学習成果を称える)、週1回の社内勉強会開催などを導入し、学習することが評価される文化を醸成します。失敗を許容しナレッジ共有を促す風土づくりも欠かせません。 - テクノロジー活用と学習環境整備
LMS(学習管理システム)や社内SNS、動画教材などのデジタルツールを活用し、効率的で継続的な学習環境を提供します。また、テレワーク下でも学びやすいよう機材や通信環境を整えることも重要です。 - 成果測定とフィードバックサイクル
研修前後の指標を設定して効果を測定し、人材育成施策をPDCAで改善し続けます。研修後には上司や人事からフォローアップ面談を行い、学んだ内容の実践状況を確認・フィードバックすることで、定着率を高めます。
これらのポイントを実践することで、限られたリソースでも効果的な人材育成が可能となり、紹介した成功事例のような成果に近づけるでしょう。
成功企業に共通する成功の秘訣
実際に人材育成に成功している企業には、いくつか共通するポイントがあります。
その秘訣をまとめると、主に次の3点に集約されます。
- 育成の目的・計画が明確であること
何のために誰を育成するのかがはっきりしており、ゴールに向けた計画が社内で共有されています。目的が不明確なまま手探りで進めるのではなく、明確なビジョンと戦略に基づいて人材育成が実行されています。 - 従業員一人ひとりのキャリアデザインを支援していること
社員が自分のキャリア目標を描き、それを会社の目標と結びつける取り組みが行われています。従業員自身が将来像を明確にすることでモチベーションが高まり、会社もそれを後押しする制度(メンター面談やキャリア相談窓口など)を用意しています。 - 研修制度や職場環境など育成の仕組みが確立していること
社員がスキルアップし続けられるよう、研修制度や働きやすい制度が整っています。例えば、階層別研修や時短勤務制度、育児支援制度などを整備し、社員が成長とワークライフバランスを両立できる環境を作っています。その結果、社員のエンゲージメントが高まり、定着率や業績向上にも好影響を与えています。
以上のような要素が揃っている企業は、人材育成が好循環に乗りやすく、優秀な人材の確保・定着や生産性向上を実現できています。
まとめ:今すぐ始める改善アクション
以上、人材育成で直面しがちな10大課題とその解決策・成功事例を見てきました。自社にも当てはまる課題がいくつもあったのではないでしょうか。
人材育成の改善は一朝一夕にはいきませんが、今日からできる一歩を踏み出すことが重要です。最後に、今すぐ始められる具体的なアクションを3つ提案します。
- 自社の課題を見える化する
まず、現在どんな課題が存在しているのか棚卸ししてみましょう。本記事のリストをチェックし、自社の人材育成上の弱点(例:研修の効果が不明、計画がない、OJT任せになっている等)を書き出すことで、解決すべきポイントが明確になります。 - 経営層と育成の方向性を共有する
抽出した課題について、経営陣や上司と現状認識をすり合わせ、今後の人材育成のビジョンを議論します。経営層のコミットを取り付け、リソース配分や制度整備の協力を仰ぎましょう。トップの後押しがあれば、施策も進めやすくなります。 - 小さな施策から着手する
いきなり完璧な育成プログラムを作る必要はありません。まずはできる範囲で一つ施策を導入してみます。例えば、月1回の社員勉強会を開催する、試験的にeラーニング教材を配信してみる、若手にメンターをつける等、効果が測りやすいものから始めましょう。実施後はアンケートや成果を確認し、次の施策改善に活かします。
人材育成は、継続的な取り組みと改善によって確実に成果が積み上がっていきます。最初の一歩を踏み出せば、必ず道は開けます。ぜひ本記事の内容を参考に、できるところから人材育成改革に取り組んでみてください。
あなたの会社の人材育成が軌道に乗り、社員と組織が共に成長できることを心より応援しています。
音声動画解説
ガイド:Q&A
1. 若手社員の定着率が低いことは、企業にとってどのような悪循環を生み出しますか?
若手社員の早期離職は、経験が蓄積されず常に人手不足の状態を引き起こします。これにより、先輩から後輩への技能継承が滞り、現場の負担が増加することで、さらに新人が定着しにくくなるという悪循環に陥ります。
2. 人材育成にリソース(時間・予算)が不足している場合、どのような解決策が考えられますか?
解決策として、経営層が育成を優先事項と位置づけ、業務設計を見直すことが挙げられます。具体的には、eラーニングシステムを導入して研修をオンライン化したり、マイクロラーニングを活用したりすることで、限られた時間や予算内でも継続的な育成が可能になります。
3. 現場の指導者スキルが不足している問題に対し、古河電気工業ではどのような制度を導入して解決を図りましたか?
古河電気工業では、新人教育と次世代リーダー育成を両立させるために「OJTリーダー制度」を導入しました。選抜された社員を育成担当リーダーとし、研修を通じて指導スキルを身につけさせることで、育成する側とされる側の双方がスキルアップできる仕組みを実現しています。
4. 場当たり的な研修に陥る「体系的な研修制度・計画の未整備」という課題を解決するための出発点は何ですか?
出発点は、人材育成の目的と全体計画を明確化することです。企業として「どのような人材をいつまでに育成したいのか」というビジョンを設定し、それを達成するための研修カリキュラムや評価指標を設計することが求められます。
5. OJT(On-the-Job Training)が形骸化するのを防ぎ、組織的な育成ツールとして機能させるためには、どのような取り組みが有効ですか?
OJTを制度化・標準化することが有効です。具体的には、OJT担当者を正式に任命して育成計画書を作成し、その進捗を人事部と共有する仕組みを整えます。また、OJTとOff-JT(集合研修やeラーニング)を組み合わせ、相互に補完させることが重要です。
6. 研修の効果を測定・評価しないと、どのような問題が生じますか?また、その具体的な測定方法を一つ挙げてください。
研修の効果を測定しないと、「研修をやりっぱなし」で終わってしまい、施策の改善につながりません。その結果、経営層からは人材育成がコストと見なされてしまう恐れがあります。具体的な測定方法として、研修前後のテスト得点や資格試験の合格率、業績指標の変化などを追跡することが挙げられます。
7. 人材育成の方針が経営戦略と結びついていない場合、社員にどのような影響を与えますか?
人材育成と経営戦略が不整合であると、社員に「何のために勉強するのか」という目的が伝わりません。これにより、学習へのモチベーションが低下し、エンゲージメントの強化を妨げる一因となります。
8. 従業員の学習意欲の低下という課題に対し、株式会社LIFULL(ライフル)はどのような文化を醸成することで対応しましたか?
株式会社LIFULLは、「失敗を積極的に讃える」文化を社内に浸透させました。失敗は挑戦した結果であり、ほめられるべきものと経営層が定義することで、従業員が失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性の高い学習文化を醸成しています。
9. DX(デジタルトランスフォーメーション)時代において、人材育成が直面している新たな課題とは何ですか?
DX時代における課題として、オンライン研修の環境整備が不十分であることや、社内のDX推進に必要なデジタル人材が育っていないことが挙げられます。また、オンライン研修では受講者の集中度合いの確認が難しいことや、通信環境のトラブルなども新たな問題となっています。
10. 次世代リーダーの育成が停滞している問題に対し、ソフトバンクグループはどのような研修機会を提供していますか?
ソフトバンクグループでは、新入社員だけでなく30代・40代の中堅社員を対象にしたキャリア研修を実施しています。これにより、中堅層の視野拡大やリスキリングを促し、意欲ある社員に成長の機会を提供することで、次世代のリーダー候補を社内から生み出すことを目指しています。
用語集
| 用語 | 定義 |
| 人材育成 | 企業の「財産」である社員を成長させること。企業の競争力向上に直結する重要課題。 |
| OJT (On-the-Job Training) | 職場での実地研修。計画や仕組みがないまま現場任せにすると形骸化するリスクがある。 |
| Off-JT (Off-the-Job Training) | 職場を離れて行われる研修。集合研修やオンライン講座などが含まれ、OJTを補完する役割を持つ。 |
| 1on1ミーティング | 上司と部下が定期的に対話する場。若手が抱える悩みや目標をこまめに共有し、不安や不満の早期解消につなげる。(ヤフー株式会社の事例) |
| eラーニング | デジタル教材を活用したオンライン学習システム。時間や場所の制約を受けずに学習機会を提供できる。 |
| マイクロラーニング | 短時間で完結する学習コンテンツ。限られた時間内でも継続的な人材育成を実現する手法の一つ。 |
| コーチング | 指導対象者の自発的な思考や行動を促すコミュニケーション技術。現場指導者の「教えるスキル」を向上させるために用いられる。 |
| PDCAサイクル | Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)のサイクル。人材育成施策の効果を測定し、継続的に改善するために必要。 |
| LMS (学習管理システム) | Learning Management Systemの略。個々の学習履歴や進捗を詳細に記録・管理できるシステムで、効果測定や弱点分析に活用される。 |
| エンゲージメント | 従業員の組織に対する愛着や貢献意欲。企業理念の教育などを通じて高めることができ、定着率向上につながる。 |
| リスキリング | 従業員がDX時代に求められる新しいスキルを習得すること。継続的な支援が重要とされる。 |
| アクションラーニング | 参加者がグループで現実の課題に取り組み、解決策を探る過程でリーダーシップなどを学ぶ研修手法。 |
| ハイポテンシャル人材 | 高い潜在能力を持つ人材。早期に見極め、ジョブローテーションなどで計画的に育成することが次世代リーダー育成につながる。 |
| 心理的安全性 | 組織内で、誰もが安心して自分の意見を言えたり、失敗を恐れずに挑戦できたりする状態。学習文化の醸成に不可欠。 |
| DX (デジタルトランスフォーメーション) | デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織を変革すること。DX時代への対応は人材育成の大きな課題となっている。 |

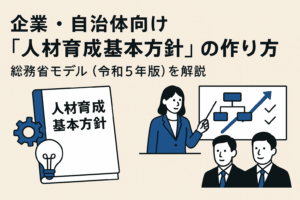
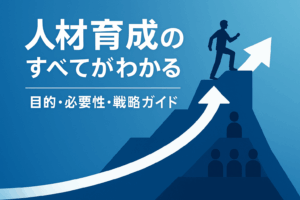
コメント