要旨
日本政府は、企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、従来の「ローリスク・ローリターン」経営から脱却し、適切なリスクテイクを伴う「攻めの経営」への転換を推進しています。
この改革の中心的な手段として、役員報酬制度の見直しが位置づけられています。欧米企業と比較して固定報酬の割合が高く、業績連動報酬や株式報酬の導入が遅れている日本企業の現状に対し、本手引書は経営陣に株主と利害を共有させ、中長期的な成長へのインセンティブを付与するための具体的な指針を提示しています。
近年の会社法改正(役員への株式の無償発行を可能化)や税制改正(損金算入要件の明確化・拡充)により、企業が多様なインセンティブプランを導入しやすい環境が整備されました。本手引書は、これらの法的・税制上の枠組みを詳説するとともに、コーポレートガバナンス・コードやCGSガイドラインの趣旨を踏まえ、形式的な制度対応に留まらず、各社の経営戦略と連動した実効性のある報酬制度の設計・運用を強く求めています。
関連資料
動画簡易解説(約:約7分)
1. 背景:コーポレートガバナンス改革と役員報酬の重要性
1.1. 政府方針:「攻めの経営」への転換
日本政府は、企業の「稼ぐ力」を向上させるため、一連の経済政策を通じてコーポレートガバナンス改革を推進してききました。2014年の「日本再興戦略」以降、「未来投資戦略」に至るまで、持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進、会社法改正、コーポレートガバナンス・コードの策定・改訂などが一貫して進められてきました。
これらの施策の根底にあるのは、日本企業を「攻めの経営」へと転換させるという強い意志です。特に、経営陣に中長期的な企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与する仕組みとして、株式報酬や業績連動報酬の柔軟な活用が不可欠とされています。
主な政府戦略における言及
- 日本再興戦略:改訂2015
CEOの選解任プロセスやインセンティブ報酬の導入に関する指針・事例集の策定を方針として掲げた。 - 日本再興戦略2016
業績連動報酬を含む経営陣への適切なインセンティブ付けが不十分であるとの課題認識を示し、インセンティブ報酬の導入・開示状況の分析・公表を打ち出した。 - 未来投資戦略2017・2018
コーポレートガバナンス改革を「形式」から「実質」へと深化させる必要性を強調した。
1.2. 日本企業の報酬体系の現状と課題
日本企業の役員報酬は、欧米主要国と比較していくつかの構造的な課題を抱えています。
報酬水準と構成比の国際比較
2022年度の売上高1兆円以上の企業におけるCEO報酬の比較では、日本の報酬水準が欧米に比べて低いだけでなく、固定報酬の割合が高いことが示されています。
| 国 | 固定報酬比率 | 変動報酬比率 |
|---|---|---|
| 日本 | 36% | 64% |
| フランス | 25% | 75% |
| ドイツ | 27% | 73% |
| 英国 | 22% | 78% |
| 米国 | 9% | 91% |
出典:ウイリス・タワーズワトソン 『日米欧CEO報酬比較(2022年調査結果)』
変動報酬比率が米国で91%に達するのに対し、日本は64%に留まっており、経営者のリスクテイクを促すインセンティブが相対的に弱い構造となっています。
業績連動指標の傾向
2017年の経済産業省の調査によると、業績連動報酬を導入している企業においても、その評価指標は短期的なものに偏る傾向があります。
- 短期(年度)の業績連動報酬を導入している企業:61%(主な指標:連結売上高、経常利益など)
- 中期(3年程度)の業績連動報酬を導入している企業:14%(主な指標:資本効率指標(ROE、ROIC)、株主還元指標(TSR)など)
この短期志向は、中長期的な企業価値向上への動機付けとしては不十分であると指摘されています。
機関投資家の視点
国内外の機関投資家は、日本企業の役員報酬制度に対して以下のような懸念を表明しています。
- 「現状、我が国企業においては中長期の業績連動報酬を導入している企業が少なく、業績向上のインセンティブが十分働いていない。」
- 「日本では経営者が自社株を持っていない。欧米では極めて一般的である株式保有ガイドラインでは、例えばCEOは在任中には年間基本報酬の3~5倍相当の株式を継続保有することを求めている。」
- 「経営者に中長期的な成長を志向するよう促すには、自社株をどれだけ保有させるかが、重要なポイント。大量の株を持っている経営者なら、中長期的に企業価値が下落するような施策は取りにくい。」
これらの声は、経営陣と株主の利害を一致させるための手段として、特に株式報酬の導入拡大が強く求められていることを示しています。
2. 株式報酬・業績連動報酬導入の意義と種類
2.1. 導入の目的
株式報酬や業績連動報酬の導入促進は、以下の効果をもたらすことを目的としています。
- 中長期的インセンティブの付与: 経営者に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与え、企業の「稼ぐ力」の向上に繋げる。
- 株主目線の経営促進: 経営陣が自社株を保有することで、株主と同じ視点での経営判断を促す。
- 人材のリテンション: 一定期間の譲渡制限を設けることで、優秀な人材の引き留め(リテンション効果)を図る。
- 投資家からの評価向上: グローバルな機関投資家の要望に応え、ガバナンス評価を高める。
2.2. 主な報酬制度の種類
インセンティブ報酬には多様な設計があり、目的や企業の状況に応じて選択されます。
| 報酬分類 | 制度名 | 概要 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬(現物株式) | 事前交付型リストリクテッド・ストック | 一定期間の譲渡制限が付された現物株式を事前に交付。 | リテンション、株価向上インセンティブ |
| 事後交付型リストリクテッド・ストック | 勤務条件等に応じて、事後に現物株式を交付。 | リテンション、株価向上インセンティブ | |
| パフォーマンス・シェア (PS) | 中長期の業績目標の達成度合いに応じて、事後に現物株式を交付。 | 業績向上・株価向上インセンティブ | |
| ストックオプション (SO) | あらかじめ定められた価格で自社株を購入する権利を付与。 | 株価向上インセンティブ | |
| 株式交付信託 | 信託を通じて株式を取得し、一定期間後に役員に交付する仕組み。PSやRSの設計が可能。 | 設計の柔軟性 | |
| 金銭報酬(キャッシュ) | パフォーマンス・キャッシュ | 中長期の業績目標の達成度合いに応じて、金銭を交付。 | 業績向上インセンティブ |
| ファントム・ストック | 仮想的に株式を付与し、一定期間後の株価相当の現金を交付。 | 株価向上インセンティブ | |
| SAR (Stock Appreciation Right) | 株価が予め定めた価格を上回った場合、その差額を金銭で交付。 | 株価向上インセンティブ |
3. 制度導入のための法的・税制上の整備
株式報酬制度の導入を促進するため、法的・税制上の環境整備が進められてきました。
3.1. 会社法上の整備
• 歴史的背景
2019年の会社法改正以前は、無償での株式発行や労務出資(役務提供を対価とする株式発行)が認められていなかったため、役員に直接株式を報酬として交付することが困難でした。そのため、金銭報酬債権を現物出資する(デット・エクイティ・スワップ)手法が用いられていました。
• 2019年会社法改正
上場会社が取締役又は執行役に対し報酬として株式を発行する場合に限り、金銭の払込み等を要しない「無償発行」が可能となりました(改正会社法第202条の2)。これにより、株式報酬導入の手続きが大幅に簡素化されました。
• 報酬決定方針の義務化
一定の上場会社等に対し、取締役会で取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めることが義務付けられました(同法第361条第7項)。これにより、報酬決定プロセスの透明性向上が図られています。
3.2. 税制上の損金算入要件
法人税法上、役員給与は原則として損金不算入だが、以下の3つの類型に該当する場合に限り、損金算入が認められます。
- 定期同額給与 (法人税法第34条第1項第1号)
1ヶ月以下の一定期間ごとに同額で支給される給与。 - 事前確定届出給与 (同項第2号)
・事前に税務署へ届け出た内容に従い、所定の時期に確定額の金銭または確定数の株式等を支給する給与。
・特定譲渡制限付株式(RS)事後交付型リストリクテッド・ストックなどがこの類型に該当しうる。
※一定の要件を満たす特定譲渡制限付株式等については届出が不要となる特例がある。 - 業績連動給与 (同項第3号)
・業績に連動して支給される給与で、パフォーマンス・シェアなどが該当する。損金算入には以下の厳格な要件を満たす必要がある。
・対象会社: 非同族会社、または非同族会社による完全支配関係がある同族会社。
・算定指標: 有価証券報告書に記載される客観的な指標(利益、株価、売上高など)を基礎とすること
・プロセス:
▪ 算定方法が、構成員の過半数が独立社外取締役である報酬委員会の決定など、適正な手続きにより決定されていること。
▪ 算定方法が有価証券報告書等で開示されていること。
・交付時期: 業績指標確定後、一定期間内(金銭は1ヶ月、株式は2ヶ月)に交付又は交付見込みであること。
平成29年度税制改正により、従来は損金算入が難しかった報酬類型(事後交付型RS、パフォーマンス・シェア等)も、これらの要件を満たすことで損金算入が可能となり、制度設計の自由度が高まりました。
4. CGSガイドラインと実務上の指針
経済産業省の「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」は、ガバナンス改革を形式的なものに終わらせず、企業価値向上に結びつけるための具体的な考え方を示しています。
4.1. ガバナンス改革の実質化
- 課題解決志向
ガバナンス改革は、事業ポートフォリオの見直し、意思決定の迅速化、将来の経営戦略の議論といった各企業が抱える具体的な課題を解決する観点から取り組むべきである。 - 取締役会の機能強化
取締役会は個別業務の執行決定から、中長期の経営戦略やCEO後継者計画の審議・策定といった監督機能に重点を移すべきである。 - 社外取締役の資質重視
社外取締役は「数合わせ」ではなく、経営経験者など、企業に必要な資質・役割を明確にした上で人選すべきである。 - 指名・報酬プロセスの客観化
社外者中心の指名・報酬委員会を設置・活用し、CEO・経営陣の選解任や評価、報酬に関する基準・プロセスを明確化すべきである。委員会の過半数を社外取締役とすることが望ましい。
4.2. 報酬設計の在り方
- 経営戦略との連動
報酬体系は、まず経営戦略ありきで検討されるべきである。経営戦略からKPIを設定し、その実現を促すインセンティブとして報酬を設計するというストーリー性が重要である。 - グローバルな視点
報酬水準や構成は、グローバルな競合他社をベンチマークとして勘案し、海外の優れた経営人材を確保できる水準を目指すべきである。 - 長期インセンティブの比率
グローバル展開が進む企業では、CEOの長期インセンティブ報酬の比率をグローバル水準である40~50%程度とすることも考えられる。 - 積極的な情報開示
業績連動報酬や自社株報酬の内容、非財務指標を用いる場合はその選択理由などを積極的に開示し、株主の理解を得ることが期待される。
4.3. 従業員への株式報酬
CGSガイドラインでは、将来の幹部候補人材の育成・エンゲージメント向上の観点から、従業員への株式報酬の活用も有益であると指摘しています。
- 導入の意義
従業員に対し自社株報酬を付与することは、企業価値や株価への意識を高め、エンゲージメントを向上させる効果が期待できる。また、譲渡制限を付すことで優秀な人材のリテンションにも繋がる。 - 労働基準法との関係
従業員への株式報酬は「賃金通貨払いの原則」に抵触するかが論点となる。しかし、以下の3要件を全て満たす場合は、賃金ではなく「福利厚生」と解釈でき、原則に抵触しないと考えられる。
1. 通貨による賃金等を減額することなく付加的に付与されること
2. 労働契約や就業規則で賃金として支給されるとされていないこと
3. 労働の対償全体の中で、通貨による賃金等が主たるものであること
5. Q&Aハイライト:実務上の重要論点
手引書のQ&Aセクションでは、制度導入における実務的な論点が詳細に解説されている。
株式報酬の選択肢
事前に株式を交付する「事前交付型」(リテンション効果が高い)と、事後に交付する「事後交付型」(業績連動させやすい)があり、目的応じて選択する。
税務上の課税タイミング
■法人(損金算入時期)
特定譲渡制限付株式の場合、役務提供に係る費用として、役員等に所得税の課税が生ずることが確定した日(通常は譲渡制限解除時)の属する事業年度に損金算入される。
■個人(所得認識時期)
特定譲渡制限付株式の場合、株式交付時ではなく、譲渡制限が解除された日に、その時点の株価で給与所得または退職所得として課税される。
組織再編時の対応
株式報酬制度の導入後は、合併や会社分割などの組織再編が生じる可能性を考慮する必要がある。実務的には、組織再編時点でそれまでの権利関係を一旦清算し、再編後の新会社で新たなインセンティブプランを付与するなどの対応が考えられる。
開示規制
株式報酬のための第三者割当は、発行価額の総額が1億円以上の場合、原則として金融商品取引法上の有価証券届出書の提出が必要となる。ただし、一定の要件を満たす譲渡制限付株式等を取締役等のみに交付する場合は、臨時報告書の提出で足りる。また、東京証券取引所の適時開示規則にも従う必要がある。
従業員への無償発行
2019年会社法改正による株式の無償発行は、上場会社の取締役・執行役に対する報酬等に限られるため、従業員や会社法上の役員でない「執行役員」に対しては適用されない。従業員向けには、金銭報酬債権を現物出資する形式が基本となる。
音声解説(詳細:約17分)
ガイド:Q&A
1. 本手引が推進する「攻めの経営」を促す役員報酬の導入には、どのような意義がありますか?
株式報酬や業績連動報酬の導入を促進することで、経営者に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与え、日本企業の「稼ぐ力」の向上につなげる意義があります。特に株式報酬は、経営陣に株主目線での経営を促し、海外を含む機関投資家の要望に応えるものとされています。
2. 2019年の会社法改正以前、日本企業が株式報酬を直接役員に交付することが困難だった主な法的背景は何でしたか?
当時の会社法では、無償で株式を発行することや、役務の提供を現物出資の目的とする「労務出資」が認められていませんでした。そのため、役員に報酬として株式そのものを直接交付することができず、信託を用いた手法や金銭報酬債権を現物出資する手法など、間接的な方法に頼る必要がありました。
3. 「事前交付型リストリクテッド・ストック」と「事後交付型リストリクテッド・ストック」の主な違いを説明してください。
主な違いは株式を交付するタイミングです。「事前交付型」は、一定期間の譲渡制限が付された現物株式を役員に事前に交付する方式です。一方、「事後交付型」は、勤務条件などを満たした後に、現物株式を事後的に役員に交付する方式です。
4. 法人税法上、損金算入が認められる役員給与の3つの類型を挙げてください。
法人税法上、損金算入が認められる役員給与は、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③業績連動給与の3つです。これらに該当しない役員給与は、原則として損金の額に算入されません。
5. 税制上の「特定譲渡制限付株式」とは何か、また、その株式を付与された役員等に対する所得税の課税はいつ行われますか?
「特定譲渡制限付株式」とは、役務提供の対価として交付される株式で、一定期間の譲渡制限が設けられ、勤務条件や業績条件未達の場合に会社が無償取得(没収)できる事由が定められているものです。所得税の課税時期は、株式の交付時ではなく、譲渡制限が解除された日となります。
6. CGSガイドラインは、経営陣の報酬体系を設計する上で、経営戦略と報酬をどのように関連付けるべきだと提言していますか?
まず経営戦略が存在することが必要であり、その上で経営戦略を踏まえて具体的な目標となる経営指標(KPI)を設定し、それを実現するためにどのような報酬体系が良いのか、という順番でストーリー性をもって検討することが重要だと提言しています。報酬政策は、自社が掲げる経営戦略等の基本方針に沿った内容であるべきです。
7. 2019年の会社法改正によって可能となった株式の「無償発行」とはどのような制度で、誰を対象としていますか?
「無償発行」とは、金銭の払込み等を要せずに募集株式を発行・処分する制度です。この制度は、上場会社がその会社の取締役または執行役に対する報酬等として株式の発行等を行う場合に限定して認められており、執行役員や一般従業員に対する無償発行は認められていません。
8. CGSガイドラインが推奨する「指名委員会」および「報酬委員会」の主な役割は何ですか?
CEO・経営陣の選解任や評価、報酬に関する基準およびプロセスを明確化し、役員人事プロセスの客観性を向上させることが主な役割です。これらの委員会は社外者を中心に構成・活用し(過半数が社外役員など)、CEOの評価や報酬決定、後継者計画の策定・運用に主体的に関与することが期待されています。
9. 「パフォーマンス・シェア」とは、どのような仕組みの株式報酬ですか?
中長期の業績目標の達成度合いに応じて、株式を役員に交付する事後交付型の株式報酬です。一定の業績評価期間が経過した後に、利益や株価などの指標を用いて算定された数の株式が交付されるため、中長期の業績向上に向けた強いインセンティブとなります。
10. 「株式交付信託」は、役員報酬制度においてどのように活用されますか?
導入企業が金銭を信託銀行に拠出し、信託がその資金で市場から自社株を取得・管理します。その後、信託期間中に役員の役位や業績達成度に応じてポイントが付与され、一定期間経過後に、累積したポイントに応じた株式が役員に交付される仕組みです。
用語集
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 攻めの経営 | 我が国企業のローリスク・ローリターンの経営からの脱却と「稼ぐ力」の向上を目指す経営姿勢。中長期的な企業価値向上に向けた適切なリスクテイクを伴う経営を指す。 |
| コーポレートガバナンス・コード | 企業が持続的に企業価値を向上させるための企業統治の原則。本手引では、このコードの原則4-2で、経営陣の報酬は中長期的な業績を反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブ付けを行うべきとされている点が言及されている。 |
| CGSガイドライン | 経済産業省が策定した「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」。企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的とし、取締役会の機能強化、役員人事プロセスの客観性向上、CEOのリーダーシップ強化等の提言を含む。 |
| 株式報酬 | 役員や従業員に対し、報酬として金銭ではなく自社の株式を付与する制度。経営陣に株主目線での経営を促し、中長期の業績向上インセンティブを与える利点がある。 |
| 業績連動報酬 | 企業の業績や株価の変動に応じて経営陣が得られる経済的利益が変化する報酬。中長期的な企業価値向上への動機付けとなる。 |
| リストリクテッド・ストック | 一定期間の譲渡制限が付された株式報酬。在職条件のみが付される場合が多い。交付タイミングにより事前交付型と事後交付型がある。 |
| 事前交付型リストリクテッド・ストック | 職務執行開始後速やかに、一定期間の譲渡制限が付された現物株式を役員に交付する方式。リテンション効果(転職防止)や中長期の株価向上インセンティブを持つ。 |
| 事後交付型リストリクテッド・ストック | 予め交付株式数を定め、中期経営計画終了時など一定期間経過後にその株式を役員に交付する方式。 |
| パフォーマンス・シェア | 中長期の業績目標の達成度合いに応じて、事後的に株式を役員に交付する方式。中長期の業績向上に向けた強いインセンティブとなる。 |
| ストックオプション | 自社の株式をあらかじめ定められた権利行使価格で購入する権利(新株予約権)を付与する制度。 |
| 株式交付信託 | 企業が金銭を信託に拠出し、信託がその資金を元に市場等から自社株を取得し、一定期間経過後に役員に株式を交付する手法。 |
| 特定譲渡制限付株式 | 税法上の概念で、①一定期間の譲渡制限、②勤務条件や業績条件に基づく無償取得(没収)事由、③役務提供の対価であること、の要件を満たす株式。所得税の課税時期が交付時ではなく譲渡制限解除時となる。 |
| 無償発行 | 金銭の払込み等を要しないで募集株式を発行・処分すること。2019年改正会社法により、上場会社が取締役・執行役への報酬として株式を発行する場合に限り可能となった。 |
| 現物出資 | 金銭以外の財産を出資の目的とすること。株式報酬では、役員に付与された金銭報酬債権を現物出資財産として会社に給付し、その対価として株式の交付を受ける手法が用いられる。 |
| 定期同額給与 | 1ヶ月以下の一定期間ごとに同額で支給される給与。法人税法上、損金算入が認められる役員給与の一つ。 |
| 事前確定届出給与 | 事前の届出に従い、所定の時期に確定額の金銭または確定数の株式等を支給する給与。法人税法上、損金算入が認められる役員給与の一つ。 |
| 業績連動給与 | 利益、株価、売上高などの業績指標に連動して支給する給与。報酬委員会の決定や情報開示など一定の要件を満たすことで、法人税法上、損金算入が認められる。 |
| ROE (Return On Equity) | 自己資本利益率。当期純利益を自己資本で割った指標で、株主資本に対してどれだけの利益を生み出したかを示す。業績連動給与の指標として利用される。 |
| ROIC (Return On Invested Capital) | 投下資本利益率。税引後営業利益を投下資本(株主資本+有利子負債)で割った指標で、資本効率を示す。業績連動給与の指標として利用される。 |
| TSR (Total Shareholder Return) | 株主総利回り。一定期間における株価上昇分と配当金を合わせた、投資家から見た総合的なリターンを示す指標。業績連動給与の指標として利用される。 |
| 指名委員会・報酬委員会 | 取締役会の下に設置され、役員の指名や報酬決定の客観性・透明性を高めるための機関。CGSガイドラインでは、社外者を中心とした構成での設置・活用が推奨されている。 |
| 独立社外取締役 | 会社の経営陣から独立した立場で職務を執行する社外取締役。業績連動給与の損金算入要件において、報酬委員会の構成員として重要な役割を担う。 |
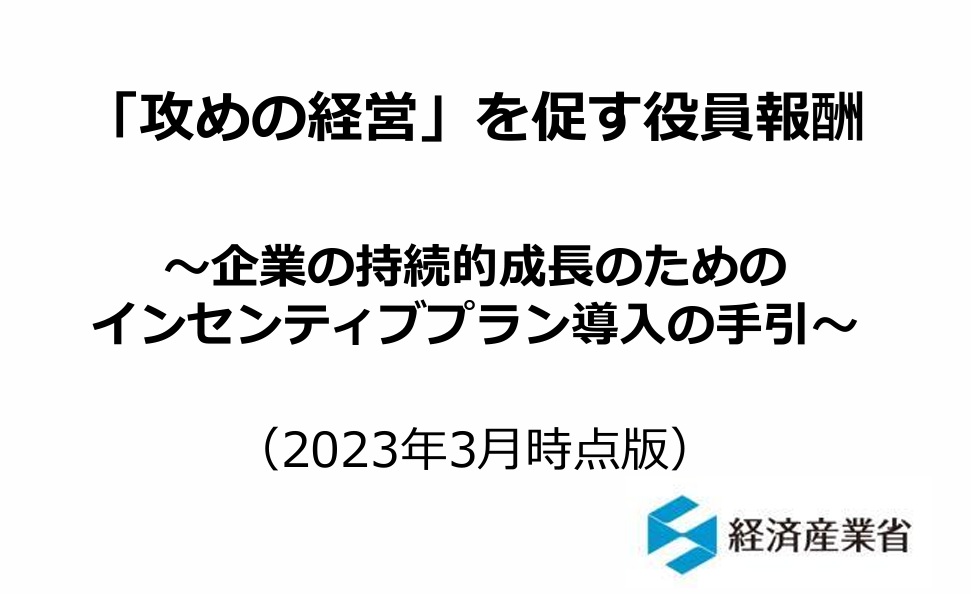

コメント