エグゼクティブサマリー
本記事は、金融庁の「記述情報の開示の好事例集2022」に基づき、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報、特に「社会(人的資本、多様性等)」に関する開示の主要な傾向と洞察をまとめたものです。改正内閣府令により、女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女間賃金格差といった人的資本に関する情報の開示が新たに求められており、企業の情報開示は新たな段階に入っています。
投資家が期待する開示は、単なるデータ羅列ではなく、経営戦略と人材戦略の連動性、KPI設定の論理的根拠、そして独自性と比較可能性のバランスが取れた情報です。好事例とされる企業は、自社の企業理念やビジネスモデルと紐づけたストーリー性のある開示を行い、具体的な施策と定量的な目標・実績(KPI)を明確に示している。
主要なテーマとして、以下の点が挙げられます。
- 人的資本経営の具体化
「人の成長=企業の成長」といった理念を掲げ、対話の文化醸成、働き方改革、Well-being推進などの施策を通じて企業文化の変革を図り、その成果を離職率や残業時間といった具体的な指標で開示する動きが顕著である。 - ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の加速
女性活躍推進が最重要課題の一つとなっており、多くの企業が女性管理職比率に関する中長期的な数値目標を設定している。さらに、LGBTQに関する取り組みや障がい者雇用など、より広範なD&I施策の開示も進んでいる。 - サプライチェーンと人権
グローバルに事業を展開する企業を中心に、サプライチェーン全体を対象とした人権デューデリジェンスの実施や、NGOの客観的データを活用したリスク評価など、人権尊重への取り組みが具体的に開示されている。 - マテリアリティ(重要課題)の戦略的特定
自社事業の持続的成長と社会的要請の両面からマテリアリティを特定し、SDGsと紐づけながら経営戦略に統合するプロセスを開示する事例が増加している。 - DXと人材育成
デジタルトランスフォーメーション(DX)を経営戦略の柱と位置づけ、全社的なデジタルリテラシー向上や専門人材の育成・獲得に関する具体的な目標と進捗を開示する企業も見られる。
総じて、先進的な企業はサステナビリティ情報を単なる義務的開示と捉えず、企業価値向上に繋がる戦略的なコミュニケーションツールとして活用しています。
関連情報
解説簡易動画(約7分)
1. サステナビリティ情報開示の要点と投資家の期待
金融庁の好事例集は、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報、特に人的資本や多様性に関する開示の質の向上を目的としています。改正内閣府令では「従業員の状況(女性管理職比率、男性育児休業取得率及び男女間賃金格差)」の開示が新たに求められており、これらの項目は開示の基準点となっている。
1.1. 投資家・アナリストが期待する開示のポイント
投資家は、企業の持続的成長を評価する上で、以下の観点からの情報開示が有用であると考えています。
- 戦略との連動性
経営戦略や企業理念と、人的資本・サステナビリティ戦略がどのように結びついているかの説明。特にKPIの目標設定の背景にあるロジックや前提の開示。 - 独自性と比較可能性
自社固有の戦略に沿った独自指標と、標準的な指標による比較可能な情報を適切に使い分けた開示。 - 定量性と具体性
独自指標を数値化する際の明確な定義と、過去の実績を含む長期時系列での変化の開示。 - マテリアリティの明確化
企業がどの社会課題を重要(マテリアリティ)と捉えているかについて、比較可能な形での標準化。 - グローバルな視点
グローバル展開する企業においては、人権に関する地政学リスクなど、事業展開地域(ロケーション)に着目した情報開示。
1.2. 企業の情報開示における課題と対応策
好事例企業も、開示の充実化にあたり様々な課題に直面しています。特に、法定開示項目と、人的資本経営のストーリー性を両立させる点に苦労が見られます。
| 課題 | 対応策と効果 |
|---|---|
| 定量情報をストーリーにどう盛り込むか | 決算説明会の動画を参考にし、担当役員へニュアンスを確認することで、ストーリーを深く理解。その上で、ISO 30414なども参考に開示する定量情報を選定。 |
| 部署横断的な情報収集と開示判断 (丸井グループ) | 経営陣の「投資家との共創」姿勢と、統合報告書作成で培われた部署横断の協力体制が背景にある。失敗を恐れず積極的に開示するリテラシーが醸成されており、最終的な開示判断は担当部門へ権限委譲することで円滑な開示を実現。 |
| 多岐にわたる事業と社会課題の特定 (双日) | 事業成長と密接に関係する社会課題を優先的に特定し、長期ビジョンに盛り込む。感覚値ではなく客観的データ(例:英国NGOの糾弾件数データ)を用いてサプライチェーン上の人権課題を分析し、特定プロセスの納得感を高める。 |
2. 企業別の好事例分析
2.1. 人的資本経営と企業文化の変革(株式会社丸井グループ)
丸井グループは「人の成長=企業の成長」という理念を基盤に、17年間にわたる企業文化変革を人的資本経営の核として開示しています。
企業文化変革のための8つの施策:
- 企業理念: 理念共有のための対話を重ね、結果的に退職率が約3%の低水準で定着。
- 対話の文化: 結論を求めない、傾聴するなど7つの目安を設け、双方向コミュニケーションを醸成。
- 働き方改革: 仕事の本質を「価値の創出」と捉え、残業時間を月平均4.5時間まで削減(2022年3月期)。
- 多様性の推進: 独自のKPI「女性イキイキ指数」を掲げ、男性の育休取得率は4年連続100%を達成。
- 手挙げの文化: 社員の自主性を促し、約8割の社員が何らかのプロジェクトに自ら手を挙げて参画。
- グループ間職種変更異動: 全グループ社員の約77%が職種変更を経験し、個人の多様性とレジリエンスを育成。
- パフォーマンスとバリューの二軸評価: 業績評価に加え、360度評価を導入。
- Well-being: CWO(チーフウェルビーイングオフィサー)を中心に、活力ある組織を目指す。
ガバナンスと投資:
人材戦略委員会
経営戦略と人材戦略の連動を図るため、取締役会の諮問機関として設置。社外取締役も委員として参加。
人的資本投資の再定義
教育研修費に加え、新規事業に係る人件費なども「人的資本投資」と再定義。2022年3月期の77億円から2026年3月期には120億円まで拡大する計画。
2.2. サプライチェーンにおける人権尊重(双日株式会社)
双日は、グローバル総合商社としてサプライチェーン上の人権尊重を経営の重要課題と位置づけ、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿ったフレームワークで取り組みを開示しています。
- リスク評価
英国NGO「ビジネスと人権リソースセンター」のデータベースを活用し、自社事業における高リスク分野を客観的に特定。サプライチェーンのどの段階でリスクが発生しやすいかを分析・図示している。 - PDCAサイクルの構築
特定した高リスク事業分野に対し、以下の体制で継続的な改善を図る。
1. 網羅的なアンケート実施
2. グループ会社へのヒアリングを通じたモニタリング
3. 現地実査を含む人権デューデリジェンス - 方針の周知徹底:
「双日グループ サプライチェーンCSR行動指針」を策定し、サプライヤーやグループ会社に周知。グループ各社から「人権尊重への理解と事業現場への認識徹底」に関する確認書を取得している。
2.3. ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進
D&Iは多くの企業で経営戦略の中核に据えられており、特に女性活躍推進に関する定量的な目標設定が共通して見られます。
カゴメ株式会社
- 経営戦略としてのD&I
多様な知の組み合わせによる新たな価値創造を目的とし、D&Iを経営戦略と明確に位置づけている。 - 長期ビジョン
2040年までに各職位の女性比率を50%にすることを掲げ、これをイノベーション創出のための指標と定義。 - 重点活動
「本音で意見が言い合える」心理的安全性の高い職場づくりと、SOGI(性的指向・性自認)や障がい者活躍といった推進領域の拡充に注力。
三井物産株式会社
- 推進体制
経営会議の諮問委員会として「ダイバーシティ推進委員会」を設置。海外現地法人役員や女性役員を含む多様なメンバーで構成し、活動内容は社内イントラネットで広く公開。 - 定量目標と実績
2025年3月期までに女性管理職比率10%を目標とし、育成プログラムや経営会議メンバーによるスポンサーシッププログラムを実施。 - グローバルな視点
海外拠点における現地採用人材の活躍推進にも注力しており、選抜型研修「Change Leader Program」などを実施。
株式会社サンゲツ
- 基本方針の策定
「サンゲツグループダイバーシティ基本方針」を定め、性別、年齢、国籍、障がいの有無、性自認・性的指向等に関わらない個性の尊重を明記。 - 具体的な取り組み
◦ 女性活躍: 2022年度までに**女性管理職比率20%**を目標とする行動計画を策定。
◦ LGBTQ: ALLY(アライ)ステッカーの掲示支援やヘルプライン設置など、具体的な支援策を実施。 - 実績の可視化
女性管理職比率や障がい者雇用率の推移をグラフで図示し、定量的な進捗を分かりやすく開示。
各社の女性活躍に関するKPI(一部抜粋)
| 会社名 | 指標 | 実績/目標 |
|---|---|---|
| 東急株式会社 | 管理職に占める女性比率 | 8.9% (2021年度実績) / 10%以上 (2023年度目標) |
| 株式会社リコー | 女性管理職比率 (グローバル) | 9.0% (2022年4月時点) |
| 帝人株式会社 | 女性役員数 | 3名 (2022年3月期実績) / 4名以上 (2022年度目標) |
| 株式会社ひろぎんホールディングス | 女性管理職比率 | 6% (2022年4月実績) / 10%程度 (2030年度目標) |
| アンリツ株式会社 | 幹部職に占める女性の割合 (グローバル連結) | 10.9% (2021年度) |
2.4. 人材育成と自律的キャリア形成
従業員の成長を促し、人的資本を拡充するための制度設計と開示も重要なテーマとなっています。
カゴメ株式会社:
- 自律的キャリア構築支援
自己申告制度、キャリア異動希望制度、社内公募制度、カフェテリア型研修などを整備。 - 人材育成担当
社員のキャリア自律をサポートする専門職を配置。従業員との面談を通じてキャリア像を共有し、経営へのブリッジ役も担う。
三井物産株式会社:
- 多様なキャリアパス
従来のラインマネージャー職に加え、高度な専門性を持つ人材のための「Expertバンド」(複線型人事制度)を導入。 - キャリアチャレンジ制度
年齢や昇格要件に関わらず、適任者が上位ポジションに挑戦できる制度を整備。
株式会社サンゲツ:
- 新人事制度
職能型と職務型のハイブリッド型制度へ移行。プロフェッショナル人材創出を目指すコースを新設し、社員のエンゲージメント向上を図る。
2.5. サステナビリティ経営とマテリアリティの開示
ESG課題を経営に統合し、自社にとっての重要課題(マテリアリティ)を特定・開示するアプローチが主流となっています。
J.フロント リテイリング株式会社:
- 経営のゴール
グループビジョンのゴールとして「Well-Being Life(心身ともに豊かなくらし)」を設定。 - マテリアリティ
「脱炭素社会の実現」「サーキュラー・エコノミーの推進」など7つのマテリアリティを特定し、それぞれに2030年度のKGIを設定。
株式会社サンゲツ:
- 特定プロセス
「社会及び長期投資家にとっての重要度」と「自社事業の持続的成長への影響」の2軸でマテリアリティをマッピングし、プロセスを図示。
不二製油グループ本社株式会社:
- マテリアリティマップ
「自社グループが社会に与える影響度」と「社会課題が自社グループに与える影響度」の2軸で整理し、リスク管理と連動させている。 - 目標設定の具体化
株式会社村田製作所や株式会社髙島屋、株式会社キッツなどは、ESGの各項目における重点課題に対し、中期・長期の定量目標を設定し、開示している。
2.6. デジタルトランスフォーメーション(DX)と人材戦略
DXの推進は、事業変革だけでなく、人材戦略においても重要な要素となっている。
旭化成株式会社:
- DXロードマップ
「デジタル導入期」から「デジタル創造期」「デジタルノーマル期」へと至る明確なロードマップを策定。 - 推進体制
デジタル共創本部を設置し、機能を集約。共創ラボ「CoCo-CAFE」を開設し、社内外の人材交流を促進。 - 人材育成・獲得
「4万人デジタル人財化」を掲げ、全従業員のデジタルリテラシー向上を目指す。 - KPI設定
2024年度目標として「DX-Challenge 10-10-100」を策定。
▪ デジタルプロフェッショナル人財を10倍(2,500名程度)に
▪ データ活用量を10倍に
▪ 重点テーマで100億円の増益貢献(3年累計)
3. 好事例企業一覧と注目テーマ
本資料で分析対象とした企業および金融庁のレポートで言及された企業の注目テーマは以下の通りです。
| 企業名 | 経営 | 人材 | 多様性 | SDGs | DX |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 丸井グループ | ● | ● | ● | ||
| 双日株式会社 | ● | ● | ● | ● | |
| カゴメ株式会社 | ● | ● | ● | ||
| 三井物産株式会社 | ● | ● | ● | ||
| 株式会社サンゲツ | ● | ● | ● | ● | |
| J.フロント リテイリング株式会社 | ● | ● | |||
| オムロン株式会社 | ● | ● | ● | ||
| アンリツ株式会社 | ● | ● | ● | ||
| 豊田合成株式会社 | ● | ● | |||
| 東急株式会社 | ● | ● | |||
| 株式会社リコー | ● | ● | |||
| 帝人株式会社 | ● | ● | |||
| 株式会社ひろぎんホールディングス | ● | ● | |||
| 株式会社村田製作所 | ● | ● | ● | ||
| 株式会社髙島屋 | ● | ● | ● | ||
| 株式会社キッツ | ● | ● | ● | ● | |
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 | ● | ||||
| 不二製油グループ本社株式会社 | ● | ● | ● | ||
| 旭化成株式会社 | ● | ● |
4. 音声動画(詳細:約20分)
5. ガイド:Q&A
1. 投資家やアナリストが人的資本情報の開示において有用と考える、2つの異なる観点とは何ですか?
投資家やアナリストは、「独自性」と「比較可能性」の2つの観点を有用と考えています。独自性とは、自社固有の戦略やビジネスモデルに沿った取り組み・指標・目標を開示することです。一方、比較可能性とは、他社と比較できるよう標準的な指標で開示することであり、これらを適宜使い分けるか、併せた開示が期待されています。
2. 株式会社丸井グループが掲げる人的資本経営の根本的な理念と、その理念を共有する取り組みがもたらした組織的な変化について説明してください。
丸井グループは「人の成長=企業の成長」という理念を人的資本経営の根本に置いています。この理念について対話の場を設けて会社のパーパスと個人のパーパスのすり合わせを行った結果、理念を共有できない社員が退職し一時的に退職率は上がりましたが、その後は約3%前後の低水準で安定し、会社と個人との「選び選ばれる関係」の基盤が構築されました。
3. 双日株式会社は、サプライチェーンにおける人権リスクを客観的に評価するため、どのような外部データを活用しましたか?
双日株式会社は、サプライチェーン上の人権リスクを特定・分析するにあたり、英国のNGO「ビジネスと人権リソースセンター」が保有する環境・人権リスクの発生事例データベースを活用しました。これにより、感覚値ではなく客観的なデータに基づいて、自社事業の中で特にリスクが高い事業分野や、サプライチェーン上のリスク発生箇所を特定することが可能になりました。
4. カゴメ株式会社がダイバーシティ&インクルージョンを次の段階へ進めるために、2022年度の重点活動として掲げた2つのテーマは何ですか?
カゴメ株式会社が掲げた2022年度の重点活動テーマは、「『本音で意見が言い合える』心理的安全性の高い職場づくりに向けた取り組みの強化」と、「ダイバーシティ&インクルージョン推進領域の拡充、特に『SOGI』『障がい者活躍』領域の取り組み強化」です。これらは、多様な人材を活かしイノベーションを生み出すための土台作りと位置づけられています。
5. 三井物産株式会社がダイバーシティ経営を推進するために設置した経営会議の諮問委員会の名称と、その主な活動内容を挙げてください。
三井物産株式会社は、経営会議の諮問委員会として「ダイバーシティ推進委員会」を設置しています。この委員会では、女性活躍推進や海外の現地法人・各拠点で採用された社員の活躍推進に向けた指標管理やアクションプランのモニタリングを行っています。また、社員エンゲージメントサーベイの結果を確認し、全社施策の討議も行っています。
6. 株式会社サンゲツは、マテリアリティ(重要課題)を特定する際に、どのような2つの軸で評価・整理を行いましたか?
株式会社サンゲツは、「社会及び長期投資家にとっての重要度」と「当社事業の持続的成長への影響」という2つの軸を用いてマテリアリティを特定しました。このプロセスを通じて抽出された重要課題は、マッピングされ、長期ビジョンや関連するSDGsと紐づけられています。
7. オムロン株式会社が定義する「人が活きるオートメーション」には、人と機械の関係性によって分類される3つの段階があります。その3つとは何ですか?
オムロン株式会社が定義する「人が活きるオートメーション」の3段階は、「代替」「協働」「融和」です。「代替」は機械が人の作業を担う自動化、「協働」は機械が人と共に働く段階です。そして「融和」は、機械が人の可能性や人間らしさを引き出し、人に合わせて自律化を促す、最も進化した段階とされています。
8. 東急株式会社が人材戦略の一環として掲げている健康経営において、従業員の健康状態を示す具体的なKPIを2つ挙げてください。
東急株式会社が設定している健康経営に関するKPIには、「喫煙者率」(2023年度目標:22.0%以下)や「肥満者率」(同:35.0%以下)、「運動習慣率」(同:50.0%以上)などがあります。これらの指標を用いて従業員の健康状態を定量的に把握し、改善に取り組んでいます。
9. 帝人株式会社は、事業のグローバル化に伴い、役員層の多様性を推進するためのKPIを設定しています。具体的にどのような指標を設けていますか?
帝人株式会社は役員層の多様性推進のため、「女性役員数」と「非日本人役員数」をKPIとして設定しています。2021年度実績は女性役員3名、非日本人役員3名であり、2022年度の目標としてそれぞれ4名以上を掲げています。
10. 旭化成株式会社がDX(デジタルトランスフォーメーション)の進捗を測るために設定したKPI「DX-Challenge 10-10-100」が目指す3つの具体的な目標を説明してください。
旭化成株式会社の「DX-Challenge 10-10-100」が目指す3つの目標は、2024年度までに「デジタルプロフェッショナル人財を2021年比で10倍(約2,500名)にする」、「グループ全体のデジタルデータ活用量を10倍にする」、そして「選定した重点テーマで100億円の増益貢献(3年累計)を達成する」ことです。
6. 主要用語集
| 用語 | 定義 |
| 人的資本 (Human Capital) | 従業員が持つ知識、スキル、能力、経験などを、企業の価値創造の源泉となる「資本」として捉える考え方。教育・研修費や新規事業に係る人件費などを「人的資本投資」として再定義する企業もある(丸井グループの事例)。 |
| ダイバーシティ&インクルージョン (D&I) | 性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向等にかかわらず、従業員一人ひとりの個性を多様性として活かし、互いに尊重しあうこと。また、それらの多様な能力が相互に影響し機能し合う(インクルージョン)ことで、イノベーション創出や事業成長を目指す経営戦略。 |
| マテリアリティ (Materiality) | 企業の持続的な成長にとっての「重要課題」。社会及び長期投資家にとっての重要度と、自社事業への影響度の2つの軸で特定され、サステナビリティ経営の重点テーマとなることが多い(サンゲツ、コスモエネルギーHD等の事例)。 |
| KPI (Key Performance Indicator) | 重要業績評価指標。サステナビリティや人的資本に関する取り組みの進捗や成果を定量的に測定するための指標。「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」「障がい者雇用率」などが多くの企業で設定されている。 |
| Well-being | 従業員一人ひとりが心身ともに健康で、やりがいを持って生き生きと仕事に取り組める状態、またはそれを目指す取り組み。丸井グループではCWO(チーフウェルビーイングオフィサー)を設置している。 |
| サステナビリティ経営 | 社会課題の解決と企業の持続的な成長の両立を目指す経営。ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を経営戦略の中核に据え、企業価値と社会価値の向上を図る(キッツ、Jフロントリテイリング等の事例)。 |
| サプライチェーンにおける人権尊重 | グローバルに事業を展開する企業が、自社だけでなく、原材料の調達から製品が消費者に届くまでの全過程(サプライチェーン)に関わる人々の人権が守られるよう努めること。双日は「ビジネスと人権に関する国連指導原則」に沿って推進している。 |
| DX (デジタルトランスフォーメーション) | デジタル技術を活用し、ビジネスモデルや業務、組織、企業文化などを変革し、競争上の優位性を確立すること。旭化成は「デジタル創造期」として、人財育成を含めたDX推進に取り組んでいる。 |
| 心理的安全性 (Psychological Safety) | 組織の中で、自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のこと。カゴメは、多様な人材を活かす土台として、心理的安全性の高い職場づくりを重点活動テーマに掲げている。 |
| SOGI | Sexual Orientation and Gender Identity(性的指向と性自認)の頭文字をとった言葉。カゴメはダイバーシティ推進領域の拡充の一環として、SOGIに関する取り組みを強化している。 |
| アンコンシャス・バイアス (Unconscious Bias) | 自分自身では気づいていない「ものの見方や捉え方のゆがみや偏り」。双日は部長研修のテーマとして取り上げ、多様性を活かす組織づくりの一環としている。 |
| CHRO (Chief Human Resource Officer) | 最高人事責任者。経営陣の一員として、経営戦略と連動した人材戦略の策定・実行を担う。三井物産や丸井グループでは、CHROがダイバーシティや人材戦略に関する委員会の要職に就いている。 |
| ESG | Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の3つの要素。企業の持続的な成長を評価する非財務情報として、投資家などから重視されている。 |
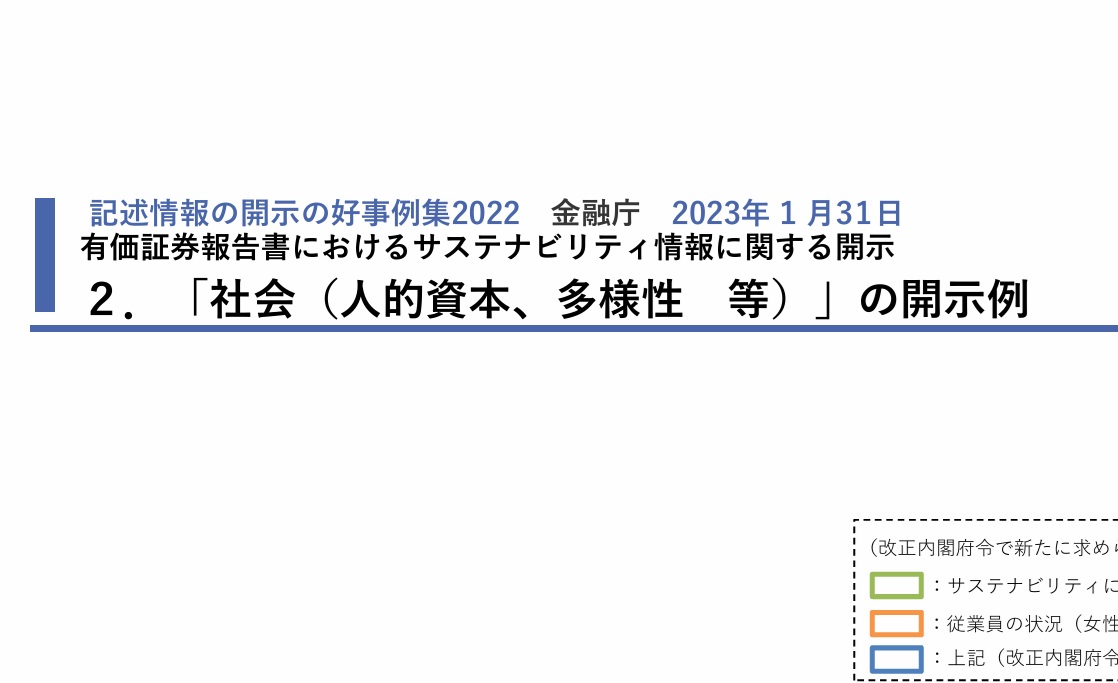

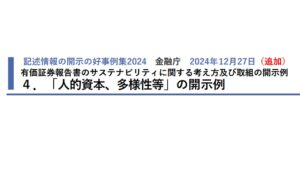
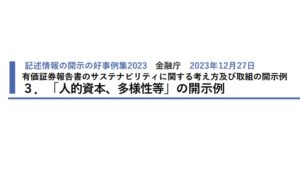
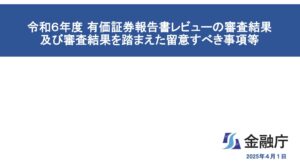
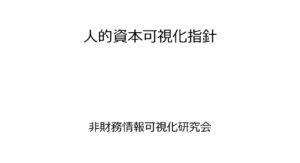
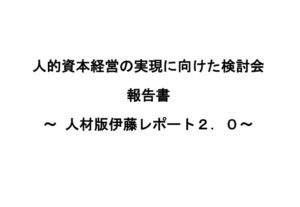
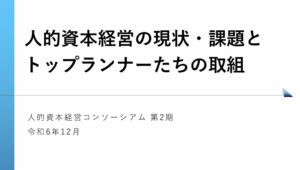
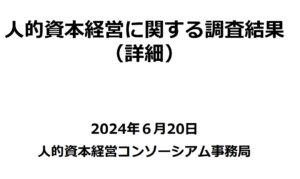
コメント