エグゼクティブ・サマリー
過去10年間で、日本のコーポレートガバナンスは役員報酬制度の領域で大きな変革を遂げました。その中心にあるのが、2016年以降に急速に普及した譲渡制限付株式(Restricted Stock, RS)です。現在、全上場企業の約6割が何らかの株式報酬制度を導入し、その中でもRSは約1,400社で採用されるなど、事実上の標準となりつつあります。
この変革は、単一の事象ではなく、複数の要因が複合的に作用した結果です。
- ガバナンス改革の推進
2015年に導入されたコーポレートガバナンス・コードが、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブとして株式報酬を強く推奨した。 - 決定的な税制改正
2016年の税制改正により、RSの付与が企業にとっては損金算入可能、役員にとっては課税繰延べ対象となり、導入の障壁が劇的に低下した。 - 投資家からの圧力
スチュワードシップ・コードを背景に、国内外の機関投資家が経営陣と株主の利害一致を求め、業績や株価に連動する報酬体系への移行を強く要求した。
RS導入の主目的は、経営陣に自社株を保有させることで「株主としての目線」を植え付け、短期的な業績だけでなく中長期的な企業価値向上へのコミットメントを促すことにあります。実際、RS導入企業は市場平均を上回る株価パフォーマンスを示す傾向が報告されています。
しかし、制度の普及はまだ第一段階に過ぎません。
現状では、多くの企業が税制上の制約から在任期間のみを条件とするシンプルなRSを導入しています。今後の課題は、業績目標の達成度に応じて報酬が変動する、より実質的なインセンティブ設計(パフォーマンス・シェア等)への質的深化です。加えて、報酬決定プロセスの透明性向上、不祥事発生時に報酬を没収・返還させるリスク管理策(マルス・クローバック条項)の一般化、さらには人材獲得競争の激化を背景とした従業員全体への株式インセンティブの拡大が、今後の重要な潮流となります。
解説動画
1. 譲渡制限付株式(RS)の急速な普及とその背景
RSの定義と仕組み
譲渡制限付株式(RS)とは、役員や従業員に対し、一定期間(通常3年以上)の譲渡制限が付された自社株式を報酬として付与する制度です。付与された者はその直後から株主となり、議決権の行使や配当の受領が可能だが、所定の譲渡制限期間が満了するまでは株式を売却できません。
この制度は、経営陣に株主と同じ視点を持たせ、中長期的な企業価値向上への動機付けを目的としている。
普及の動向
日本の役員報酬は伝統的に固定給が中心で、業績に連動するインセンティブが乏しいと指摘されてきました。しかし、コーポレートガバナンス改革の流れの中で株式報酬への注目が高まり、特に2016年の制度・税制整備を機にRSの導入が爆発的に増加しました。
| 指標 | 2015年 | 2023年10月 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬制度導入企業数 | 592社 | 2,321社 | 約4倍に増加 |
| (全上場企業に占める割合) | (約15%) | (約60%) | – |
| うち、RS導入企業数 | ほぼ0社 | 1,418社 | 急速に普及 |
RSは、権利行使まで株主になれないストックオプションの課題を克服し、仕組みの簡潔さや運用コストの低さから、従来主流であった「株式報酬型ストックオプション」や株式交付信託を凌駕し、短期間で日本の株式報酬制度の中核を成すに至りました。
普及を後押しした主な要因
RSの普及は、以下の3つの主要因が同時期に作用した結果である。
- コーポレートガバナンス・コード: 経営陣へのインセンティブ付けとして株式報酬を推奨。
- 2016年税制改正: RSの税務上の不利な取扱いを解消し、導入のハードルを撤廃。
- 株主・投資家からの要求: 経営と株主の利害一致を求めるエンゲージメント活動の活発化。
RS導入企業は、非導入企業に比べてTOPIXを上回る株価パフォーマンスを示す傾向が報告されており、一分析では2016年以降の累積で約25%のアウトパフォームが見られました。これは、RS導入が「経営陣が自社の将来に自信を持っている」というポジティブなシグナルとして市場に評価された側面もあるとされています。
2. コーポレートガバナンス改革と法制度整備の役割
コーポレートガバナンス・コードの影響
2015年に導入されたコーポレートガバナンス・コード(CGコード)は、RS普及の直接的な引き金となりました。
2015年初版
役員報酬について「中長期的な業績やリスクを反映させ、健全な企業家精神を発揮させるインセンティブ付けを行うべき」と明記。現金報酬と自社株報酬の適切なバランスを求め、株式報酬の導入を強く示唆。
2018年改訂
報酬決定プロセスの客観性・透明性を強調。報酬委員会など任意の諮問委員会の設置や、独立社外取締役の関与を求め、「株主から見て妥当か」を検討する仕組みの構築を促進。
このCGコードの原則を受け、経済産業省が2016年4月に「攻めの経営」を促す役員報酬の手引きを公表し、RS導入の具体的な手続きを示したことが、企業の制度導入を加速。
会社法改正による後押し
2019年の会社法改正により、上場企業が取締役に対し金銭を介さず株式そのものを無償で交付できることが法的に明文化。それ以前は「金銭報酬債権を現物出資する」という迂遠な手続きが必要だったが、改正によって制度の適法性が明確になり、株主への説明責任も果たしやすくなり、この法整備を受け、RS導入企業の約80%が既存の金銭報酬枠とは別に、新たな株式報酬枠を株主総会で承認を得て設定。
3. 2016年税制改正の決定的影響
RS普及における最大の転機は、平成28年度(2016年)の税制改正でした。
改正前の課題
改正前、役員に株式を付与しても、その費用は法人税法上「損金」として認められず、企業にとって税負担が重い状況でした。このため、損金算入が可能で、役員側も退職所得として税優遇を受けられた「1円ストックオプション」が「退職慰労金の代替」として広く利用されていました。
2016年改正の要点
この改正により、RSの税務上の取扱いが明確化され、ストックオプションと同等の税務メリットが認められました。
- 役員側(個人): RS付与時には課税されず、譲渡制限が解除された時点で初めて所得として課税される(課税の繰延べ)。
- 企業側(法人): 譲渡制限が解除された時点で、支給額相当額を損金に算入できる。
この改正はRS導入の強力なインセンティブとなり、翌2017年の株主総会シーズンから導入企業が急増。同年の6月総会だけで130社の上場企業がRS等の現物株式報酬導入を発表しました。
退職所得としての活用と残された課題
譲渡制限の解除を役員の退任時に設定することで、RSを退職所得として扱うことが可能となり、役員は税法上の優遇措置(控除、1/2課税など)を受けられるます。これにより、RSは「長期インセンティブ兼退職報酬」としての性格を帯び、経営者に超長期の企業価値向上を促す設計が可能となった。実際に、譲渡制限期間を30年と設定する企業も存在します。
一方で、税制には課題も残ります。。特に、業績目標の達成を条件とする業績連動型のRSは、税務上「業績連動給与」とみなされ、原則として損金不算入となります。経団連などはこの点の改正を求めており、税制が整備されれば、より実質的なインセンティブ設計が広がると期待されています。
4. 株主・投資家からの期待と圧力
スチュワードシップ・コードとエンゲージメント
2014年に導入されたスチュワードシップ・コードは、機関投資家に対し、投資先企業との建設的な対話(エンゲージメント)を通じて企業価値向上を促す責務を課しました。この中で「経営陣の報酬体系」は最重要テーマの一つとなりました。特に海外投資家は、経営陣の自社株保有率の低さや、業績と連動しない報酬体系に批判的であり、RSのような制度の導入を強く求めました。
投資家の要求事項とリスク管理
議決権行使助言会社や主要機関投資家は、株式報酬制度に対し、以下のような具体的なガイドラインを示している。
- 株式の希薄化: 潜在的な株式価値の希薄化率を5~10%以下に抑制すること。
- 譲渡制限期間: 在任条件のみのRSの場合、制限期間を最低3年以上とすること。
また、過度なリスクテイクを抑制する仕組みとして、不祥事発生時に報酬を没収(マルス条項)または返還(クローバック条項)させる規定の導入も重視されています。武田薬品工業の株主総会でクローバック条項導入の株主提案が提出された事例は象徴的であり、これを機に日本企業でも導入の動きが広がり始めています。
意識の変化:「報酬=コスト」から「報酬=投資」へ
かつては「役員報酬は低いほど良い」という風潮もあったが、現在では「適切なリスク・リターンを与えないと企業は成長しない」という認識が、企業と投資家の間で共有されつつあります。経営陣と株主の利害を一致させるRSは、この新しい価値観に合致するツールとして、投資家からの支持を得やすくなっています。
5. RS導入企業の設計トレンドと事例分析
制度設計の主要トレンド
| 項目 | 主流な設計 | 備考・事例 |
|---|---|---|
| 譲渡制限期間 | 3年 | ・機関投資家の要求水準とも合致しており、慣行となっている。 ・一部企業では、長期コミットメントを促すため30年といった超長期の設定も見られる。 |
| 業績連動条件 | 在任条件のみ(業績連動なし) | ・税制上の制約から、導入企業上位20社のうち16社(80%)がこの形式を採用。 ・少数派ながら、より高度な業績連動型を導入する企業も存在する。 |
| 株式報酬枠 | 既存の報酬枠とは別枠で設定 | ・導入企業の約80%が採用。 ・経済産業省の手引きでも推奨されている。 |
業績連動型RSの先進事例
大半がシンプルな在任条件型である一方、一部の企業は戦略的に業績連動条件を組み込んでいます。
- ユナイテッドアローズ
中期経営計画の目標(連結経常利益、ROE等)の達成度に応じて、3年後に譲渡制限の解除割合を決定する。 - ヤマハ
譲渡制限期間を10年と長期に設定し、複数の業績指標(営業利益率、EPS、ROE)の達成度に応じて解除割合を決定する。不正発生時には株式返還を求めるクローバック条項も導入。 - 富士通
中長期の業績目標に基づき、3年分を一括付与するPSU(パフォーマンス株式ユニット)型を採用。
従業員への拡大
役員報酬改革で培われたノウハウは、従業員向けのインセンティブ制度にも波及しています。従業員エンゲージメントの向上や人材獲得を目的に、従業員向け株式インセンティブ制度を導入する企業は過去10年で3倍以上に増加(2023年時点で915社)。ぴあ株式会社が2017年に正社員全員にRSを付与した例など、役員だけでなく全社的な企業価値向上を目指す動きが広がっています。
6. 今後の展望と課題
RSの普及はゴールではなく、日本企業のガバナンス改革における新たなスタート地点です。今後は、制度の「量」から「質」への転換が求められます。
- 業績連動型インセンティブの拡充
税制改正を契機に、**「目標未達なら報酬ゼロ、達成すれば報酬増」**といったメリハリの利いたPSU等の導入が進むことが期待される。業績指標の選定や目標設定の妥当性について、企業と投資家の対話を通じて洗練させていく必要がある。 - ガバナンス体制の強化
報酬委員会の監督機能の実質的な強化や、報酬体系に関する情報開示の充実が求められる。将来的には、英国や米国で導入されている経営陣の報酬に対する株主の諮問投票(Say on Pay)制度の導入も議論される可能性がある。 - リスク管理の一般化
不祥事発生時に備え、マルス・クローバック条項を標準的な制度として組み込むことが、健全なリスクテイクを促す上で重要となる。 - 人的資本経営との連動
役員だけでなく、従業員全体を株主とすることで、企業と従業員の一体感を醸成し、エンゲージメントや人材定着率の向上につなげる動きが加速する。
RSの普及によって「経営陣も株主である」という状態が常態化し、経営者のオーナーシップ精神が醸成されつつあります。この流れを定着させ、経営者、従業員、株主が共に利益を享受できる持続的な成長モデルを構築していくことが、今後の日本企業に課せられた重要な課題です。
ガイド:Q&A
1. 譲渡制限付株式(RS)とは何か、その基本的な仕組みを説明してください。
譲渡制限付株式(RS)は、一定期間の譲渡制限が付された自社株式を役員や従業員に付与する制度です。付与された者は直ちに株主となり議決権や配当を得られますが、通常3年以上の譲渡制限期間中は株式を売却できず、在任条件などを満たすことで制限が解除されます。
2. 2010年代後半に日本でRSの導入が急速に進んだ背景には、どのような要因がありましたか。主なものを2つ挙げてください。
主な要因として、第一に2015年のコーポレートガバナンス・コードで中長期的な業績向上に向けた株式報酬が推奨されたことが挙げられます。第二に、2016年の税制改正により、会社側で損金算入が可能になるなど税務上の取扱いが整備され、導入のハードルが大幅に下がったことが挙げられます。
3. RSは、それ以前に利用されていたストックオプションと比較して、どのような利点があるとされていますか。
RSは、付与された役員が即時に株主となるため、株価や配当への意識が高まり、株主と同じ目線で経営に取り組むインセンティブが強いとされます。また、ストックオプションに比べて評価算定や行使手続きが不要なため、運用コストが低いという利点もあります。
4. 2015年に導入されたコーポレートガバナンス・コードは、日本の役員報酬改革にどのような影響を与えましたか。
コーポレートガバナンス・コードは、役員報酬について「中長期的な業績やリスクを反映させ、健全な企業家精神を発揮させるインセンティブ付けを行うべき」と明記しました。これにより、従来の固定給中心の報酬体系を見直し、経営陣と株主の利害を一致させるための株式報酬制度の導入を企業に強く促すきっかけとなりました。
5. 2016年の税制改正は、RSの普及にどのように貢献しましたか。具体的な変更点を2つ挙げて説明してください。
2016年の税制改正では、第一に、RSを付与された役員への課税タイミングが付与時から譲渡制限解除時に繰り延べられました。第二に、会社側は譲渡制限が解除された時点で、支給額相当を法人税法上の損金として算入できるようになったため、税務上のメリットが生まれ、制度の導入が加速しました。
6. RSを「長期インセンティブ兼退職報酬」として設計できるのはなぜですか。
譲渡制限の解除条件を「退任時」と設定することで、役員は在任中にわたって株主として企業価値向上へのコミットメントを求められます。さらに、退任時に受け取る株式は税法上の「退職所得」として扱われ、税優遇を受けられるため、実質的に退職金としての機能も果たします。
7. スチュワードシップ・コードは、RS導入の動きにどのように関わっていますか。
スチュワードシップ・コードは、機関投資家に対し、投資先企業との建設的な対話を促す原則です。このコードに基づき、国内外の投資家は企業経営陣の報酬体系を重要な対話テーマとし、株主価値向上と連動する報酬制度、特にRSのような株式報酬の導入を強く求めるようになりました。
8. RSを導入する企業において、譲渡制限期間は一般的にどのくらいの長さに設定されていますか。また、その理由は何ですか。
譲渡制限期間は、一般的に「3年以上」に設定されることが主流です。これは、短期的な売却を防ぎ、経営者に中長期的な視点での企業価値向上に取り組ませるという制度の目的を担保するためであり、主要な機関投資家も3年未満の期間を容認しない傾向があるためです。
9. 日本企業において、業績目標の達成を条件とする「業績連動型RS」の導入が限定的である主な理由を説明してください。
その主な理由は税制上の制約です。業績連動条件が付いたRSは、法人税法上「業績連動給与」と見なされ、原則として損金に算入できないため、企業にとって税負担が重くなります。この税務上の不利が、業績連動型の導入を躊躇させる大きな要因となっています。
10. 役員報酬におけるリスク管理策として注目されている「マルス条項」と「クローバック条項」とは、それぞれどのような制度ですか。
マルス条項は、不祥事などが発覚した場合に、まだ支払われていない未確定の報酬を没収または減額する制度です。一方、クローバック条項はさらに踏み込み、既に支払われた報酬であっても、後から不正や業績の重大な下方修正などが判明した場合に、その返還を求めることができる制度です。
用語集
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 譲渡制限付株式(RS) | 役員や従業員に対し、一定期間の譲渡制限(売却禁止)が付いた自社株式を報酬として付与する制度。付与された者は即時に株主となり、在任などの条件を満たすことで制限が解除される。 |
| リストリクテッド・ストック | 譲渡制限付株式のことで、欧米で広く用いられている株式報酬の一形態。日本のRSはこれを参考に制度設計されている。 |
| 株式報酬型ストックオプション | 権利行使価格を1円など極めて低額に設定したストックオプション。実質的に株式を付与するのと同じ経済的効果を持つため、RS導入以前は退職慰労金の代替などとして利用された。 |
| コーポレートガバナンス・コード(CGコード) | 東京証券取引所が定める上場企業向けの原則集。実効的な企業統治の実現を目的とし、役員報酬における中長期インセンティブや株式報酬の導入を推奨している。 |
| スチュワードシップ・コード | 機関投資家向けの行動原則。投資先企業との建設的な対話(エンゲージメント)を通じて、企業の持続的成長を促す責任を定めており、役員報酬制度の改善要求の背景となっている。 |
| 平成28年度税制改正(2016年) | RSの税務上の取扱いを明確化した改正。役員への課税繰延べと、会社側での損金算入を可能にし、日本でのRS普及の直接的な契機となった。 |
| 業績連動給与 | 役員報酬のうち、利益や株価などの客観的な指標に連動して支給額が決定される部分。現行税制では、業績連動型のRSはこれに該当し、原則として損金不算入となる。 |
| パフォーマンスシェア(PS)/ パフォーマンス株式ユニット(PSU) | 業績目標の達成度に応じて、付与される株式数やユニット数が変動する株式報酬制度。RSに業績条件を付加したもので、より直接的な業績インセンティブを目的とする。 |
| 議決権行使助言会社(プロキシーアドバイザー) | 機関投資家に対し、株主総会の議案に対する賛否の判断材料を提供する専門会社。役員報酬議案についてもガイドラインを設け、その判断が投資家の議決権行使に大きな影響を与える。 |
| マルス条項(Malus) | 「悪化」を意味するラテン語に由来。不正会計や重大な経営判断ミスなどが発覚した場合に、まだ権利が確定していない報酬(株式など)を没収または減額する規定。 |
| クローバック条項(Clawback) | 「取り戻す」の意。不正行為などによって過去の業績が過大に評価されていたことが判明した場合、既に支給済みの報酬であっても会社が返還を要求できる規定。 |
| Say on Pay(経営陣報酬に対する株主の諮問投票) | 株主総会において、経営陣の報酬方針や報酬額について、株主が賛否を表明する投票制度。法的拘束力はないが、経営陣に対する強力なメッセージとなる。 |
| 人的資本経営 | 従業員を「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上を目指す経営のあり方。従業員への株式報酬付与も、その重要な施策の一つと位置づけられている。 |

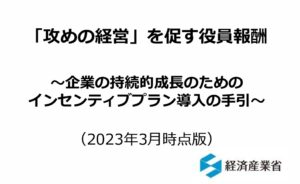
コメント