エグゼクティブサマリー
本記事は、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(以下、PPIHグループ)が開示した2025年6月期の有価証券報告書に基づき、同グループのサステナビリティ戦略、特に気候変動、人的資本、サプライチェーン・マネジメントに関する取り組みを統合的に分析したものである。
PPIHグループのサステナビリティ活動は、企業原理である「顧客最優先主義」と企業理念集『源流』を核心に据えている。事業活動を通じて環境・社会課題を解決することが、最終的に企業価値向上につながるという「好循環の連鎖」を目指すことを基本方針としている。
ガバナンス体制
ガバナンス体制は、代表取締役 兼 専務執行役員CSOがサステナビリティ関連施策を統括し、取締役会が方針策定や重要な取り組みを審議・承認する構造となっている。サステナビリティ委員会やダイバーシティ・マネジメント委員会などの専門組織が、具体的な施策の企画・立案を担う。
戦略の中核には、中長期経営計画「Visionary 2025/2030」と連動して特定された5つの重要課題(マテリアリティ)がある。これらは「環境負荷の低減」「多様性と働きがい」「持続可能な商品調達」「地域社会との共生」「確固たるガバナンス」であり、それぞれに具体的な目標と指標が設定されている。
気候変動対策
特に気候変動対策では、1.5℃および4℃シナリオに基づいた分析を実施し、店舗から排出されるCO₂を2030年までに50%削減(2013年度比)、2050年までに実質ゼロにするという野心的な目標を掲げている。
人的資本経営においては、『源流』の理念である「権限委譲」「実力主義」を基盤に、女性活躍推進(2030年までに女性店長100名)や、店舗運営の要と位置づけるメイト(パート・アルバイト)のMDプランナー登用など、多様な人材の成長と活躍を支援する施策を体系的に展開している。
サプライチェーン
サプライチェーンにおいては、PB/OEM商品の製造委託先工場に対し、第三者CSR監査や自己評価質問票(SAQ)を通じて人権・環境リスクを評価し、課題の改善に向けたフォローアップを継続的に実施している。
これらの取り組みは具体的な数値目標と実績によって管理されており、進捗は定期的に公開されている。一方で、男女間の賃金格差といった課題も認識されており、その要因分析と解消に向けた方針が明確に示されている。総じて、PPIHグループは理念主導型のアプローチとデータに基づく実践を両輪として、サステナビリティ経営を強力に推進している。
解説動画
1. サステナビリティへの統合的アプローチ
1.1. 基本理念:顧客最優先主義と『源流』
PPIHグループのサステナビリティに関する基本的な考え方は、企業原理である「顧客最優先主義」に根差している。総合小売業という本業を通じて地域顧客の暮らしを支え、買い物の楽しみを提供することを第一義とし、その事業活動の中で環境・社会における重要課題(マテリアリティ)の解決に取り組む。
この活動の根幹には、コアバリューとして定められた企業理念集『源流』が存在する。『源流』に示された企業理念・行動指針を徹底し、事業を通じて顧客や社会へ貢献することが最終目的とされている。この貢献が従業員の使命感と誇りを高め、最終的に企業価値向上へとつながる「好循環の連鎖」を創出することを目指している。
1.2. ガバナンス体制
サステナビリティ推進のため、明確な役割分担と監督機能を備えたガバナンス体制が構築されている。
- 統括責任者: 代表取締役 兼 専務執行役員CSOが担当役員として全体を統括する。
- 監督機関: 取締役会がサステナビリティ活動を監督する。方針や目標の策定、重要な取り組みは取締役会で議論・承認され、定期的に活動報告が行われる。
取締役会への主な報告議題(実績・予定)
| 報告年月 | 報告者/組織 | 主な議題 |
| 2024年7月 | 代表取締役 兼 専務執行役員CSO | ESG評価機関からの評価 |
| 2024年10月 | サステナビリティ委員会 | SSBJ気候関連開示基準及びカリフォルニア州法への対応状況報告、環境・サプライチェーン・マネジメント目標に対する進捗報告 |
| 2024年11月 | ダイバーシティ・マネジメント委員会 | 女性活躍推進目標に基づく重点取組 |
| 2025年4月 | 代表取締役 兼 専務執行役員CSO | ESG評価機関からの評価、機関投資家とのエンゲージメント報告 |
| 2025年5月 | ダイバーシティ・マネジメント委員会 | 女性活躍推進目標に基づく重点取組 |
| 2025年6月 | サステナビリティ委員会 | 環境・サプライチェーン・マネジメント目標に対する進捗報告 |
実行組織
以下の委員会および本部が連携し、施策の企画・立案・実行を担う。
- サステナビリティ委員会
リスクマネジメント管掌執行役員を委員長とし、月1回開催。気候変動(TCFD対応)、CO₂排出量削減、サプライチェーン・マネジメント、廃棄物削減などを担当。社外専門家(冨田 秀実氏)からの助言も得ている。 - ダイバーシティ・マネジメント委員会
ダイバーシティ・マネジメント管掌取締役を委員長とし、月1回開催。関連部署が連携し、女性やLGBTQ+など多様な人材の活躍を目指す施策を推進。 - 人財本部・人事労務本部
従業員の採用、育成、労務管理を担当。月2回の会議で人材戦略に関する施策や課題を協議し、重要事項は取締役会に報告。 - リスクマネジメント本部
リスクの予防・対応・再発防止を包括的にマネジメント。 - コンプライアンス委員会
法務・コンプライアンス管掌役員を委員長とし、不正防止やコンプライアンス上のリスク分析・評価を実施。独立社外取締役や外部顧問弁護士も関与する。
1.3. 戦略:マテリアリティの特定
中長期経営計画「Visionary 2025/2030」策定時に、ステークホルダーからの期待と自社の強みを踏まえ、持続可能な社会への貢献と事業成長の両立に向けた重要課題(マテリアリティ)が特定された。
マテリアリティは社会環境の変化に応じて定期的に見直される。
PPIHグループ 重要課題(マテリアリティ)と中期注力領域
| 重要課題(マテリアリティ) | 中期における注力領域 |
|---|---|
| 事業活動で生じる環境負荷の低減 | ・気候変動への対応強化(CO₂排出量の削減、プラスチック使用量の削減等) |
| 多様性の容認と働きがいのある職場づくり | ・人的資本経営の推進(人材育成の強化)<br>・多様性を認め合うダイバーシティ型組織の確立 |
| 持続可能な商品調達と責任ある販売 | ・人権・環境に配慮した商品調達と責任ある販売<br>・サプライチェーンを通じた社会・環境課題の解決 |
| 地域社会との共生による社会課題の解決 | ・地域社会への寄付・募金・貢献活動や次世代支援<br>・日本の農畜水産物 輸出拡大 |
| 確固たるガバナンス | ・コーポレート・ガバナンス強化<br>・リスクマネジメント強化 |
2. 主要テーマ別分析
2.1. 環境:気候変動への対応
気候変動は持続可能な社会の実現に向けた喫緊の課題であり、事業のあらゆる面に影響を及ぼす社会的責任と認識されている。
戦略とシナリオ分析
- 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書等を基に、1.5℃シナリオ(脱炭素社会への移行が急速に進む社会)と4℃シナリオ(物理的リスクが深刻化する社会)に基づいた分析を実施(2025年6月)。
- 分析対象範囲は、売上の8割を占め影響度が相対的に高い「国内店舗運営」および「商品調達」に設定。
- 特定されたリスクと機会に対し、短期・中期・長期の時間軸で財務影響度を評価し、事業継続と機会拡大のための対応策を検討している。
指標・目標と実績
- 目標: 国内店舗から排出されるCO₂排出量(Scope1・2)について、2030年までに50%削減(2013年度比/売上原単位)、2050年までに総量でゼロを掲げる。
- 実績:
▪ 当連結会計年度のScope1・2排出量削減率は32.7%減(2013年度比/売上原単位)となり、目標達成に向けて進捗している。
▪ 電力消費に占める再生可能エネルギー比率は**10.32%**に上昇。
CO₂排出量実績(国内)
| 指標 | 単位 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|---|
| Scope1排出量 | t-CO₂ | 64,228 | 68,530 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | t-CO₂ | 446,025 | 433,236 |
| Scope1・2排出量 合計 | t-CO₂ | 510,253 | 501,766 |
| 電力消費に占める再エネ比率 | % | 8.26% | 10.32% |
| Scope1・2削減率(2013年度比) | % | ▲26.0% | ▲32.7% |
具体的施策
- 再生可能エネルギーの創出・利用: オンサイトCPPAによる再生可能エネルギー導入を拡大(累計27店舗・1拠点)。
- サプライチェーンでの取り組み: 仕入れ商品に関わるGHG排出量データ収集のため、パートナー向け説明会を実施。
- プラスチック使用量の削減: ロールポリ袋の使用抑止POPを国内全店に設置。PB/OEM商品の容器にバイオマス資材を活用。北米やアジアの一部店舗でレジ袋の提供・販売を中止。
2.2. 人的資本:『源流』を基盤とした人材育成とダイバーシティ
「人財」はグループ最大の強みであり、成長の原動力と位置づけられている。理念を体現し、挑戦を続ける活力ある組織づくりが社会的使命であると認識されている。
基本戦略:『源流』実践による人材育成
- 創業以来の「個店経営」を背景に、従業員を信じて任せる「権限委譲」と、成果を公正に評価する「実力主義」、挑戦を促す「失敗への許容」を人材育成の基本方針とする。
- この方針のもと、従業員の自律的な成長を「成長支援」の考え方でサポートする。
- 理念の形骸化を人的資本における主要リスクと捉え、源流推進本部が理念浸透策を推進。
主な人材育成施策
- 理念浸透: 源流研修、源流一般試験(合格率98.7%)、源流伝道士認定試験(合格率23.2%)を国内外で実施。
- 成長支援: 全従業員対象の「キヅキスキルアップセミナー」、社内公募制度「公募.com」、若手向け社内コンペ、経営幹部候補育成プログラム「ミリオンスター制度」などを運用。
- グローバル人材輩出: 海外研修や海外店舗への出向、外国籍従業員向けの多言語対応デジタル研修ツールなどを提供。
ダイバーシティ&インクルージョン
- 女性活躍推進: 店舗顧客の半数以上が女性であることから、女性視点の取り入れを不可欠と考え、2つの目標を設定。
- 目標: 女性店長数を2026年6月期までに50名、2030年6月期までに100名とする。女性社員の離職率を2026年6月期までに8.8%、2030年6月期までに5%にする。
- 実績: 女性店長数は46名、女性社員の離職率は7.3%と、いずれも目標達成に向け順調に進捗。
- 施策: キャリアアップセミナー(参加者の98%がモチベーション向上と回答)、管理職へのレポート配信、意識調査などを実施。
- メイト(パート・アルバイト)活躍: 47,016名のメイトを「店舗運営の要」と位置づけ、活躍を支援。
▪ 目標: メイトのMDプランナーを毎年新規で200名輩出。
▪ 実績: 当期は127名を輩出。研修実施時期の関係で、一部は翌期に計上予定。
▪ 施策: 報酬制度「フォア・ザ・チーム賞」、表彰制度「ベストメイト賞」などを導入。 - 社内環境整備:
▪ 労働環境: 勤怠システムによる労働時間管理の徹底、GLTD保険への加入
▪ 多様性の尊重: 2022年より服装・髪色ルールを緩和。LGBTQ+に関する研修を推進(累計約68,000名が受講)。
▪ 両立支援: 地域限定社員制度、育児休業取得推進、ベビーシッター補助、時短勤務制度(子が小学校卒業まで)、ウェルカムバック採用制度などを整備。
2.3. サプライチェーン・マネジメント
国際的な指針に基づき、PB/OEM商品の製造委託先工場に対するリスクアセスメントを実施し、人権・環境に配慮したサプライチェーンの構築を目指す。
リスクアセスメント手法
- SAQ(自己評価質問票): 取引規模に関わらずリスクの観点で重要と判断した159工場に実施(回収率100%)。
- 第三者CSR監査: リスク管理の観点で特に重要と判断した39工場(国内22、海外17)に実施。
監査結果と課題
- 当連結会計年度末現在、人権・労働に関する重大リスク・インシデントにあたる工場はないことを確認。
- 主な課題:
▪ 第三者CSR監査では、多くの工場で「安全衛生分野」の指摘(消防設備の不備等)が確認された。
▪ SAQでは、児童労働や強制労働の防止に関する方針を策定していない工場が57件確認された。 - 対応:
課題が確認された工場に対し、結果の共有と改善に向けたフォローアップを進めており、評価の低い工場には翌年度に再監査を予定している。
第三者CSR監査 実施結果(工場数)
| 評価 | A (Excellent) | B (Good) | C (Fair) | D (Poor) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 2 | 16 | 2 | 2 | 22 |
| 海外 | 3 | 8 | 6 | 0 | 17 |
| 合計 | 5 | 24 | 8 | 2 | 39 |
3. 定量的データと目標達成状況
3.1. サステナビリティ指標・目標一覧
| テーマ | 指標及び目標 | 実績(当連結会計年度) |
|---|---|---|
| 環境 | CO₂排出量(店舗): 2030年までに50%削減(2013年度比)、2050年までにゼロ | 32.7%減(売上100万円当たり原単位) |
| プラスチック使用量: 2030年までに70%削減(2019年度比) | 約67.0%削減(売上100万円当たり原単位) | |
| 人的資本 | 源流一般試験: 合格率100% | 合格率 98.7% |
| 源流伝道士認定試験: 合格率50% | 合格率 23.2% | |
| メイトのMDプランナー: 毎年新規で200名輩出 | 127名 | |
| 女性店長数: 2026年6月期までに50名、2030年6月期までに100名 | 46名 | |
| 女性社員の離職率: 2026年6月期までに8.8%、2030年6月期までに5% | 7.3% | |
| サプライチェーン | サステナブル調達方針とサプライチェーン行動規範の徹底 | 人権・労働に関する重大リスク・インシデントにあたる工場はなし |
3.2. 従業員データと労使関係
従業員数(2025年6月30日現在)
| 分類 | 従業員数(人) | 臨時雇用者数(人) |
|---|---|---|
| 連結合計 | 17,075 | 47,016 |
| 国内事業 | 11,189 | 43,998 |
| 北米事業 | 3,380 | 2,397 |
| アジア事業 | 2,506 | 621 |
| 提出会社 | 3,580 | 539 |
• 提出会社の状況: 平均年齢42.5才、平均勤続年数16.2年、平均年間給与6,901,515円。
• 労働組合: 提出会社では結成されていない。連結子会社の㈱長崎屋(組合員数4,063名)やユニー㈱(組合員数20,747名)などでは労働組合が結成されており、労使関係は円満に推移している。
3.3. 女性活躍および男女間の賃金格差
主要な連結子会社14社合算のデータ
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) | 男性の育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異(%) |
|---|---|---|
| 16.1 | 50.0 | 全労働者: 58.1 正規雇用: 82.0 パート・有期: 106.2 |
賃金格差の要因分析
- 雇用形態・賃金制度において性別による差異はない。
- 格差の主な要因は、相対的に賃金の低い非正規労働者の7割以上が女性であること、および正規雇用労働者において上級管理職に占める女性比率が低いことと分析されている。
- 差異解消に向けた方針:
昇格者や職位ごとの男女割合を定期的にモニタリングし、引き続き女性のキャリア支援、育成、管理職への登用を進めることで差異の解消を目指す。
4. ビジョナリー・カンパニーの実現に向けた人的資本の重要性
グループが目指す「ビジョナリー・カンパニー」とは、長期的な成長を遂げる企業であり、その実現には『名前(ブランド)』『店』『商品』そして、それら全てを実現するための『人財』という4つのコアバリューが不可欠であると考えています。このビジョンにおいて、主体性を持ち、目標達成への強い執着心で行動する「人財」こそが、当社グループの最大の強みであり、成長の原動力に他なりません。
4.1. 成長の核となる企業理念『源流』の実践
グループの人材育成における根幹的な考え方である企業理念集『源流』の実践について解説します。従業員一人ひとりが自律的に成長し、挑戦できる環境を整えることは、変化の激しい時代において持続的な競争優位性を確立するための最重要戦略です。
『源流』には、私たちの行動の拠り所となる4つの重要な指針が示されています。
- 顧客最優先主義
- 権限委譲
- 実力主義
- 失敗への許容
これらの指針は、創業以来の「個店経営」を支える思想的基盤です。商圏ごとに異なる顧客ニーズへ機動的に対応するため、現場に大胆な裁量を委ねる文化の中で、従業員は自ら「どうすれば上手くいくか」を考え、判断し、挑戦を繰り返してきました。このプロセスを通じて個々の経験やスキルが磨かれ、社会や市場の変化に柔軟かつ迅速に対応できる強固な組織力が培われてきたのです。
この理念を単なるスローガンに終わらせず、組織の隅々にまで浸透させるための具体的な施策を展開しています。
- 研修制度
新卒・中途を問わず、入社時には必ず源流研修を実施し、当社グループの価値観と行動規範の理解を深めます。 - グローバル展開
世界中の従業員が共通の視点を持つことを目的に、『源流』を日本語だけでなく、英語、中国語(簡体字・繁体字)、タイ語にも翻訳し、グローバルでの理念共有を推進しています。 - 定着度測定
国内外の従業員を対象に年2回「源流一般試験」を実施し、理念の理解度を測ります。さらに、一定の職位・職務を担う管理職には「源流伝道士認定試験」を課しています。源流伝道士は、理念を体現し人材育成を実践するだけでなく、合格後も年2回のレポート提出や実践事例の共有会を通じて、常に理念の解釈を深め、その体現レベルを高め続ける責務を担います。
『源流』が示す理念、特に「実力主義」は、具体的な人事評価や後述する成長支援制度と密接に連携しており、従業員の公正な評価と成長機会の創出へとつながっています。
4.2. 実力主義と成長支援による人材育成
従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、企業の持続的成長を支えるための具体的な人事制度設計について詳述します。「教育」ではなく「成長支援」という哲学は、意図的な戦略的選択です。従業員のオーナーシップ精神を醸成するために設計されたプログラムのポートフォリオに投資し、長期的な競争優位性に不可欠な未来のリーダーとイノベーターからなる自己推進的なパイプラインを構築します。
実力主義に基づく公正な評価制度
グループの人事評価は、年齢、性別、国籍といった個人の属性を一切問わず、純粋に仕事の成果と能力に基づいて行われます。半年ごとに実施される評価とフィードバックは、従業員が自身の現在地と課題を客観的に把握する機会となります。この公正な評価に基づき、成長に応じた「大胆な抜擢」を積極的に行うことで、従業員のモチベーションを高め、さらなる挑戦意欲を引き出す好循環を生み出しています。適材適所の人員配置を徹底することで、個々の強みを最大限に活かし、組織全体のパフォーマンス向上につなげることを目指しています。
従業員の自律的な成長を促す支援制度
従業員の「手挙げ・主体性」を尊重し、自らの意志でキャリアを切り拓くための多様な機会を提供しています。
- 自己成長機会の提供
全従業員を対象に、新たな知識やスキルの習得を支援する「キヅキスキルアップセミナー」を随時開催しています。 - キャリア形成支援
社内公募制度「公募.com」を活性化させ、従業員が自らの意志で新たな職務や部署に挑戦できる機会を提供しています。 - 優秀人材の発掘・育成
◦ 若手従業員がマーケティング思考と陳列技術を競う社内コンペティションを実施し、優秀な人材を発掘します。◦ 公募で選ばれた社員が支社長として大規模商圏を統括する「ミリオンスター制度」を通じ、経営幹部候補を育成します。
◦ 外部の専門家の監修のもと、次世代経営幹部育成プログラムを体系的に実施しています。 - イノベーションの創出
未来の成長エンジンを発掘するため、新規事業創出コンテスト「創造的破壊選手権」を開催し、社内からの新たなアイデアを積極的に求めています。
これらの制度を通じて個々の従業員の成長を支援することが、組織全体の多様性を育み、絶え間ないイノベーションを生み出す基盤となると確信しています。
4.3. 多様性の推進とインクルーシブな組織文化の醸成
多様化する顧客ニーズに応え、企業の競争力を高めるために不可欠なダイバーシティ&インクルージョン戦略について解説します。ダイバーシティへのコミットメントは、企業理念『源流』の「顧客最優先主義」を直接的に拡張したものです。多様な顧客層にサービスを提供するためには、まず社内からその多様性を反映し、理解する組織を構築しなければなりません。重要課題(マテリアリティ)の一つとして「多様性の容認と働きがいのある職場づくり」を特定し、すべての従業員がその能力を最大限に発揮できる組織文化の醸成に注力しています。
女性活躍推進
グループの店舗をご利用いただくお客様の半数以上が女性であり、その視点を経営や店舗運営に活かすことは極めて重要な戦略です。女性が活躍できる環境を整えることは、多様性を尊重する組織づくりの第一歩であり、より柔軟で創造的な企業文化の醸成につながると考えています。
【主な取り組み】
- 女性従業員の意識改革を促すキャリアアップセミナーの実施
- 女性部下を持つ管理職への定期的なレポート配信による現状把握と意識向上
- 女性の働き方やキャリアに特化した採用イベントの開催
(補足:労働者の男女の賃金の差異について)
同一労働同一賃金の原則は遵守されていますが、それだけでは十分ではないと認識しており、歴史的な役割分担の偏りから生じる構造的な賃金格差は、真正面から取り組むべき重要な戦略的課題です。この格差の根本原因は、相対的に賃金の低い非正規労働者に女性が多いこと、そして上級管理職層における女性比率の低さにあります。目標は単なる法令遵守に留まらず、才能ある人材のパイプラインを抜本的に改革し、これらの構造的障壁を打破して、上級管理職への道を誰もが平等に歩めるようにすることです。そのために、昇格者の男女比を定期的にモニタリングし、女性のキャリア支援と管理職登用を継続的に推進してまいります。
メイト(パート・アルバイト)の活躍推進
全従業員に占める47,016名のメイトは、地域のお客様を最もよく知る存在であり、「個店経営」を支える上で不可欠な戦力です。メイトを消費者の代表かつ店舗運営の要と位置づけ、その活躍を積極的に支援しています。
【目標と実績】
- 目標: メイトのMDプランナーを毎年新規で200名輩出する。
- 実績: 当期は127名を登用。現在234名が研修中であり、次連結会計年度以降の登用を見込んでいます。
【主な取り組み】
- 店舗の営業成果に応じて報酬を支給する「フォア・ザ・チーム賞」
- 優れた功績をあげたメイトを表彰する「ベストメイト賞」
グローバル人材の輩出
海外店舗網の拡大とインバウンド需要の増加を背景に、グローバルな視点を持つ人材の育成は急務です。海外研修や海外店舗への出向機会を提供するとともに、国内で働く外国籍従業員向けには5言語(英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、ウクライナ語)に対応したデジタル研修ツールを活用し、円滑な業務遂行をサポートしています。
インクルーシブな文化の醸成
多様な個性を認め合う組織風土を醸成するため、具体的な環境整備を進めています。
- 2022年より、従業員の個性を尊重するため服装・髪色ルールを自由化しました。
- 性的マイノリティ(LGBTQ+)の従業員に対し、福利厚生の適用を拡大するとともに、全従業員を対象とした理解促進研修を実施(2021年開始以来、累計約6万8,000名が受講)しています。
多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮するためには、心身の健康を支え、安心して働ける労働環境が不可欠です。次に、その基盤となる具体的な制度について詳述します。
4.4. 働きがいを支える労働環境と支援制度
全従業員が心身ともに健康で、安心してその能力を発揮できるための基盤となる環境整備と具体的な支援制度について解説します。働きがいのある職場づくりは、持続的な企業成長の土台をなす戦略的投資です。
適正な労働時間の管理
勤怠システムを用いて職場と人事部門が連携し、労務管理を徹底することで、過剰な長時間労働の発生を防止しています。残業時間や休暇取得状況を随時モニタリングし、長時間勤務となりうる従業員に対しては、個別の状況確認や必要に応じた産業医・保健師との面談を実施するなど、きめ細かな対応を行っています。
セーフティネットの構築
- 病気やケガによる長期休職時の収入を補償するGLTD(団体長期障害所得補償)保険に加入しており、万一の際にも従業員が安心して療養に専念できる体制を整えています。
- 職場の悩みから健康、家庭の問題まで幅広く相談できる社内外の相談窓口を設置しています。これらの窓口は、メイトを含むすべての従業員が利用可能です。
多様なライフスタイルへの対応
従業員一人ひとりのライフイベントや価値観に寄り添い、柔軟な働き方を支援する制度を導入しています。
- 勤務地を限定して働き続けることができる「地域限定社員制度」
- 育児と仕事の両立を支援するため、ベビーシッター補助制度や、子どもが小学校を卒業するまで利用可能な時短勤務制度を設けています。
- 一度退職した従業員が、その経験やスキルを活かして再び活躍できる機会を提供する「ウェルカムバック採用」制度を運用しています。
これらの戦略や制度が形骸化することなく、確実に実行され、全従業員に届くためには、それを支える強固なガバナンス体制が不可欠です。
4.5. 人的資本戦略の推進体制とガバナンス
上記の人的資本戦略を着実に実行し、継続的に改善していくための組織的な枠組みについて説明します。実効性のあるガバナンスこそが、戦略の成功を左右する鍵となります。
- 主管部署: 「人財本部」および「人事労務本部」が、採用、成長支援、労務管理など人材に関わる各種施策の企画・運営を責任を持って担っています。
- 連携体制: 主管部署は、ダイバーシティ・マネジメントを管掌する取締役 兼 執行役員が委員長を務める「ダイバーシティ・マネジメント委員会」をはじめとする複数の関連部署と横断的に連携しています。月2回の定例会議を通じて、人材戦略に関わる施策や課題を共有し、協議することで、迅速かつ効果的な意思決定を可能にしています。
- 監督・報告体制: 人材に関する重要事項は、都度、取締役会へ報告され、経営レベルでの適切な監督を受けています。これにより、人的資本戦略が経営戦略と一体となって推進される体制を確保しています。
戦略の進捗と成果を客観的に評価し、継続的な改善につなげていくためには、適切な指標を用いたモニタリングが不可欠です。
4.6. 主要指標と今後の展望
人的資本戦略の進捗を測定し、今後の方向性を定めるための主要な指標と、将来に向けた目標は以下の通りです。
| 指標 | 目標 | 当連結会計年度実績 |
|---|---|---|
| 源流一般試験 合格率 | 100% | 98.7% |
| 源流伝道士認定試験 合格率 | 50% | 23.2% |
| メイトのMDプランナー 輩出数 | 毎年新規200名 | 127名 |
| 女性店長数 | 100名(2030年6月期) | 46名 |
| 女性社員の離職率 | 5%(2030年6月期) | 7.3% |
これらの指標を継続的にモニタリングし、その結果を真摯に分析することで、戦略の有効性を検証していきます。そして、社会環境や事業の変化に柔軟に対応しながら、人的資本戦略を常に進化させていきます。
音声解説(詳細:19分)
ガイド:Q&A
問1: PPIHグループのサステナビリティに関する基本的な考え方の中心にある企業原理と、その最終目的は何ですか?
中心にある企業原理は「顧客最優先主義」です。この原理のもと、本業を通じて環境・社会課題の解決に取り組み、顧客や社会へ貢献することが最終目的とされています。これは結果として従業員の使命感を高め、企業価値向上につながる好循環を生み出すと考えられています。
問2: サステナビリティ推進におけるガバナンス体制について、CSO(最高サステナビリティ責任者)と取締役会はそれぞれどのような役割を担っていますか?
CSOは代表取締役 兼 専務執行役員が務め、サステナビリティ推進の各施策を企画・立案する各委員会や本部を統括します。取締役会は、CSOや各委員会から定期的に活動報告を受け、方針や目標の策定、重要な取組について議論・承認を行い、サステナビリティ活動全体を監督します。
問3: サステナビリティ委員会はどのような目的で設置され、どのような課題に取り組んでいますか?
サステナビリティ委員会は、リスクマネジメント管掌執行役員を委員長とし、月に1回開催されます。気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への対応、CO₂排出量削減、人権・環境に配慮したサプライチェーン・マネジメントの構築、プラスチック及び廃棄物削減といった重要課題に取り組んでいます。
問4: PPIHグループが掲げる、店舗から排出されるCO₂排出量に関する2030年と2050年の目標を具体的に述べてください。
店舗から排出されるCO₂排出量について、2030年までに50%削減(2013年度比、売上100万円当たりの原単位)することを目標としています。さらに、2050年までには総量でゼロにすることを目指しています。
問5: PPIHグループの人材育成における基本方針は、「教育」ではなく「成長支援」であるとされています。この考え方はどのようなものですか?
「成長支援」とは、従業員を信じて任せる「権限委譲」と「実力主義」のもと、自律的に成長し挑戦できる環境を整えるという考え方です。従業員自らが手を挙げ参加できる研修や公募制度などを通じ、主体性を尊重して挑戦機会を提供し、成長に必要な知見を支援することに重点を置いています。
問6: 「源流伝道士」とはどのような役割を持つ社員であり、認定後にはどのような活動が求められますか?
「源流伝道士」とは、企業理念集『源流』の教えを深く理解・実践し、各組織で理念や文化の実現に貢献する人材育成を担う社員です。認定後は、年に2回レポートを提出し、自身の実践事例を他の伝道士と共有することで、さらなるレベルアップを図ることが求められます。
問7: PPIHグループがサプライチェーンにおける人権・環境リスクを評価するために実施している主な手法を2つ挙げてください。
主な手法は、PB/OEM商品の製造委託先工場に対するSAQ(自己評価質問票)によるリスクアセスメントと、第三者機関によるCSR監査です。SAQはリスクの観点で重要と判断した工場に、CSR監査は取引規模や所在国などを考慮し特に重要と判断した工場に実施されます。
問8: 気候変動のシナリオ分析において、なぜ「1.5℃シナリオ」と「4℃シナリオ」という両極端なシナリオが採用されたのですか?
中間的なシナリオのみを想定して対策を練ることは戦略的ではないためです。両極端なシナリオ(脱炭素社会への移行が進む1.5℃と、気候変動の物理的影響が深刻化する4℃)に対する対策を講じることで、その間のどの結果に収まった場合でも対処しやすくなると考えられています。
問9: 当連結会計年度における第三者CSR監査の結果、特に多くの工場で指摘された課題分野と、「D評価」となった工場で確認された課題は何でしたか?
多くの工場で指摘されたのは「安全衛生」分野の課題でした。「D評価」となった工場でも、消防設備の不備など安全衛生や労務管理といった分野での課題が確認されました。
問10: 連結子会社の正規雇用労働者において男女間の賃金差異が生じている主な要因は何であると説明されていますか?
正規雇用労働者における賃金差異の主な要因は、女性管理職の登用は進んでいるものの、上級管理職に占める女性比率が低いことであると説明されています。この差異を解消するため、昇格者や職位ごとの男女割合のモニタリングや、女性のキャリア支援・育成を継続する方針です。
9. パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスで働く際に調べておきたいこと
- PPIHグループのサステナビリティ戦略について論じなさい。その際、企業原理「顧客最優先主義」がマテリアリティ(重要課題)の特定とガバナンス体制にどのように関連しているかを具体的に説明すること。
- PPIHグループの人的資本戦略における企業理念集『源流』の役割と、その浸透に向けた具体的な取り組みについて説明しなさい。また、「メイト」や女性社員など、多様な人材の活躍を促進するためにどのような施策が講じられているか詳述すること。
- PPIHグループの気候変動への対応について分析しなさい。ガバナンス体制、リスク管理、シナリオ分析(1.5℃と4℃)、そしてScope1・2排出量削減に関する具体的な目標と進捗状況を含めて論じること。
- PPIHグループが構築を目指す「人権・環境に配慮したサプライチェーン・マネジメント」について説明しなさい。SAQや第三者CSR監査といったリスク評価手法、その結果明らかになった課題、そしてそれらに対する今後の対応策について具体的に記述すること。
- PPIHグループにおけるダイバーシティ&インクルージョンの現状、特に女性活躍推進に関する課題を考察しなさい。女性店長数の目標や男女間の賃金差異の背景、そしてこれらの課題解決に向けた企業の取り組みについて論じること。
用語集
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 企業原理「顧客最優先主義」 | PPIHグループの経営の根幹をなす考え方。サステナビリティにおいても、この原理のもと、事業活動を通じて顧客や社会へ貢献することを最終目的としている。 |
| マテリアリティ(重要課題) | ステークホルダーの期待・重要性と、企業の強みを活かして解決に貢献できる環境・社会課題を議論し特定したもの。環境負荷低減、多様性、持続可能な調達、地域社会との共生、ガバナンスの5つが挙げられている。 |
| 『源流』 | PPIHグループの企業理念集。企業理念・行動指針が定められており、サステナビリティや人材育成の基本的な考え方の核となっている。「権限委譲」「実力主義」「失敗への許容」といった文化の源泉。 |
| CSO (Chief Sustainability Officer) | 最高サステナビリティ責任者。代表取締役 兼 専務執行役員が務め、サステナビリティの取組を推進する各施策を統括する。 |
| サステナビリティ委員会 | リスクマネジメント管掌執行役員を委員長とする、月1回開催される委員会。気候変動対応、CO₂削減、サプライチェーン管理、廃棄物削減などに取り組む。社外委員の専門的知見も活用している。 |
| ダイバーシティ・マネジメント委員会 | ダイバーシティ・マネジメントを管掌する取締役 兼 執行役員を委員長とする、月1回開催される委員会。女性やLGBTQ+など多様な人材の活躍を目指す施策を企画・実行する。 |
| TCFD | 気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)。PPIHグループはTCFDの提言に基づき、気候変動に関するリスクと機会の情報を開示している。 |
| メイト | PPIHグループにおけるパート・アルバイト従業員の呼称。地域や顧客を熟知した店舗運営の要と位置づけられ、MDプランナーへの登用など活躍推進策が講じられている。 |
| MDプランナー | 商品の仕入れや売り場づくりなど、マーチャンダイジングの計画を担う職務。メイトから毎年200名を新規で輩出する目標が設定されている。 |
| 源流伝道士 | 『源流』の教えを深く理解・実践し、所属組織で理念浸透や人材育成を担う役割を持つ社員。認定試験に合格する必要があり、合格後もレポート提出などが課される。 |
| 1.5℃シナリオ | 今世紀末までの世界の平均気温上昇を1.5℃に抑えることを想定した社会。脱炭素社会への移行に伴う政策や規制(移行リスク)が事業に影響を及ぼす可能性が高い。 |
| 4℃シナリオ | 今世紀末までの世界の平均気温が4℃上昇することを想定した社会。地球温暖化による異常気象など(物理的リスク)が事業に影響を及ぼす可能性が高い。 |
| Scope1排出量 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出量(例:燃料の燃焼)。 |
| Scope2排出量 | 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出量。 |
| SAQ (自己評価質問票) | Supplier Self-Assessment Questionnaire。PB/OEM商品の製造委託先工場に送付し、人権・環境などに関する取り組みを自己評価してもらう調査手法。 |
| 第三者CSR監査 | 独立した第三者機関が、製造委託先工場の人権・労働環境・安全衛生などを客観的に評価する監査。PPIHグループではリスクが高いと判断した工場に実施している。 |
| ビジョナリー・カンパニー | 長期的に成長を遂げる企業。PPIHグループは、「名前」「店」「商品」「人財」の4つのコアバリューがその実現に不可欠と考えている。 |
| 権限委譲 | 現場の従業員に大胆な裁量を委ねること。『源流』に示される経営理念の一つで、従業員の挑戦を促し、組織力を高める源泉となっている。 |
| 個店経営 | 店舗ごとに商品の仕入れや売り方を決定する経営手法。商圏ごとの顧客ニーズに機動的に対応するためのPPIHグループの特色。 |
| UAゼンセン | ㈱長崎屋およびユニー㈱の労働組合が加盟している上部団体。 |
| GLTD保険 | 長期障害所得補償保険(Group Long Term Disability)。従業員が病気やケガで長期間働けなくなった際の収入を補償する保険で、福利厚生として導入されている。 |
| ウェルカムバック採用(アルムナイ採用) | 一度退職した人材に対し、再びグループ内で活躍する機会を提供する採用制度。 |
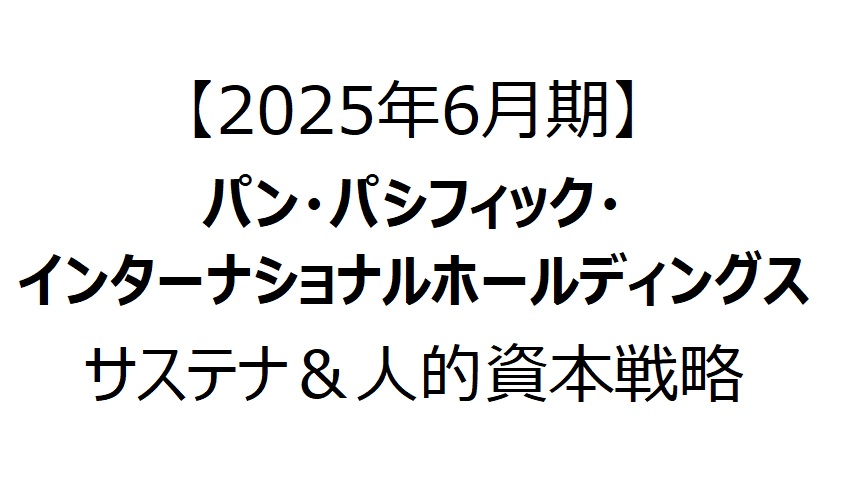
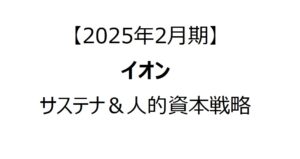
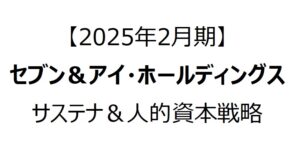
コメント