要旨
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除及び給与所得控除が引き上げられ、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。これらの改正は令和7年分の所得税から適用されるが、その施行は令和7年12月1日であるため、実務上の対応は段階的に行われます。
令和7年1月から11月までの月々の給与計算における源泉徴収事務は、従来通りの「改正前」の税額表を用いて行われます。全ての改正内容は、同年12月に行われる年末調整の際に一括して精算される。この精算により、基礎控除や給与所得控除の増額分が反映され、多くの給与所得者において例年より還付額(過納額)が増加することが見込まれます。
また、新設される「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の扶養親族が一定の所得を有する場合に適用されるもので、年末調整で適用を受けるには「特定親族特別控除申告書」の提出が必要となります。
令和8年1月以降は、改正を反映した新しい「令和8年分 源泉徴収税額表」が使用され、月々の源泉徴収税額の計算方法も変更されます。給与事務担当者は、これらの変更点を正確に理解し、従業員への周知と適切な事務処理を行う必要があります。
解説動画(約9分)
I. 令和7年度税制改正の主要な概要
源泉徴収事務に関連する主な改正項目は、①基礎控除の引き上げ、②給与所得控除の引き上げ、③特定親族特別控除の創設であり、これらに伴い扶養親族等の所得要件や各種申告書の様式も変更されます。
1. 基礎控除の引き上げ
納税者本人の合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。特に、合計所得金額が2,350万円以下の層で控除額が10万円引き上げられ、所得水準に応じた特例加算措置が講じられた結果、控除額は5段階となりました。
合計所得金額別の基礎控除額(改正前後比較)
| 納税者本人の合計所得金額 | 改正前 | 改正後 | 備考 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 改正なし |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 改正なし |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 改正なし |
| 655万円超 2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | |
| 489万円超 655万円以下 | 48万円 | 63万円 | 令和7・8年分限定加算額 5万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 48万円 | 68万円 | 令和7・8年分限定加算額 10万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 48万円 | 88万円 | 令和7・8年分限定加算額 30万円 |
| 85万円超 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 加算額 37万円 |
| 85万円以下 | 48万円 | 95万円 |
- 適用開始
令和7年分以後の所得税について適用。施行は令和7年12月1日。 - 特例加算
改正後の控除額は、所得税法上の基礎控除額58万円に、租税特別措置法による特例加算額を加算した額となる。この加算は居住者のみに適用される。
2. 給与所得控除の最低保障額引き上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ10万円引き上げられた。この改正は令和7年分以後の所得税に適用されます。
給与等の収入金額別の給与所得控除額(改正前後比較)
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 | 備考 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 195万円(上限) | 改正なし |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 | |
| 162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 | |
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
- この改正に伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び「源泉徴収税額表」が改正されます。
3. 特定親族特別控除の創設
大学⽣年代の⼦を持つ世帯の税負担を軽減するため、従来の特定扶養控除(合計所得金額58万円以下)に加え、子の合計所得金額が58万円を超えても段階的に控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。
- 対象者(特定親族)
居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者。 - 適用要件
控除を受ける居住者は、年末調整時に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要がある。
特定親族の合計所得金額に応じた控除額
| 親族の合計所得金額 | 収入が給与のみの場合 | 控除額 | 控除の名称 |
| 58万円以下 | 123万円以下 | 63万円 | 特定扶養親族の扶養控除額 |
| 58万円超 85万円以下 | 123万円超 150万円以下 | 63万円 | 特定親族特別控除額 |
| 85万円超 90万円以下 | 150万円超 155万円以下 | 61万円 | |
| 90万円超 95万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 51万円 | |
| 95万円超 100万円以下 | 160万円超 165万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超 105万円以下 | 165万円超 170万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 170万円超 175万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超 115万円以下 | 175万円超 180万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超 120万円以下 | 180万円超 185万円以下 | 6万円 | |
| 120万円超 123万円以下 | 185万円超 188万円以下 | 3万円 | |
| 123万円超 | 188万円超 | 0円 | 控除対象外 |
4. 関連する改正事項
扶養親族等の所得要件引き上げ
基礎控除の改正に伴い、扶養親族や同一生計配偶者等の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
所得要件の改正前後比較
| 扶養親族等の区分 | 改正後の要件 | 改正前の要件 |
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) | 48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 58万円超 133万円以下 | 48万円超 133万円以下 |
| 勤労学生 | 85万円以下 (給与収入150万円以下) | 75万円以下 (給与収入130万円以下) |
「源泉控除対象親族」の新設(令和8年分以降)
令和8年1月以降、毎月の源泉徴収税額計算に特定親族特別控除の一部を加味するため、「源泉控除対象親族」という概念が導入されます。これは従来の控除対象扶養親族に、特定親族のうち合計所得金額が100万円以下の者を加えたものです。
各種様式の改正
- 給与所得の源泉徴収票: 特定親族の人数を記載する「特親」欄及び「特定親族特別控除の額」の項目が新設される。
- 各種申告書: 「特定親族特別控除申告書」が創設され、基礎控除申告書等との兼用様式となる。
II. 令和7年分における源泉徴収・年末調整の実務
令和7年分の源泉徴収事務は、年内で取り扱いが大きく変わるため注意が必要です。
1. 事務手続きのタイムライン
- 令和7年1月~11月
毎月の給与計算では、改正前の源泉徴収税額表を使用する。この期間、事務手続きに特段の変更は生じない。 - 令和7年12月(年末調整時)
年末調整において、改正後の基礎控除額、給与所得控除額、特定親族特別控除額を適用して年間の所得税額を再計算する。この計算結果と、1年間に徴収した源泉徴収税額(改正前の基準で計算)との差額を精算(還付または徴収)する。 - 給与の支払日が年をまたぐ場合
給与計算の対象期間ではなく、「支給日ベース」で適用関係を判断する。例えば、12月25日支給の給与は令和7年分として年末調整の対象となり、翌年1月25日支給の給与は令和8年分として改正後の税額表で源泉徴収を行う。
2. 年末調整における留意点
- 従業員への周知
改正内容、特に所得要件の緩和により新たに扶養控除等の対象となる家族がいないか、従業員に確認を促すことが望ましい。年収2,000万円超で年末調整の対象外となる従業員に対しても、改正内容を周知することが推奨される。 - 申告書の事前提出
実務上、12月1日以降に年末調整関係書類を回収するのは困難なため、施行日前の11月中から改正内容を反映した申告書を提出してもらうことは差し支えない。 - 扶養控除等申告書の再提出
改正により新たに扶養控除等の対象となる親族ができた従業員は、「扶養控除等(異動)申告書」を再提出する必要がある。その際、「異動月日及び事由」欄に「令和7年12月1日改正」などと記載する。 - 過納額の増加への備え
11月までは改正前の高い税率で源泉徴収し、年末調整で控除額が増えるため、例年より還付額(過納額)が大幅に増加することが想定される。還付しきれない場合は、翌月以降の納付税額と相殺するか、「年末調整過納額還付請求書」を税務署に提出して還付を受けることができる。 - 源泉徴収簿への対応
国税庁提供の「令和7年分 給与所得に対する源泉徴収簿」は特定親族特別控除に対応していないため、適用がある場合は余白に控除額を追記するなど手作業での対応が必要となる。
III. 「特定親族特別控除」に関する詳細な論点
新設される控除であるため、実務上の判断に迷う点が複数存在します。
1. 適用対象と判定日
特定親族に該当するかどうかの判定は、原則としてその年の12月31日の現況による。ただし、以下の例外があります。
| ケース | 年齢要件の判定日 | 所得要件の判定基準 |
| 通常の年末調整 | 12月31日の現況 | 申告書提出日の現況による見積額 |
| 年の中途で死亡・出国 | 死亡時・出国時の現況 | 死亡時・出国時の現況による見積額 |
| 特定親族が年中に死亡 | 死亡時の現況 | 死亡時の現況による所得 |
2. 重複適用の可否
- 原則
一人の特定親族について、控除を適用できるのは2人以上の居住者(例:両親)がいる場合でも、いずれか1人のみ。 - 例外(重複適用が可能なケース)
共働き夫婦の一方(例:夫)が年の中途で死亡または出国した場合、判定日が異なるため、夫婦の両方で控除を受けられる可能性がある。- 夫: 死亡時または出国時の現況で特定親族に該当すれば、準確定申告等で控除を適用。
- 妻: 年末(12月31日)の現況で特定親族に該当すれば、年末調整または確定申告で控除を適用。
- 出国時期による手続きの違い:
- 令和7年11月30日までに出国: 施行日前の出国であるため、出国時の準確定申告では控除を適用できない。施行日(12月1日)以降に更正の請求を行うことで適用を受ける。
- 令和7年12月1日以降に出国: 施行日後のため、出国時の準確定申告等で控除を適用できる。
3. 見積額の誤りと源泉徴収義務者の責任
年末調整において、従業員が提出した申告書に基づき控除額を計算するが、特定親族の所得の見積額が誤っており、結果として控除が過大になる(源泉所得税の納付不足が生じる)ケースが想定されます。
この場合、国税通則法の事務運営指針により、「扶養控除等申告書等に基づいてした控除が過大であった場合において、その申告書に基づき控除したことにつき源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由があると認められないとき」は、不納付加算税の対象外となる「正当な理由がある場合」に該当する。新設される特定親族特別控除申告書もこの「申告書等」に含まれるため、会社側にペナルティが課されることは基本的にない。
IV. 令和8年分以降の源泉徴収事務
1. 新しい源泉徴収税額表の使用
令和8年1月1日以降に支払う給与については、改正後の「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用します。 ただし、この税額表に織り込まれている基礎控除額は58万円のみであり、所得に応じた特例加算部分(5万円〜37万円)は反映されていません。したがって、この特例加算については、引き続き年末調整または確定申告で精算することになるります。
2. 「源泉控除対象親族」に基づく計算
令和8年分以降、毎月の源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」は、従来の「控除対象扶養親族」に代わり、「源泉控除対象親族」の数を基に算定される。これにより、特定親族特別控除の一部が月々の源泉徴収に反映されることになる。
V. その他の留意事項
通勤手当の非課税限度額改正の可能性
令和7年8月の人事院勧告により、自動車等を使用する者に対する通勤手当の額の引き上げが勧告されました。
これを受けて所得税の非課税限度額が改正される場合、年末調整での対応が必要になる可能性があります。年末調整を実施する前には、国税庁ホームページ等で最新情報を確認する必要があります。
音声動画(約18分)
ガイド:Q&A
1. 令和7年度税制改正は、令和7年分の給与計算にどのように適用されますか?
令和7年1月から11月までは改正前の源泉徴収税額表に基づき源泉徴収を行い、12月の年末調整の際に改正後の控除額を適用して精算します。改正は令和7年12月1日に施行されるため、令和8年1月以降の給与からは改正後の税額表が使用されます。
2. 基礎控除は令和7年度改正でどのように変更されましたか?
納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額が引き上げられました。例えば、合計所得金額が2,350万円以下の納税者の基礎控除額は、原則として10万円引き上げられ58万円となり、さらに所得水準に応じて特例措置による加算が行われ、58万円から最大95万円までの5段階の控除額が設定されました。
3. 給与所得控除の改正内容について説明してください。
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。この改正は令和7年分以後の所得税に適用され、給与等の収入金額が162.5万円以下の場合は一律で65万円の控除となります。
4. 新たに創設された「特定親族特別控除」とはどのような制度ですか?
年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の「特定親族」を有する居住者が受けられる所得控除です。控除額は特定親族の合計所得金額に応じて、最大63万円から3万円まで段階的に逓減する仕組みとなっています。
5. 従業員が年末調整で「特定親族特別控除」の適用を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?
その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。この申告書は、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書との兼用様式となっています。
6. 令和8年分の源泉徴収から導入される「源泉控除対象親族」とは何ですか?
毎月の源泉徴収税額の計算に特定親族特別控除を加味するために設けられた区分です。「控除対象扶養親族」と、合計所得金額が58万円超100万円以下の「特定親族」を合わせたもので、令和8年分以後の扶養控除等申告書に記載され、税額計算の際の「扶養親族等の数」の算定基礎となります。
7. 特定親族に該当するかどうかの判定は、原則としていつの時点の状況で行われますか?例外的なケースもあれば挙げてください。
原則として、その年の12月31日の現況で判定します。ただし、親等が年末調整で適用を受ける場合の所得要件は「申告書の提出日の現況の見積額」で、親等が年の中途で死亡または出国した場合は「死亡時または出国時の現況」で判定します。
8. 共働き世帯において、1人の子について夫婦両方が特定親族特別控除を適用できるのはどのような場合ですか?
原則として夫婦のいずれか一方しか適用できませんが、例外として、夫婦の一方が年の中途で死亡または出国した場合には、夫婦両方で適用できるケースがあります。これは、出国・死亡した親と国内に残る親とで、特定親族の判定基準日が異なるために生じます。
9. 従業員が提出した申告書の子の所得見積額に誤りがあり、控除額が過大になった場合、会社(源泉徴収義務者)はペナルティを課されますか?
いいえ、原則としてペナルティ(不納付加算税)の対象外となります。従業員から提出された申告書に基づいて控除を行ったことについて、源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由がない場合は、「正当な理由があると認められる場合」に該当するためです。
10. 基礎控除と給与所得控除の改正に伴い、「扶養親族」の所得要件はどのように変わりましたか?
合計所得金額の要件が、改正前の48万円以下から改正後の58万円以下に引き上げられました。これにより、収入が給与だけの場合、扶養親族に該当する年収の上限は103万円以下から123万円以下に変わりました。
主要用語集
| 用語 | 説明 |
| 年末調整 | 毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額と、その年の給与総額について計算した年税額との差額を精算する手続き。 |
| 源泉徴収 | 給与や報酬などを支払う者(源泉徴収義務者)が、その支払いの際に所得税を天引きし、国に納付する制度。 |
| 基礎控除 | すべての納税者に適用される所得控除。令和7年度改正により、合計所得金額に応じて58万円から95万円の5段階となった。 |
| 給与所得控除 | 給与所得者が給与収入から差し引くことができる控除。令和7年度改正で最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた。 |
| 特定親族特別控除 | 年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を有する居住者が受けられる所得控除。控除額は特定親族の所得に応じて変動する。 |
| 特定親族 | 居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者。 |
| 扶養親族 | 居住者と生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円以下の者(改正後)。 |
| 控除対象扶養親族 | 扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の者。 |
| 源泉控除対象親族 | 令和8年分以後の源泉徴収税額計算に用いる区分。控除対象扶養親族、および年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額58万円超100万円以下の親族を指す。 |
| 合計所得金額 | 各種所得の金額を合計した金額(純損失や雑損失の繰越控除を適用する前の金額)。各種控除の適用判定に用いられる。 |
| 給与所得者の特定親族特別控除申告書 | 年末調整で特定親族特別控除の適用を受けるために、給与の支払者に提出する書類。基礎控除申告書等との兼用様式。 |
| 準確定申告 | 年の中途で死亡した人や出国する人が行う確定申告。 |
| 不納付加算税 | 源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合に課されるペナルティ税。 |



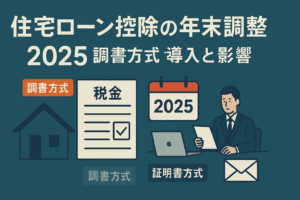
コメント