エグゼクティブサマリー
本記事は、「人的資本可視化指針」で提示された主要な概念と提言を統合し、その核心を解説するものである。企業の競争優位の源泉が有形資産から人的資本を含む無形資産へと移行する現代において、人的資本への戦略的投資とその可視化は、持続的な企業価値向上のための不可欠な要素となっている。
最重要ポイント
- 認識の転換: 人的資本は単なる「費用」ではなく、企業の競争優位性と持続的成長を駆動する「戦略的投資」である。多くの投資家は、この認識に基づき、経営者による人材戦略の明確な説明を求めている。
- 可視化の目的: 人的資本の可視化は、単なる情報開示に留まらない。経営戦略と連動した人材戦略をステークホルダーに伝え、経営者、投資家、従業員間の相互理解を深め、中長期的な企業価値向上を実現するための循環的プロセスの中核をなす。
- 核心的アプローチ「統合的ストーリー」: 効果的な可視化の基盤は、自社の経営戦略と人的資本への投資・人材戦略の関係性を明確にする「統合的なストーリー」を構築することにある。この構築には、「価値協創ガイダンス」や「IIRCフレームワーク」の活用が推奨される。
- 推奨される開示フレームワーク: 構築したストーリーを開示する際には、投資家にとって馴染みやすく、国際的にも受け入れられている「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4要素に沿って情報を整理することが効果的かつ効率的である。
- 開示事項の2類型: 開示内容は、自社のビジネスモデルに根差した「独自性のある取組・指標」と、他社との比較を可能にする「比較可能性の観点から期待される事項」の2つに大別される。両者のバランスを確保することが重要である。
- 参照すべき重要文書: 本指針は、具体的な人材戦略の策定・実践について詳述した「人材版伊藤レポート」および「人材版伊藤レポート2.0」と併用することで、相乗効果が期待される。
解説動画(簡略版:約8分)
1. 人的資本可視化の重要性と背景
1.1. 競争優位の源泉としての人的資本
企業の競争優位の源泉や持続的な企業価値向上の推進力は、有形資産から無形資産(人的資本、知的資本、ビジネスモデル等)へと大きくシフトしている。この中で「人的資本」は、人材が教育、研修、業務経験を通じて能力や意欲を向上させ、価値創造の源泉となる「資本」として捉えられる。
人的資本への投資は、競合に対する参入障壁を形成し、企業価値に直結する戦略的投資であるとの認識が、企業と投資家の双方で広がりつつある。
1.2. 投資家からの高まる期待
今日、多くの投資家は、企業が将来の成長を確保するためにどのような人材を必要とし、具体的にどのような取り組みを行っているかについて、経営者からの直接的な説明を期待している。彼らは、人的資本への投資が、社会のサステナビリティと企業の成長・収益性を両立させる「サステナビリティ経営」の観点からも極めて重要であると認識している。
1.3. 可視化を通じた好循環の創出
人的資本の可視化は、企業が自社の投資や戦略を投資家や市場に分かりやすく伝え、相互理解を深めるための不可欠な手段である。この可視化を通じて、以下のような循環的なプロセスを構築することが求められる。
- 人材戦略の構築: 経営者による議論とコミットメント、従業員との対話を通じて、経営戦略と連動した人材戦略を策定する。
- 人的資本の可視化: 策定した人材戦略を、本指針で示すアプローチに沿って開示する。
- フィードバックによる磨き上げ: 投資家等との対話やエンゲージメントから得られるフィードバックを踏まえ、経営戦略・人材戦略をさらに洗練させる。
このサイクルを回すことで、企業と人が共に成長し、価値を創造する力強い流れを生み出すことができる。
2. 可視化の核心的アプローチ:統合的ストーリーの構築
人的資本の可視化は、単に関連する非財務情報を羅列することでは意味をなさない。競争力強化や企業価値向上に繋げるためには、まず自社の経営戦略と人的資本への投資や人材戦略の関係性を物語る「統合的なストーリー」を構築することが不可欠である。
2.1. 推奨されるフレームワークの活用
この統合的ストーリーを構築する上で、原則主義に基づき企業価値の関連要素を整理した以下のフレームワークの活用が効果的である。
- 価値協創ガイダンス
企業の価値観、長期ビジョン、ビジネスモデル、リスクと機会といった各要素と、人的資本への投資・人材戦略がどのように結びついているかを論理的に関連付けるのに有効である。 - IIRC(国際統合報告評議会)フレームワーク
人的資本を含む6つの資本が、ビジネスモデルを通じてどのように価値を創造・保存・毀損するのかを統合的に説明するための国際的な概念フレームワークであり、有益な示唆を与える。
これらのフレームワークは相互補完的に活用可能であり、自社の経営戦略と人材戦略を統合した、説得力のあるストーリーを構築するための強固な基盤となる。
3. 効果的な開示のための4要素フレームワーク
構築した「統合的なストーリー」を具体的な開示内容に落とし込む際には、気候関連情報開示(TCFD提言)で推奨され、資本市場で広く受け入れられている以下の4要素に沿って情報を整理することが効率的である。
| 要素 | 人的資本における内容 |
| ガバナンス | 人的資本に関連するリスク及び機会に関する組織のガバナンス(例:取締役会による監督体制、経営者の役割) |
| 戦略 | 人的資本に関連するリスク及び機会が、組織のビジネス・戦略・財務計画へ及ぼす影響 |
| リスク管理 | 人的資本に関連するリスク及び機会を識別・評価・管理するためのプロセス |
| 指標と目標 | 人的資本に関連するリスク及び機会の評価・管理に用いる指標と目標 |
この構造は、有価証券報告書に新設されたサステナビリティ情報の記載欄でも採用されており、これに沿って検討を進めることは合理的である。英国財務報告評議会(FRC)の報告書は、各要素で検討すべき具体的な問いを提示しており、参考となる。
4. 開示事項の検討:2つの類型と留意点
具体的な開示事項を検討する際には、以下の2つの類型を意識し、そのバランスを確保することが重要である。
4.1. 開示事項の2類型
- ① 自社固有の戦略やビジネスモデルに沿った独自性のある取組・指標・目標
- 他社との比較可能性よりも、自社の経営戦略との関連性、その指標を重要と考える理由(Why)、自社独自の定義、進捗度などの説明が重視される。
- 開示事項自体が他社と共通でも、それを選んだ理由に独自性がある場合(「Whyの独自性」)もこれに含まれる。
- ② 比較可能性の観点から開示が期待される事項
- 国内外の開示基準(ISO30414、WEF、SASB、GRI等)で示されている、投資家が企業間比較に用いる典型的な情報。
- 制度開示で求められる項目は最低限の前提となる。
- これらの事項についても、可能な限り自社の戦略やリスクマネジメントと紐付けて説明することが望ましい。
4.2. 検討における留意点
- 「価値向上」と「リスクマネジメント」の観点
開示事項には、企業価値向上に向けた戦略的取組を示す「価値向上」の側面と、企業価値を毀損するリスクへの対応を示す「リスクマネジメント」の側面がある。例えば、「育成」は価値向上に力点が置かれる一方、「ダイバーシティ」や「健康・安全」は価値向上とリスク管理の両方の観点を含む。開示の目的を明確にすることが求められる。 - ステップ・バイ・ステップでの開示
最初から完璧な開示を目指す必要はない。「できるところから開示」を始め、投資家等からのフィードバックを受けて人材戦略と開示内容を継続的に改善していくアプローチが望ましい。
5. 可視化に向けた実践的ステップ
効果的な可視化を実現するためには、以下の循環的なプロセスや体制を構築することが重要である。
5.1. ① 基盤・体制確立編
- トップのコミットメント: 経営トップが人材戦略とその可視化にコミットし、自らの言葉で積極的に発信する。
- 取締役会・経営層レベルの議論: 経営戦略と一体で人的資本について議論を深める。
- 従業員との対話: 戦略の実効性を高めるため、従業員の共感を得る「内なる可視化」を推進する。
- 部門間の連携: 人事、経営企画、IR、サステナビリティ、財務等の関連部門が横断的に連携する体制を構築する。
- 情報基盤の構築: 重要な指標をモニターし、DXやテクノロジーを活用してデータ収集・分析の基盤を整備する。
5.2. ② 可視化戦略構築編
- 統合的ストーリーの検討: 「価値協創ガイダンス」等を活用し、経営戦略と人材戦略の関連性を明確化する。
- 「人材版伊藤レポート」の参照: 具体的な人材戦略の検討において、「3つの視点・5つの共通要素」を参考にする。
- 4要素の検討: 「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」のフレームワークに沿って開示内容を具体化する。
- 企業価値向上とのつながりの分析(逆ツリー分析): ROEやROIC等の財務指標を分解し、人的資本への投資(インプット)がどのような成果(アウトプット、アウトカム)を通じて企業価値向上に繋がるかのロジックを可視化する。
6. 開示媒体の戦略的活用と制度対応
6.1. 有価証券報告書における対応
金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(2022年6月)により、有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄が新設される方針が示された。具体的には、以下の開示が求められることとなった。
- 戦略: 「人材育成方針」「社内環境整備方針」
- 指標と目標: 上記方針と整合的な測定可能指標、目標、進捗状況
- 従業員の状況: 「男女間賃金格差」「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」
企業には、これらの制度要請に対し、自社の「統合的なストーリー」に基づいた積極的な開示が期待される。
6.2. 任意開示の戦略的活用
有価証券報告書を補完し、より多角的な情報を様々なステークホルダーに提供するため、以下の任意開示媒体を戦略的に活用することが重要である。
- 統合報告書
- サステナビリティレポート
- 中期経営計画
- IRウェブサイト 等
これらの媒体を通じて、有価証券報告書と整合性を保ちつつ、より詳細な情報や背景を発信し、対話の機会を創出することが望ましい。特に、プライム市場上場企業を中心に、グローバルな投資家との対話を促進するため、英文開示の重要性が増している。
7. 詳細解説動画(約26分)
8. ガイド:Q&A
1. 本指針における「人的資本」はどのように定義されていますか?
本指針では、「人的資本」を、人材が教育や業務を通じて能力や経験を向上・蓄積することで価値創造に資する存在であり、価値を創造する源泉である「資本」としての性質に着目した表現と定義しています。事業環境の変化や経営戦略の転換に伴い、内外から登用・確保されるものとされています。
2. なぜ今、「人的資本の可視化」が不可欠だと考えられているのですか?
企業の競争優位の源泉が無形資産へと移行する中、多くの投資家が人材戦略に関する経営者からの説明を期待しているためです。可視化は、経営者、投資家、従業員といったステークホルダー間の相互理解を深め、戦略的な人的資本投資を加速させ、中長期的な企業価値向上を実現するために不可欠とされています。
3. 人的資本の情報を開示する際に推奨されている4つの構成要素とは何ですか?
推奨されている4つの構成要素は、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」です。これは気候関連情報の開示フレームワークであるTCFD提言で推奨されて以来、資本市場で広く受け入れられている構成であり、投資家にとって馴染みやすい開示構造とされています。
4. 本指針と「人材版伊藤レポート」は、それぞれどのような役割を担っており、両者を併用することでどのような効果が期待できますか?
「人材版伊藤レポート」が可視化の前提となる「人材戦略」の策定・実践について提言しているのに対し、本指針は特に資本市場への「人的資本の情報開示(可視化)」のあり方に焦点を当てています。両者を併せて活用することで、人材戦略の実践(人的資本への投資)とその可視化の相乗効果が期待できます。
5. 人的資本の開示事項は、どのような2つの類型に整理されますか?それぞれの特徴を説明してください。
開示事項は、「①自社固有の戦略やビジネスモデルに沿った独自性のある取組・指標・目標」と「②比較可能性の観点から開示が期待される事項」の2つに整理されます。①は経営戦略との関連性や理由の説明が重視される一方、②は国内外の開示基準を参考に、企業間比較が可能な形で開示することが期待されます。
6. 企業の経営戦略と人材戦略の関係性を「統合的なストーリー」として構築するために、本指針が活用を推奨している2つのフレームワークは何ですか?
推奨されているフレームワークは、「価値協創ガイダンス」と「IIRC(国際統合報告評議会)のフレームワーク」です。これらは、企業の価値創造プロセスや各資本(人的資本を含む)とビジネスモデルの関係性を整理し、経営戦略と人材戦略を統合的に説明する上で効果的です。
7. 人的資本開示における「ステップ・バイ・ステップでの開示」アプローチとはどのようなものですか?
最初から完璧な開示を目指すのではなく、まずは「できるところから開示」を始め、そのフィードバックを受けながら人材戦略や開示内容を継続的に改善していく循環的なアプローチです。この方法により、開示の遅れや内容の充実をためらうことなく、段階的に可視化を進めることが望ましいとされています。
8. 「逆ツリー分析」とはどのような分析手法で、人的資本の可視化においてどのような有益性がありますか?
ROEやROICといった資本効率指標を要素分解し、それらを改善するための戦略・施策やKPIと紐付ける分析手法です。人的資本への投資が、どのように財務指標の改善や企業価値向上につながるかという関連性やロジックを説得的に示すことができ、投資家の理解を深める上で有益です。
9. 可視化の準備段階における「基盤・体制確立編」で重要とされる取り組みの例を3つ挙げてください。
重要な取り組みとして、「トップのコミットメント」「取締役会・経営層レベルの議論」「部門間の連携」が挙げられます。(その他、「従業員との対話」「人的資本指標のモニターと情報基盤の構築」「バリューチェーンにおける取引先等との連携」なども含まれます。)
10. 日本の労働市場の特性を踏まえ、海外投資家に対してリスキルの重要性を説明する際に、どのような点を強調する必要がありますか?
単なる社内異動ではなく、自社に不足する新しい分野のプロフェッショナルを育てるための戦略的投資であることを強調する必要があります。また、外部人材の採用・活用と組み合わせつつ社内人材を活用することが、特に日本全体の労働市場で不足している人材を確保する上で効果的かつ不可欠な打ち手であることを説得的に説明することが求められます。
9. 用語集
| 用語 | 定義 |
| 人的資本 (Human Capital) | 人材が教育、研修、日々の業務等を通じて自己の能力や経験、意欲を向上・蓄積することで付加価値創造に資する存在であり、価値を創造する源泉である「資本」としての性質に着目した表現。 |
| 人的資本の可視化 (Visualization of Human Capital) | 企業・経営者が自社の人的資本への投資や人材戦略のあり方を、投資家や資本市場に対して分かりやすく伝えていくこと。 |
| サステナビリティ経営 (Sustainability Management) | 社会のサステナビリティと企業の成長・収益力の両立を図る経営。人的資本への戦略的投資はその重要な要素とされる。 |
| 統合的なストーリー (Integrated Story) | 自社の経営戦略と、人的資本への投資や人材戦略との関係性を、明瞭かつロジカルに描いたもの。投資家との建設的な対話につながる。 |
| 人材版伊藤レポート (Ito Report for Human Resources) | 持続的な企業価値向上に向けた人材戦略のあり方について提言したレポート(2020年9月公表)。「3つの視点・5つの共通要素」を整理している。本指針と併用することで相乗効果が期待される。 |
| 人材版伊藤レポート2.0 (Ito Report for Human Resources 2.0) | 「人材版伊藤レポート」の枠組みを具体化し、実行に移すためのアイディアの引き出しを提示したレポート(2022年5月公表)。 |
| 価値協創ガイダンス (Value Co-creation Guidance) | 企業価値に関連する要素を統合的に整理し、人的資本への投資や人材戦略と経営戦略を関連付けるためのフレームワーク。企業と投資家の対話の手引きとして編集されている。 |
| IIRCフレームワーク (IIRC Framework) | 国際統合報告評議会(IIRC)が策定した、人的資本を含む6つの資本とビジネスモデルとの関係を整理し、企業価値へのつながりを説明するための国際的な概念フレームワーク。 |
| TCFD提言 (TCFD Recommendations) | 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)による提言。「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4要素での開示を推奨し、資本市場で広く受け入れられている。 |
| 独自性のある開示 (Disclosure with Uniqueness) | 自社固有の戦略やビジネスモデルに沿った取組・指標・目標に関する開示。ビジネスモデルとの関連性や、当該事項を重要だと考える理由などの説明が重視される。 |
| 比較可能性 (Comparability) | 投資家が企業間比較を行うために、国内外の開示基準等を参考に、定義や算定方法に配慮して行われる開示。 |
| 逆ツリー分析 (Reverse Tree Analysis) | ROE(自己資本利益率)やROIC(投下資本利益率)などの財務指標を要素分解し、各要素と経営戦略・施策、KPIを紐付ける分析手法。人的資本投資と企業価値向上のつながりを説得的に示す上で有益。 |
| 従業員エンゲージメント (Employee Engagement) | 従業員の企業に対する貢献意欲や、仕事への熱意・没頭度合いを示す指標。企業価値向上につながる要素として重視される。 |
| リスキル (Reskilling) | 従業員が既存のスキルとは異なる、新しい分野のスキルや知識を習得すること。事業ポートフォリオの転換やDX推進において重要となる戦略的投資。 |
| FRC(英国財務報告評議会)報告書 | 従業員に関する企業報告についてまとめた英国の報告書。「ガバナンスと経営」「ビジネスモデルと戦略」「リスク管理」「指標と目標」の項目で、投資家のニーズや企業に推奨される開示事項を解説している。 |
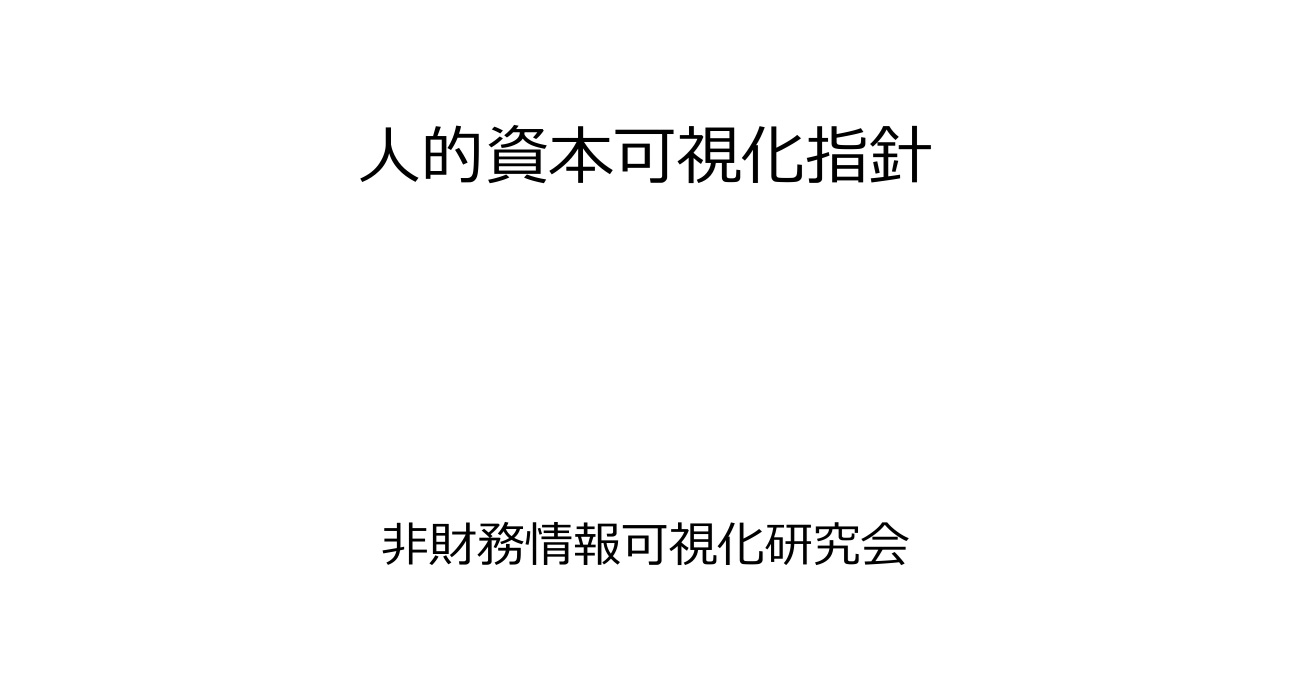

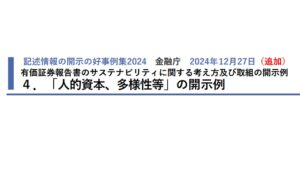
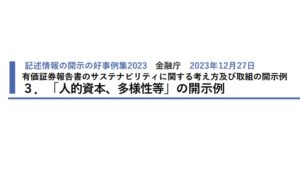
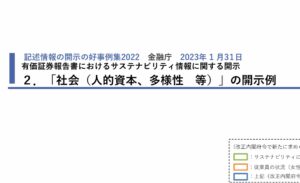
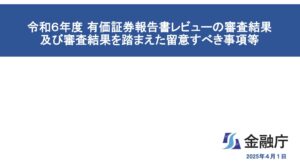
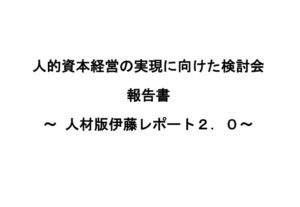
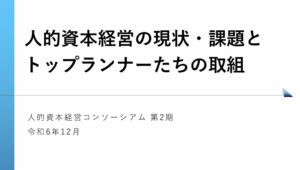
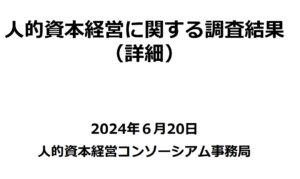
コメント