エグゼクティブサマリー
「人的資本経営の現状・課題とトップランナーたちの取組(人的資本経営コンソーシアム 第2期/令和6年12月)」は、人的資本経営コンソーシアム第2期の活動成果として、日本企業における人的資本経営の現状、共通課題、そして先進企業の取組を統合的に分析したものである。2024年に実施された調査からは、2022年比で日本企業の人的資本経営が全体的に進展していることが確認された。しかし、その深化には依然として構造的な課題が存在する。
日本企業に共通する3つの重要課題
特に、以下の3点が日本企業に共通する重要課題として浮上している。
- 取締役会の役割
多くの企業で人的資本に関する議論が行われているものの、経営戦略と連動した実質的な監督・モニタリング機能の発揮や、結果を踏まえた見直しといったPDCAサイクルの確立には至っていない。 - KPI設定・現状とのギャップ把握
半数以上の企業がKPI設定に取り組んでいる一方で、その取組が具体的な成果創出に繋がったと認識している企業はわずか3.4%に留まる。経営戦略と直結したKPIの策定と、As is-To beギャップの定量的な把握・活用が急務である。 - 人事部門のケイパビリティ
CHROの設置は進展しているが、人事部門が従来の制度運用の守り手から脱却し、事業と並走する変革のドライバーへと転換するプロセスが成果に結びついていない。
これらの課題に対し、トップランナー企業は、経営戦略と人材戦略を不可分なものと捉え、自社の文脈に合わせたKPI設定、ジョブ型人事制度の導入、多様性を活かすための具体的な施策、そしてステークホルダーへの説得力を持つストーリー性のある情報開示を強力に推進している。
結論として、人的資本経営の本質は、単なる人事改革ではなく「経営改革」そのものである。経営トップが主導し、人材を「コスト」から「資本」へとパラダイム転換させ、取締役会が実効性あるガバナンスを発揮し、人事部門が事業部門と一体となって戦略を実行する体制の構築こそが、持続的な企業価値向上の鍵となる。
動画解説
1. 日本の人的資本経営の現在地
1.1. 人的資本経営への注目とパラダイム転換
企業価値向上の源泉が設備などの有形資産から人的資本などの無形資産へと移行する中、日本企業は大きな転換期を迎えている。かつて競争力の源泉とされた長期雇用を前提とする「日本型雇用システム」は、時代の変化と共に人材をコストと捉える傾向を生み、企業の成長余力を削ぐ一因となった。
この状況に一石を投じたのが「人的資本経営」である。これは、人材を消費される「資源」ではなく、適切な投資によって価値が増大する「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上を目指す経営の在り方である。2020年の「人材版伊藤レポート」以降、この考え方は社会的なムーブメントとなり、企業と個人の関係性を、相互依存から互いに成長し「選び、選ばれる関係」へと転換させることを促している。
このムーブメントを確かなものにするため、2022年8月に「人的資本経営コンソーシアム」が設立された。設立当初320者だった会員企業数は600者を超え、企業のCHRO(最高人事責任者)が集い、好事例の共有や課題の深掘りを通じて、日本企業における人的資本経営の実践と開示を両面から促進している。
1.2. 2024年調査から見る進捗と課題
コンソーシアムは、会員企業579者(当時)を対象に調査を実施(回答261件)し、日本企業の人的資本経営の現在地を定量的に把握した。2022年に経済産業省が実施した調査と比較分析した結果、以下の進捗と課題が明らかになった。
全体的な進展
2022年調査と比較し、全ての評価項目においてスコアが「高い」または「同じ」であり、日本企業における人的資本経営が着実に進展していることが示された。特に、「経営戦略との連動」「リスキルの機会提供」「投資家との対話」などの項目でスコアの向上が見られた。
浮き彫りになった3つの主要課題
一方で、多くの企業で取組の進捗が芳しくなく、共通の課題となっている項目も特定された。これらは、多くの企業が対応策を検討・実行する段階(スコア3)にはあるものの、成果創出や継続的な改善(スコア5, 6)には至っていないことを示唆している。
| 課題項目 | 現状分析 |
| 取締役会の役割 | 取締役会の役割明確化や体制構築に取り組む企業は半数を超えるが、その結果を踏まえ必要な見直しを実施している企業は3割程度に留まる。形式的な議論に終始せず、実効性のある監督機能の発揮が求められる。 |
| KPI設定・現状とのギャップ把握 | KPI設定とギャップ把握に取り組む企業は57.0%にのぼるが、その取組が成果創出に繋がったと考える企業はわずか3.4%である。経営戦略と紐づいた実効性のあるKPI設定と、その活用が極めて大きな課題となっている。 |
| 人事部門のケイパビリティ向上 | CHROの設置や経営トップとの連携強化に取り組む企業は6割を超えるが、これらの取組が実際の成果創出に繋がったと考える企業は1割程度である。人事部門の機能変革が、企業全体の価値向上に結びついていない実態がうかがえる。 |
2. 主要課題への対応策とトップランナー事例
2.1. 課題①:取締役会の役割強化
現状と論点
取締役会は、経営戦略の実現可能性という観点から、人材戦略を承認し、その実行を監督・モニタリングする重要な役割を担う。調査では、半数近くの企業で人的資本に関する議論が定期的には行われておらず、特にCxOサクセッションプランや、より裾野の広い経営人材育成の監督が課題となっている。議論の形式化を防ぎ、実質的なガバナンス機能へと深化させることが不可欠である。
事例分析
- アステラス製薬株式会社
取締役会が「組織健全性目標」の達成に責任を持つ。役員報酬の算定指標にエンゲージメントスコアなどの人的資本指標を設定し、取締役会で定期的にモニタリングとアクションプランを議論する。後継者育成に関しても、CEOだけでなくCFOやCMOなどCxOポジション全体を対象とし、候補者の強みや育成計画を具体的に議論することで、監督機能の実効性を担保している。 - 出光興産株式会社
取締役会の年間スケジュールに人的資本経営の審議を計画的に組み込み、議論の形骸化を防ぐ。役付執行役員のサクセッションプランは、①社内役員で構成する「人事委員会」、②社外取締役中心の「指名・報酬諮問委員会」、③「取締役会」の3段階で審議を進めることで、全社的視点とガバナンス上の透明性を両立させている。
2.2. 課題②:成果に繋がるKPI設定とギャップ把握
現状と論点
経営戦略からバックキャストで人材面の課題を特定し、目指すべき姿(To be)を定量的なKPIで設定、現状(As is)とのギャップを埋める戦略こそが人的資本経営の核となる。しかし調査では、多くの企業が人材ポートフォリオの定義や、自社にとって重要な人的資本情報の特定に苦慮しており、KPI設定が成果に結びついていない。他社の動向に流されず、自社の戦略に直結したKPIを策定し、その進捗を経営に活かす仕組みが求められる。
事例分析
- 株式会社日立製作所
経営戦略(例:Lumada事業の拡大)から人材戦略(例:デジタル人財の確保・育成)、人的資本KPI(例:デジタル人財数)までをツリー構造で整理。これにより、「なぜ」「何を」「どうやって」取り組むかが明確になり、戦略の連動性を高めている。 - 日清食品ホールディングス株式会社
「組織人材ポリシー」を策定し、その実現度を測るKPIを設定。KPIは、必ずやり遂げるべき「コミットメント目標」と、将来的に目指すべき「ターゲット目標」の2段階で定義。現状に満足せず、より高みを目指すための原動力としている。 - 三井住友トラストグループ株式会社
社員の「Well-being」を人的資本戦略の基軸に据え、①健康経営、②エンゲージメント、③組織力、④人材力の4要素でKPIを設定。この一貫したストーリーと、背景や課題認識まで含めた透明性の高い情報開示は、投資家から高く評価されている。 - セイコーエプソン株式会社
「強化領域への重点配置」「人材育成強化」「組織活性化」の3つの人材戦略軸に基づきKPIを設定。過去の実績値も併せて開示することで、取組の進捗を時系列で示し、説得力を高めている。 - 日本電信電話株式会社 (NTT)
中期経営戦略の柱の一つに「従業員体験(EX)の高度化」を掲げ、取組の柱→施策と結果指標→最終的なアウトカム(事業収益向上など)を体系的に整理。人事・経営企画・財務・IR部門が連携し、一貫したストーリーで情報開示を行っている。
2.3. 課題③:人事部門のケイパビリティ変革
現状と論点
人事部門には、従来の制度運用・管理といったオペレーション業務から脱却し、経営戦略の実現を人材の側面から推進する「変革のドライバー」としての役割が求められる。調査では、半数以上の企業が人事部門の「企画機能の不足」を課題として挙げており、HRBP(HRビジネスパートナー)の設置や事業部門との人材交流といった、事業と人事を繋ぐ取組が十分に進んでいない。
事例分析
- 日本電気株式会社 (NEC)
ジョブ型人材マネジメント導入を機に、人事部門を「ピープル&カルチャー部門」へ改称。事業部門の変革を推進する「HRBP」、変革をサポートする「HRコンサルタント」、オペレーションを担う「SSC」、グループ全体の育成・変革を担う「CoE」が三位一体で機能する体制を構築し、経営と人事の同期化を実現している。 - 株式会社ベネッセホールディングス
人事部門の役割を、事業部門の「支援」から「併走・推進」へと再定義。HRBPや人材開発機能を強化し、職種ごとの人材ポートフォリオの最適化を事業部門と一体で推進。これにより、事業計画のアジェンダに「組織能力」が追加されるなど、事業部門の人材に対する意識改革も進んだ。
3. 先進的テーマ別取組
3.1. 経営戦略と人材戦略の連動
調査では7割以上の企業が取り組んでいるが、その質が問われる。先進企業は、組織構造や独自のフレームワークを通じて連動性を担保している。
- 株式会社荏原製作所
「対面市場」別のカンパニー制へ移行し、顧客起点で組織と人材戦略を連動。全社で必要なスキルを定義した「技術元素表」を共通言語とし、経営戦略と人材ポートフォリオを双方向で結びつけている。 - 日揮ホールディングス株式会社
人材に関する8つの重点プロジェクトを「船中八策」として定義。社長直下のHRM委員会のもとに、各事業会社の副社長クラスで構成される「HRO会議」を設置し、グループ全体での戦略実行を強力に推進している。 - 株式会社メルカリ
「Go Bold(大胆にやろう)」など3つのバリューが経営・人事のあらゆる意思決定の根幹。報酬制度もバリューの発揮度合いに連動させ、社員の行動をミッション実現へと方向付けている。
3.2. 実効性を高めるリスキリング・学び直し
7割以上が取り組むものの、成果を感じる企業は2割未満というギャップが存在する。成果を出す企業は、社員のキャリア自律を前提とし、処遇やキャリアパスとの連動を明確にしている。
- 中外製薬株式会社
ジョブ型人事を導入し、社員が目指すポジションと現状のギャップを可視化。社員が自律的にスキルを更新し続ける「Future Skilling」という考え方を提唱し、チャレンジアサイン制度や留職プログラムなどで挑戦を後押ししている。 - 富士通株式会社
事業ポートフォリオの変革から逆算し、必要な人材ポートフォリオを定義。全営業職約8,000名を対象としたビジネスプロデューサーへの変革など、大規模なリスキリング計画を経営主導で実行。社員の自律的な学びを支える「FUJITSU Career Ownership Program」も整備している。
3.3. イノベーションを生む多様な知・経験の活用 (DE&I)
約6割が取り組むが、成果創出に繋がった企業は1割に留まる。トップランナーは、属性の多様性だけでなく、多様な知見が事業成果に結びつくための具体的な施策を講じている。
- アステラス製薬株式会社
海外従業員比率が約7割という環境下で、「グローバル規模での適所適材」を徹底。国籍や性別を問わない登用を進める一方、日本においては無意識バイアスへの気づきを促すなど、地域ごとの課題に合わせたDE&I施策を展開している。 - 出光興産株式会社
事業構造転換の障害となる「部門の縦割り」「井の中の蛙」「安定化志向」という”3つの壁”を、多様な人材の活躍によって打破することを目指す。キャリアデザイン部の設置や社内副業制度など、多様なキャリア機会を提供している。 - 大成建設株式会社
建設業界の特性を踏まえ、「男性を巻き込む」DE&Iを推進。男性の育休取得率100%を目標に掲げるほか、社員のヒアリングから浮かび上がった「介護」という共通課題に焦点を当て、性別を問わない両立支援に注力している。
3.4. 企業価値を高める人的資本情報の開示
2023年からの開示義務化を受け、4割近くの企業が他社にはない独自の内容を開示している。開示は、投資家との対話促進だけでなく、経営層の意識改革にも繋がっている。
- SCSK株式会社
「Well-Being経営」を軸とした価値創造ストーリーを明確にし、有価証券報告書と統合報告書で定性・定量の両面から詳細に開示。良い点・悪い点に関わらず実態を正しく伝えるという方針を貫いている。 - 株式会社北國フィナンシャルホールディングス
地域のクオリティ向上というパーパスに基づき、「人材エコシステム(採用・育成・活躍・輩出)」という独自のフレームワークで開示。自社の人事改革の歩みを経営戦略の変遷と連動させて時系列で示すなど、ユニークな開示を行っている。
4. 結論:経営改革としての人材戦略
人的資本経営コンソーシアムの活動と本調査を通じて、日本企業の人的資本経営は新たなフェーズに入ったことが明らかになった。多くの企業がその重要性を認識し、具体的な施策に着手している。
しかし、本質的な変革はこれからである。
トップランナーたちの取組が示すように、成功の鍵は、人的資本経営を単なる人事施策の集積ではなく、経営戦略と一体となった「経営改革」として捉えることにある。自社のパーパスと経営戦略に基づき、どのような人材が企業価値創造の原動力となるのかを定義し、その獲得・育成・活躍を促す仕組みを構築し、その進捗をステークホルダーに説得力をもって語ること。この一連のサイクルを経営陣が主導して回し続けることこそが、全ての企業に求められている。
5. ガイド:Q&A
1. 本レポートで説明されている「人的資本経営」の基本的な考え方とは何ですか?
「人的資本経営」とは、人材をコストとして消費される「資源」ではなく、投資によって価値が向上する「資本」として捉える考え方です。その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値の向上につなげる経営のあり方を指します。これは単なる人事課題ではなく、経営課題そのものであると強調されています。
2. 2024年の調査で明らかになった、日本企業が人的資本経営を実践する上での3つの主要な課題は何ですか?
2024年の調査結果から特に注視すべき課題として、「取締役会の役割」「KPI設定・現状とのギャップ把握」「人事部門のケイパビリティ向上」の3点が挙げられています。これらの項目は、多くの企業が対応策を検討している段階(スコア3)に留まっており、実践と成果創出に課題があることが示唆されています。
3. 人的資本経営のフレームワークである「3P・5Fモデル」について説明してください。
「3P・5Fモデル」は、人材戦略を整理するためのフレームワークです。「3つの視点(3P)」は①経営戦略と人材戦略の連動、②As is‐To be ギャップの定量把握、③企業文化への定着を指します。また、「5つの共通要素(5F)」は①動的な人材ポートフォリオ、②知・経験のダイバーシティ&インクルージョン、③リスキル・学び直し、④従業員エンゲージメント、⑤時間や場所にとらわれない働き方を指します。
4. 人的資本経営において、取締役会にはどのような役割が期待されていますか?
取締役会は、経営戦略の実現可能性という観点から、経営陣が策定した人材戦略を承認し、その実行を監督・モニタリングする役割を担います。具体的には、CxOの後継者計画(サクセッションプラン)や経営に不可欠な人材パイプラインの充足状況、企業文化の醸成などを監督することが求められます。
5. レポートによると、「選び、選ばれる関係」という言葉は何を意味していますか?
「選び、選ばれる関係」とは、従来の終身雇用を前提とした企業と個人の相互依存関係からの脱却を意味します。個人は自律的なキャリア形成の観点から働く企業を選び続け、企業も自社の戦略実現に必要な人材を獲得・育成するために魅力を訴求し続けるという、対等で成長し合える関係性を指します。
6. 人的資本経営において、KPI(重要業績評価指標)の設定と「As is-To beギャップ」の把握が重要視される理由は何ですか?
KPIの設定と「As is-To beギャップ」の把握は、経営戦略と人材戦略の連動性を測るために不可欠です。目指すべき姿(To be)を定量的なKPIで設定し、現状(As is)とのギャップを把握することで、戦略の進捗を客観的に評価し、ギャップを埋めるための具体的な施策を計画・実行することが可能になります。
7. 「ジョブ型人事」は、本レポートの文脈においてどのような重要性を持っていますか?
「ジョブ型人事」は、職務内容に基づいて人材を評価・配置する制度であり、企業間の人材流動性を高める可能性があります。これにより、個人は自らの専門性やキャリアプランに合う企業を選びやすくなり、企業も戦略に必要な専門人材を外部から獲得しやすくなるため、「選び、選ばれる関係」の構築を促進します。
8. 「人的資本経営コンソーシアム」は、どのような目的で設立され、どのような活動を行っていますか?
「人的資本経営コンソーシアム」は、日本企業における人的資本経営を「実践」と「開示」の両面から促進することを目的として設立されました。活動として、先進事例の共有や企業間協力の議論を行う「実践分科会」や「開示分科会」、会員企業と投資家との対話の場などを設置しています。
9. 2022年と2024年の調査結果を比較して、日本企業の人的資本経営にはどのような進展が見られましたか?
2022年調査と比較して、2024年調査では全ての項目においてスコアが「高い」か「同じ」であり、日本企業の人的資本経営に進展が見られました。特に「経営戦略との連動」「投資家との対話」「従業員との対話」などの項目でスコアが向上しており、多くの企業で取組が進んでいることが示されました。
10. レポートでは、人事部門の役割がどのように変化すべきだと述べられていますか?
人事部門は、従来の人事諸制度の運用・改善を目的とする「制度の守り人」から、経営戦略と連動した人材戦略を策定・実行する「変革のドライバー」へと役割を変化させる必要があります。事業部門のパートナー(HRBP)として、事業課題に即した人材施策を立案・推進するケイパビリティが求められます。
6. 用語集
| 用語 | 説明 |
| 人的資本経営 | 人材をコスト(資源)ではなく、投資によって価値が向上する「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方。 |
| 人的資本経営コンソーシアム | 日本企業における人的資本経営を実践と開示の両面から促進することを目的に、2022年8月に設立された団体。先進事例の共有、企業間協力の議論、国内外の情報収集・発信などを行う。 |
| 人材版伊藤レポート / 2.0 | 経済産業省が公表した、人的資本経営の考え方や実践に向けたアイデアを示す報告書。「人材版伊藤レポート」(2020年)で基本的な考え方を示し、「2.0」(2022年)で具体的なアイデアを紹介している。 |
| 3P・5Fモデル | 人材戦略を俯瞰するためのフレームワーク。「3つの視点(Perspectives)」と「5つの共通要素(Common Factors)」から構成される。 |
| 経営戦略と人材戦略の連動 | 企業の経営戦略を実現するために、どのような人材が必要かを定義し、その獲得・育成・配置を行う人材戦略を策定・実行すること。人的資本経営の根幹をなす考え方。 |
| CHRO | Chief Human Resource Officer(最高人事責任者)。経営陣の一員として、経営戦略と連動した人材戦略の策定・実行を主導する役職。 |
| As is – To beギャップ | 人材戦略における現状の姿(As is)と、目指すべき姿(To be)との差分のこと。このギャップを定量的に把握し、埋めるための戦略を立てることが重要とされる。 |
| ジョブ型人事 | 職務(ジョブ)の内容や責任範囲を明確に定義し、その職務を遂行する能力や成果に基づいて評価・処遇を決定する人事制度。専門性の高い人材の獲得や、適所適材の配置に有効とされる。 |
| リスキリング・学び直し | 事業環境の急速な変化に対応するため、従業員が今後必要とされる新たなスキルや専門性を習得すること。企業の持続的成長と個人の自律的キャリア形成の両面で重要となる。 |
| ダイバーシティ&インクルージョン(D&I) | 性別、国籍、年齢といった属性だけでなく、経験、感性、価値観などの多様性(ダイバーシティ)を尊重し、組織の意思決定や価値創造に活かす(インクルージョン)こと。イノベーション創出の源泉とされる。 |
| 従業員エンゲージメント | 従業員が自社のパーパスや経営戦略に共感し、仕事への誇りややりがいを感じ、自発的に貢献しようとする意欲のこと。企業価値向上のための重要な指標の一つ。 |
| サクセッションプラン | 経営トップや重要ポジションの後継者育成計画のこと。取締役会がその策定・運用を監督・モニタリングすることが求められる。 |
| HRBP | Human Resource Business Partnerの略。事業部門のパートナーとして、事業戦略の実現を人事面から支援する役割を担う人事担当者。 |
| 有価証券報告書への人的資本の開示義務化 | 2023年3月期決算から、有価証券報告書において「人材育成方針」や「女性管理職比率」「男女間賃金格差」などの人的資本に関する情報の開示が義務付けられた制度。 |
| 選び、選ばれる関係 | 企業と個人が相互に依存する関係から脱却し、個人は自律的なキャリアの観点から企業を選び、企業は戦略実現のために個人を選び、互いに成長し合う対等な関係のこと。 |
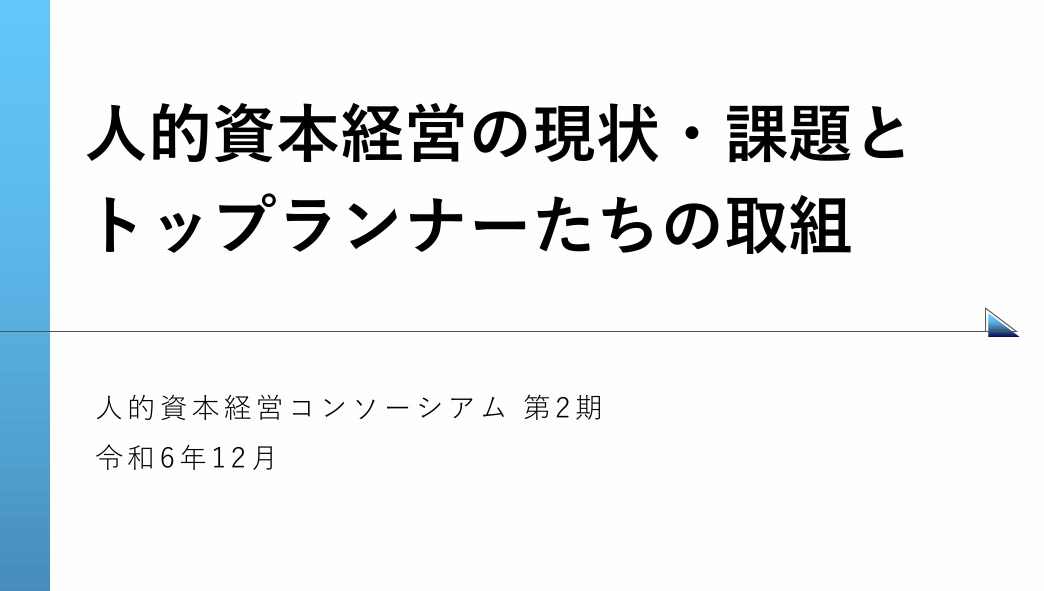

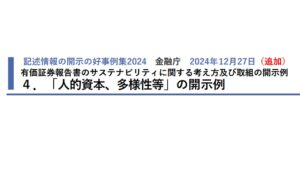
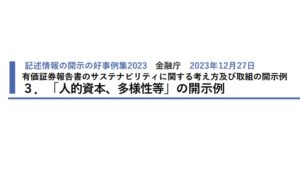
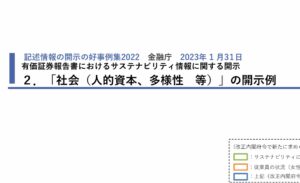
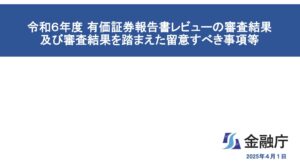
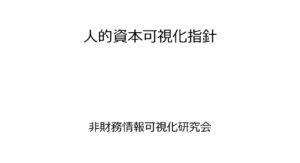
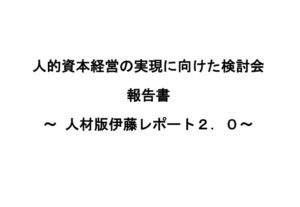
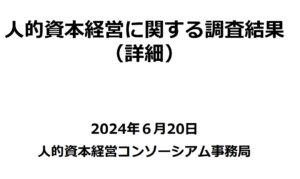
コメント